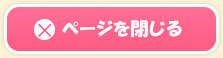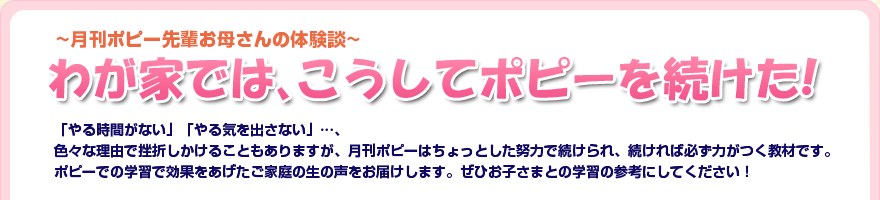

Case Study1 徳島県・川上家の場合
川上尚子さんは1女2男のお母さま。3人のお子さまは全員、2歳からポピーを始めた。長女は中3の最後までやり遂げ、目標であった国立工業高等専門学校に合格、現在同校の2年生。公立中学3年生の長男と、同2年生の次男は現役のポピー会員。インタビュー時点(平成23年夏)の学校成績は、それぞれ170人中24番、170人中9番と好成績をおさめている。部活も卓球部と陸上部に所属し活躍中。
川上家のポピー勉強法は?
学校の勉強が一番大事と考えていますので、ポピーは復習に使っています。授業で先生の話をしっかり聞いて、ポピーでちゃんと理解をしているかチェックします。時期によって、忙しかったり、体調が悪かったりで、ポピーをできずにためてしまうこともあります。ためてしまった分は土日に、それでもできなかったら夏休み・冬休みなどにまとめてやるようにしています。
川上家のポピーを続けるコツは?
子どもにまるなげしないことですね。時間を決めて「1時間だけやろう。ここまでやったら遊びに行っていいよ」などと声がけをし、小学校のうちは基本的に私がまるつけをしました。親がまるつけをすれば、子どもはやります。やりきったら表紙に大きな花まるをつけるようにしていたのですが、忘れると子どもから「花まるがない!」と文句を言われました。これは「やりきった!」という感じが嬉しかったからでしょうね。
小学生から中学生になって、やり方は変わった?
子どもが小学生のときはもちろん、中学生になっても親が何かしら関わりをもつことが大切です。上の子では一度失敗しました。中学に上がったときに、ポピーを渡して「ハイ、中学生になったから自分でやって」というようにしたら、宿題を優先してポピーをためてしまったり、解らないところがそのままだったり、これではいけないと、時々私が見て、やってないところや解けていないところをチェックして、解答や解説を読んであげたりしたこともありました。それで中学生になってからも親子の時間が持て、学校や友だちの話などもして親子のコミュニケーションもとることができました。
自主学習の習慣はつきましたか?
ポピーは塾と違ってやる時間が制限されず、融通が効きます。できないときがあっても後で時間をとってできますし、きちんとやりきれば確実に力がつきます。 学習習慣も気がつくと身に付いていたかんじですね。娘は高専に入ってポピーがなくなっても、高専のテキストを見て自分で考えて、問題にとりくむようになっていました。ポピーは最初に問題をどうやって解くかの解説がしっかりしていて、「答えとてびき」にも解き方がわかりやすく載っているので、自主学習するくせがついたのでしょう。
塾代0円、学力がついた!
子どもは高校入試など目標ができれば頑張るようになりますが、その時には基礎力が大切だと思います。基礎力となるのはやはり学校の勉強です。基礎力は、教科書にあったポピーで身に付けさせることができました。うちでは3人とも塾には通わせていません。それで部活にも熱中できます。ポピーを続けるには親の努力も必要ですが、私は「これで塾代が浮く」と思ってがんばれましたね。
※学年・学齢は取材時のものです。