
とけいあそび~時計の読み方「何時かな?」②
かんたん べんり 出先でもできる ちょっと知的な親子あそび
幼少期の子どもにとっては「あそびがまなび」です。
楽しく取り組んで好きになることがいちばん!
親子で楽しく、かんたんに取り組めて、まなびが好きになるあそびをご紹介します。
とけいあそび~時計の読み方「何時かな?」
手作り時計で「ちょうど〇時」や「〇時半(30分)」を覚えたら、5分刻みの長針の読み方へと進みましょう。
できれば長針と短針が連動して動く時計盤を準備し、実際に長針や短針を動かしながら、時刻のあてっこをしましょう。

参考:「小学ポピー1年生」とけいのよみかたセット時計盤
「ちょうど〇時」「〇時半(30分)」に親しみ覚えるあそびは、こちらでご紹介しています。
1.何時何分かな? あてっこ遊び
「ちょうど〇時」や「〇時半(30分)」の後は、いよいよ、3時5分や3時45分など、5分刻みの時刻の読み方に挑戦です。でもその前に…長針を動かしながら、〇分を読みましょう。
★最初は長針だけの手作り時計を使って、5とびの数え方に慣れましょう。

※長針だけの紙皿時計写真イメージ
長針を1・2・3…と動かしながら「5・10・15…」と声に出して数えましょう。
★長針をいろいろな数字に合わせて、「何分かな?」をあてっこしましょう。
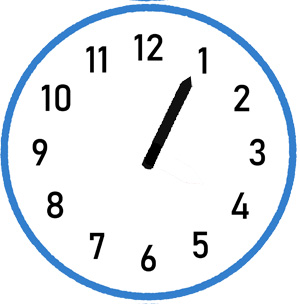
親「ここは何分かな?」
子「1だから、5分だよ」
親「すご~い!」
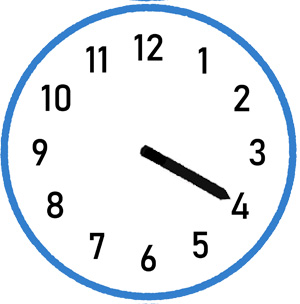
親「じゃぁ、ここは何分?」
子「えーっと、5・10・15…20分だ!」
親「あたり!」
こんなふうに、まず長針だけを使って、長針の読み方に慣れてきて…
長針が指しているところを見て、ぱっと答えられるようになるとすごいですね。
★何時何分かな 長針と短針が連動して動く時計盤を使って
長針で〇分は読めるけれど、短針で〇時を読み取るのが難しいですね。
最初はゆっくり数えていきましょう。

親「これは何時かな?」
子「3時!」
親「正解!」

親「じゃあ、これは、何時何分かな?」
子「短い針は3、長い針は2のところだから、3時10分だ」
親「すごいね。じゃあ次はこれ!よく見てね」
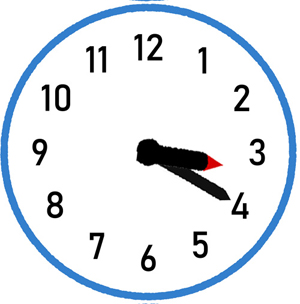
親「何時何分かな」
子「3時20分だ」

親「これは?」
子「3時半」

親「すごい! これは?」
子「3時…45分!」
このように、問題を出しながら、短針の動きに注目させましょう。
例えば3時5分のときと3時45分の短針の位置を比べて、どちらも短針が4を超えてない間は3時と読むことを知らせます。
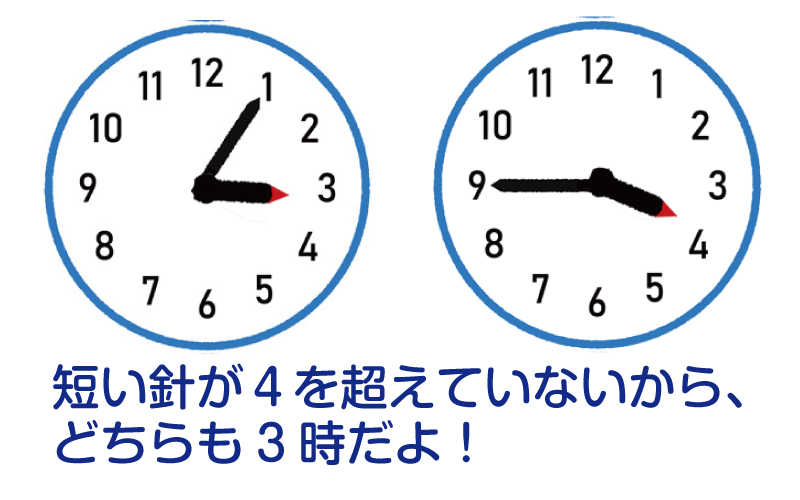
最後に長針が一周すると、短針が次の~時を指すことが意識できます。

親「これは?」
子「長い針が12になったら、短い針もちょうど4のところに来た。4時だ」
文字盤が色分けしてある時計を使うと、わかりやすいですね。
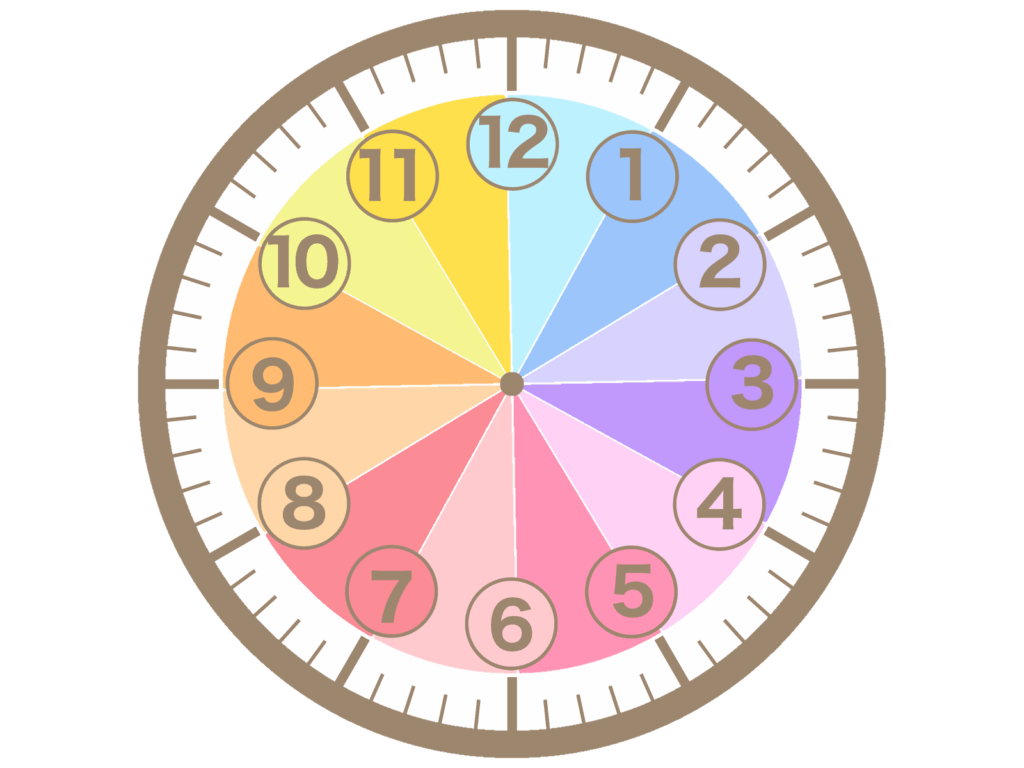
2.ジャンケンゲーム(5分刻み)
長針と短針が連動して動く時計盤を、人数分用意しましょう。
①スタートの時刻と、ゴールの時刻を決めます。(例えば12時スタート&2時ゴール)
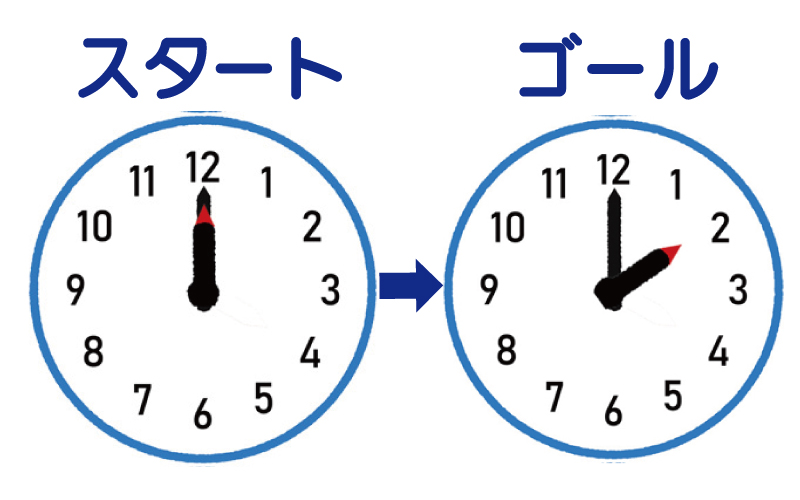
②ジャンケンをして勝った人が、長針を5分単位で進めます。
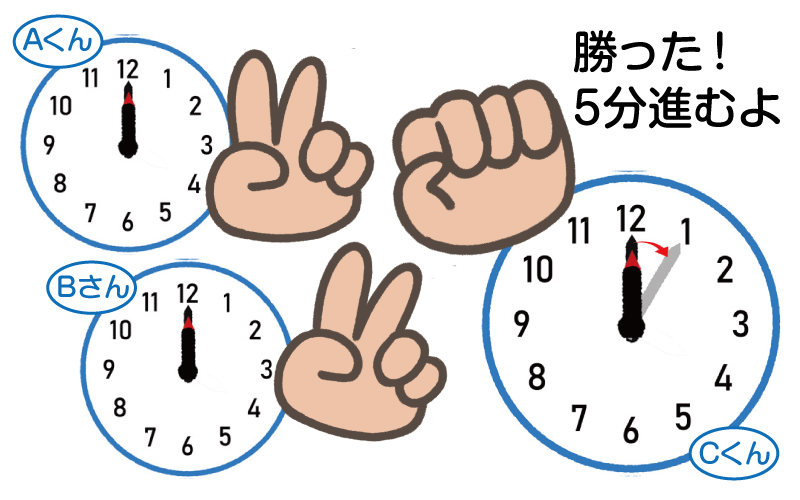
③先にゴールの時刻を超えた人が勝ちです。
「グリコ」のように、グーで勝ったら5分、チョキで勝ったら10分、パーで勝ったら25分進む!
こんなルールにしてもおもしろいですね。
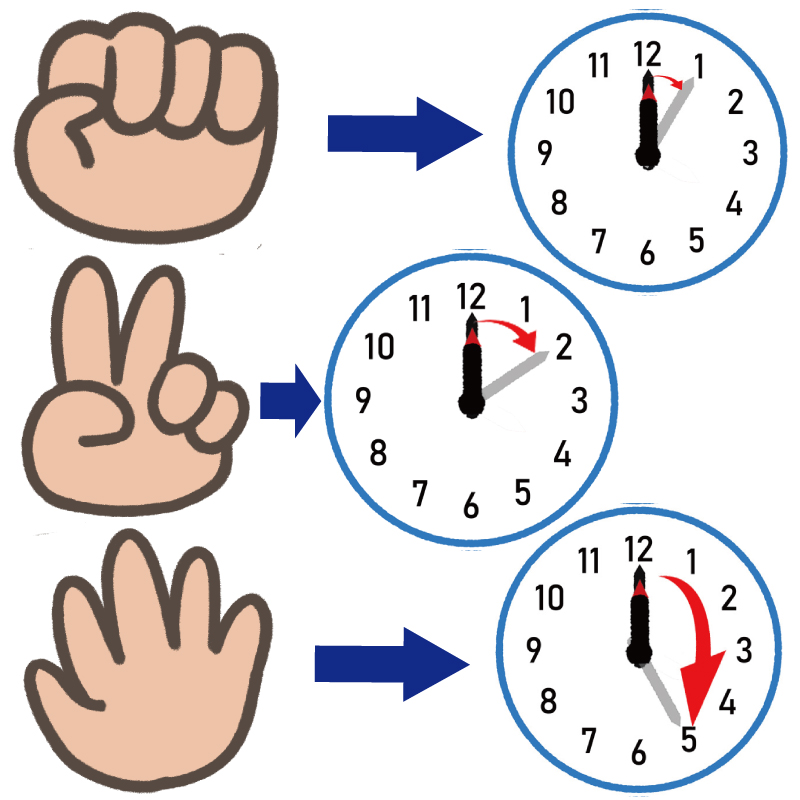
慣れてきたら1分刻みで進めたり、スタート・ゴールの時刻を変えたりしても良いですね。
ムリに教えなくても良いです。お子さんからこんな言葉が出たらうんとほめてあげましょう!
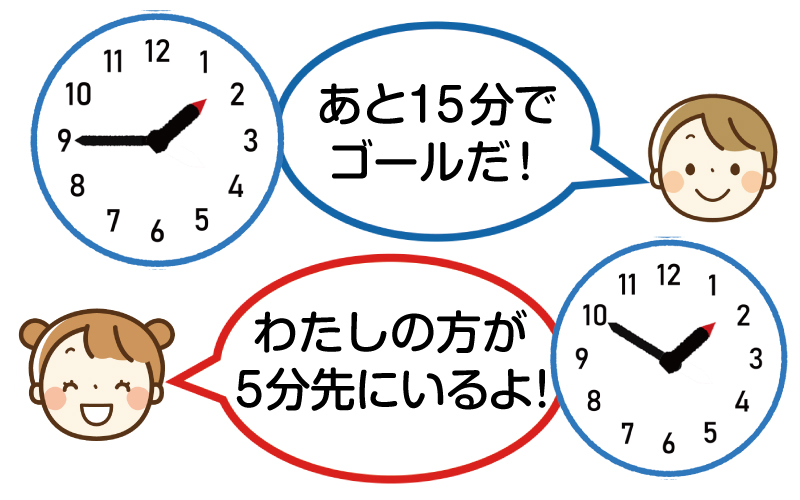
3.時計を生活に活かそう
生活リズムを整えていくための時刻も、少し細かく〇時〇分で表すことができますね。


時計を見ながら、お子さんと約束の時刻を決めましょう。
時計の絵に長針と短針を書き込んで、約束の時刻を「見える化」しておきましょう。
守れたらカレンダーに花丸を付けていくなどすると、楽しみながら、生活リズムを整えていく工夫ができます。
とけいあそびで「時計の読み方」に親しんで…
小学校では1年生の前半に「何時、何時半」の読み方、後半に「何時何分」の読み方、2年生で「時刻と時間」を学習します。
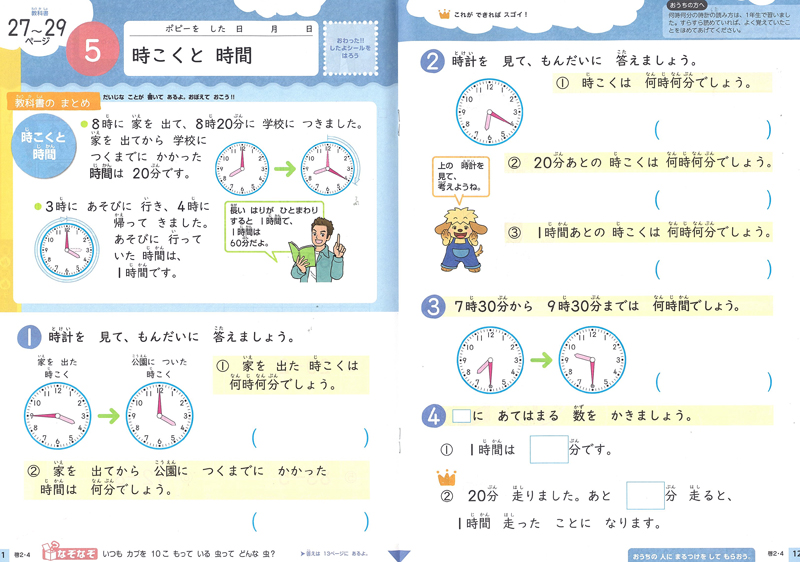
『小学ポピー2年生』算数ワークより
「ちょうど〇時」「〇時半(30分)」に親しむあそびは、こちらでご紹介しています。
小学1年生の算数で学習する「時計」。学び方のヒントは、こちらでご紹介しています。

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育



