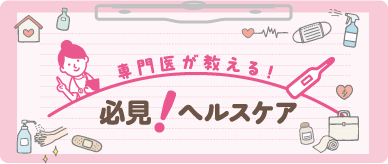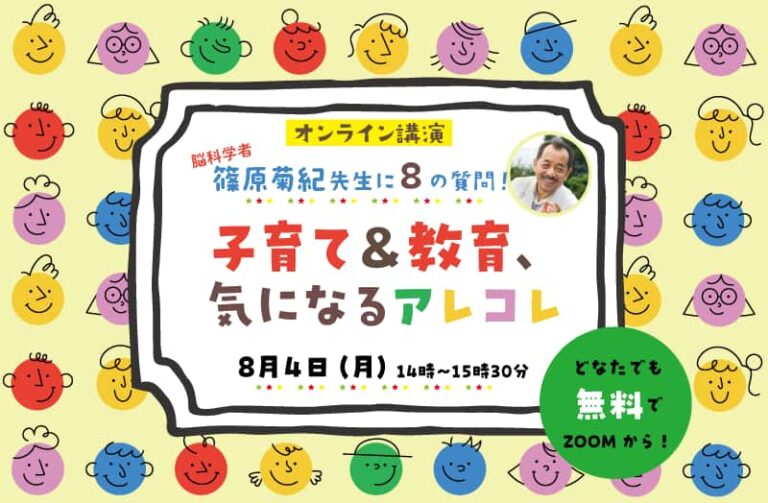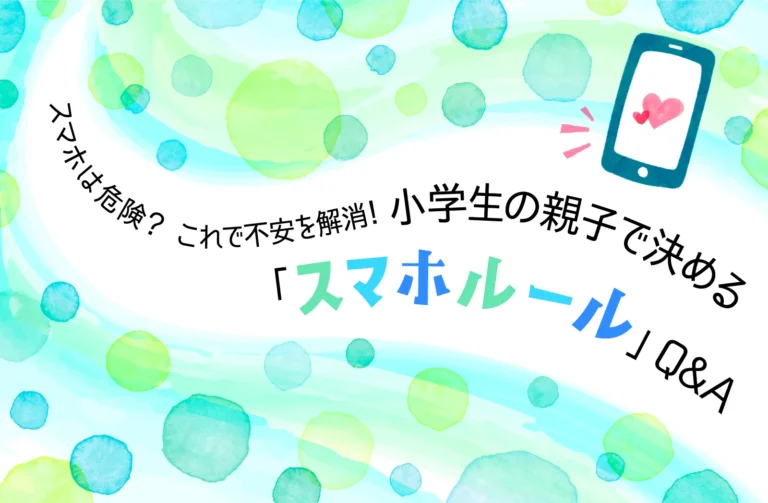小児科医が教える! 嘔吐時の着目点と嘔吐処理・症状別ケア
必見!ヘルスケア
目次
- Q.宮野先生 教えて! 嘔吐がひどい時、冬の感染症において特に懸念すべき子どもの様子は?
- 冬の感染症~原因と症状~
- 《感染性胃腸炎》原因と症状
- 《インフルエンザ》原因と症状
- 《溶連菌》原因と症状
- ◇症状主に、のどに炎症が出ます。また、体や手足に小さくあかい発疹が出たり、舌にイチゴのようなブツブツができたり(イチゴ舌)します。発熱もしますが、3歳未満ではあまり熱は上がらないことも。抗生物質を飲んで1日半ほどで登園可能になりますが、合併症などを防ぐために、病院でもらう抗菌薬は飲み切ることが大切です。自己判断で辞めずに、処方される10日分ほどを医師の指導どおりに飲むようにしましょう。
- 冬の感染症~家庭での症状別ケアと嘔吐の処理~
- しっかりと予防対策をして、元気に過ごそう!
家族みんなの健康のために、知っておくと安心なヘルスケア。今回は、冬に流行する傾向にある、感染性胃腸炎・インフルエンザ・溶連菌について詳しく解説します。
嘔吐症状が出る傾向にあるものが多いため、嘔吐した際の処理や症状別ケアについてもご紹介。小児科医の宮野孝一先生(みやのこどもクリニック 院長)にお話をうかがいました。

宮野 孝一 先生
みやのこどもクリニック 院長
日本小児科学会認定専門医、日本アレルギー学会認定専門医。ぜんそくやアトピー性皮膚炎などの診療にも積極的に取り組む。
Q.宮野先生 教えて! 嘔吐がひどい時、冬の感染症において特に懸念すべき子どもの様子は?

①3時間以上、嘔吐が続く
②固形物が食べられない
③尿が出ない
④嘔吐があるのに食べたがる
答えは③
いずれも辛い状態ですが、【尿が出ない=脱水状態】のため、特に緊急度が高く、夜間でも迷わず病院を受診しましょう。
他にも、目がくぼんでいる感じがする、涙が出ない、口の中が乾いているなどの場合は、脱水を起こしている可能性が高いため、すぐに病院へ。水分が摂れていれば、しばらく嘔吐が続いても様子を見て大丈夫です。
1時間に何度も吐くような症状の時は、胃腸が動いていないため食事は摂らず、水分のみを、一度に5cc(スプーンひとさじ/乳児は1cc)程度のほんの少量ずつ、こまめに飲ませます。OS-1か、なければ麦茶に少しだけ塩を混ぜたものでもかまいません。症状が落ち着いたら、軟らかく煮込んだうどんやおかゆから食事を再開しましょう。
※他に気になる容体として、冬の感染症ではありませんが、嘔吐や下痢に加えて血便、激しく泣いてぴたっと泣きやみ、またしばらくすると激しく泣くことを繰り返す「間欠的啼泣(かんけつてきていきゅう)」が見られる場合、腸重積にも注意が必要です。
冬の感染症~原因と症状~
《感染性胃腸炎》原因と症状
◇原因
ノロ・ロタウィルスが原因です。一般的に、ノロウィルスは11~1月ごろ、ロタウィルスは1月以降に流行ります。潜伏期間はノロウィルスが1~2日、ロタウィルスが2~4日。ウィルスが付着した食べ物やおもちゃ、患児のオムツを処理した保護者の手を介しての経口感染が経路です。ロタウィルスは、特に乳児がかかりやすい感染症です。
◇症状
どちらも症状はほぼ同じで、吐き気や嘔吐、下痢、発熱、腹痛です。子どもの場合は嘔吐が多く、大人は下痢の症状が強く出ることがあります。
《インフルエンザ》原因と症状
◇原因
インフルエンザウィルスが原因で発症します。潜伏期間は約2日。感染力が非常に強く、せきやくしゃみなどの飛沫感染や、おもちゃやドアノブなどを触ったあとに口や粘膜から入る接触感染、飛沫から水分がなくなったあとに飛び散ったウィルスを吸い込む空気感染によって、感染します。
A型・B型があり、それぞれ2種類の型があるため、最悪の場合、流行シーズンに4回かかるケースがあります。
◇症状
38℃以上の高熱・悪寒、頭痛、全身倦怠感や関節痛、筋肉痛、せき、鼻水、嘔吐などの全身症状が表れます。解熱後も2日間は安静に過ごしましょう。
A型では、まれに脳炎を発症することがあるので、注意が必要です。けいれんがとまらない、意識が遠のいている、熱せんもうなどが続く場合は、すぐに医療機関にかかりましょう。
《溶連菌》原因と症状
◇原因
溶連菌(溶血連鎖球菌)という細菌が原因です。潜伏期間は1~2日。飛沫感染や接触感染で感染します。
◇症状
主に、のどに炎症が出ます。また、体や手足に小さくあかい発疹が出たり、舌にイチゴのようなブツブツができたり(イチゴ舌)します。発熱もしますが、3歳未満ではあまり熱は上がらないことも。
抗生物質を飲んで1日半ほどで登園可能になりますが、合併症などを防ぐために、病院でもらう抗菌薬は飲み切ることが大切です。自己判断で辞めずに、処方される10日分ほどを医師の指導どおりに飲むようにしましょう。
冬の感染症~家庭での症状別ケアと嘔吐の処理~
◆症状別ケア(1)熱で関節が痛む場合
発熱すると、プロスタグランジンという物質が出ます。これが熱とともに痛みも引き起こします。関節痛の他、頭痛や筋肉痛もこの影響です。関節が痛むときは、冷湿布でクーリングするか、鎮痛剤を飲んでもよいでしょう。
◆症状別ケア(2)せきがなかなか収まらない場合
できるだけ部屋を加湿して、蒸気を吸わせましょう。寝入ってからせきが出る傾向があり、多くの場合、鼻水の症状も並行して現れます。サラサラのみずっぱなは、寝ている時に鼻水がのどに落ちて刺激になりやすく、また、粘度の高いあおっぱなの場合は鼻づまりから口呼吸になりやすいため、口からのどが乾燥して、せきにつながります。そのため、寝る前にしっかりと鼻をかんだり、吸引したりするなどで、せきが緩和されることがあります。
また、息苦しさを感じないのであれば、マスクをして寝ると、のどを保湿できます。せきどめは飲みすぎない方がよいケースもあるため、かかりつけの医師に相談しましょう。
◆症状別ケア(3)鼻水・耳だれが出る場合
冬の感染症は、のどから上に症状が出やすいため、目・鼻・耳といったつながった部位の症状にも気をつけたいところ。特に子どもは中耳炎になりやすいため、鼻水が出ている時はしっかりと拭き取ったり優しくかんだりとケアをしましょう。強くかむと耳を痛めることがあるため、片方ずつ優しく行うことがポイントです。耳の痛みを訴える時や、耳だれが出る場合は、耳鼻科を受診しましょう。
◆嘔吐したときの処理法

感染症での嘔吐の場合、吐いたものが衣類に付着したら、そのまま他の衣類と一緒に洗濯せずに、ザッとすすいでから、しばらく湯につけ置きしましょう。
また、吐しゃ物を素手で触らずに処理するために、こちらを用意しておきましょう。
- 消毒液(次亜塩素酸ナトリウム)
- ビニール袋
- 新聞紙かキッチンペーパー
- 長袖の使い捨てエプロン(ネットなどで入手できます)
- 使い捨て手袋
- マスク
(1)子どもが吐いたら、まず吐しゃ物に新聞紙などをかぶせて、ウィルスの飛散を抑えます。続きの処理は、子どもの対処後でかまいません。
(2)子どものケアが済んだら、エプロン・手袋・マスクを着用し、先ほどの新聞紙などで静かに吐しゃ物を拭き取り、ビニール袋に入れ、密閉します。
(3)次に、新聞紙かキッチンペーパーに消毒液をしみ込ませて、嘔吐した場所と周辺にかぶせてしばらく置き、同様に拭き取ります。
(4)着用したものは、拭き取ったペーパー類と一緒にビニール袋に二重に入れて封をします。換気と手洗いも忘れずに行ってください。
しっかりと予防対策をして、元気に過ごそう!
冬に感染症が流行しやすい理由として
◇気温の低さからくる抵抗力の低下
◇湿度が下がり、乾燥することによってウィルスが飛散しやすく、ウィルスの生存時間も長くなること
が挙げられます。
そこで、家庭での予防対策として
- 手洗い・うがい
- マスクの適宜使用
- アルコール消毒・熱湯消毒
- 加湿・加温
- 換気
が有効です。
手洗い・うがいはもちろんのこと、マスクの使用も状況によって取り入れることで、ウィルスの飛散や侵入を減らすことができます。
また、インフルエンザウィルスにはアルコール消毒が、感染症胃腸炎の原因となるノロ・ロタウィルスには熱湯消毒が有効です。手指消毒に加えて、手の触れるもの(おもちゃやドアノブなど)を100倍希釈した次亜塩素酸ナトリウムで消毒したり、80~85℃の熱湯消毒を行ったりすると効果的です。
1時間に5~10分間程度の換気で空気を入れ替え、加湿もしっかりと行いましょう。40~60%程度の湿度が理想です。加湿によって、のどの気道が保湿されてウィルスが付着しづらくなる他、空気中のウィルスの飛散が抑えられます。重さを含んで浮遊しにくくなるため、掃除をする際にも加湿をしてからがオススメです。
寒い季節も予防対策を欠かさず、元気に過ごしましょう!
この記事が含まれる連載はこちら

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育