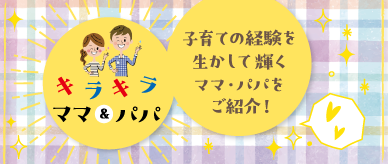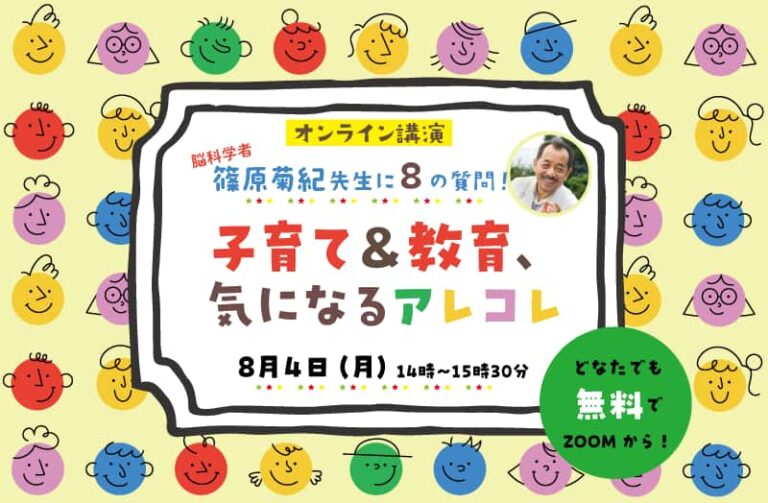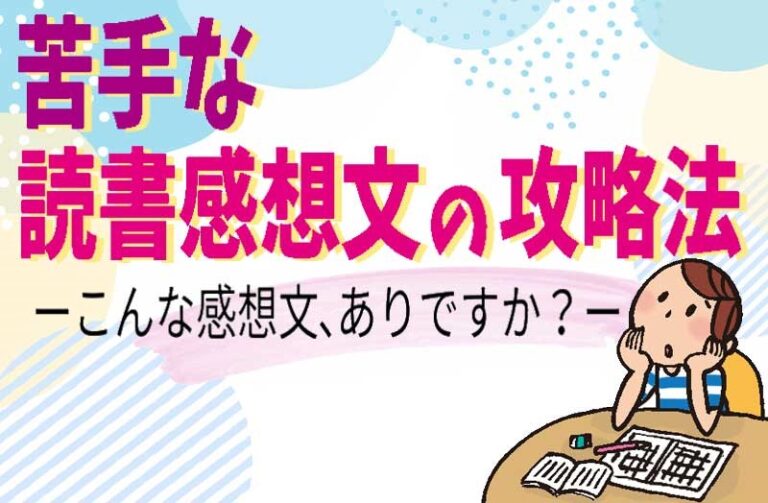【第2回】クラフト作家として活躍! おおしだいちこさん
キラキラママ・パパ
きっかけは、学生時代のボランティア「読み聞かせの会」

お母さんが保育士で、ボランティアで「読み聞かせの会」をやっていたといういちこさん。いちこさんも学生のころから、大型絵本の製作を手伝ったり、告知ポスターを作ったりしていました。「読み聞かせの会」に参加した子どもたちの楽しそうな様子を母から聞くたびに、子どもたちに喜んでもらえるクラフトを作る人になりたい、という想いが高まっていったようです。
念願のクラフト作家としてスタートするまで
子どものころから絵や工作が好きだったので美術系の大学に進んだものの、入学当初は将来についてははっきり考えていませんでした。しかし、母のボランティアを手伝ったことをきっかけに、子どもたちに喜んでもらえる製作をしたり、イラストを描いたりする仕事がしたいと思うようになりました。あれこれ模索し、保育士を経て、児童書や保育図書を得意とする制作会社に就職しました。
会社では保育図書を制作するチームで、編集を担当しました。保育図書の編集は、プロのクラフト作家さんに製作を依頼し、型紙を載せて読者が真似して作れるようにします。また記事の内容に合わせたイラストをプロに描いてもらいます。仕事をするうちに、どうすれば夢を実現できるのか見えてきたような気がしました。そして、子どもはどんなものを喜び、周りの大人(保育士)はどんなものを必要としているのかも学びました。
やがて、いちこさんは夢を実現させるために、会社をやめてクラフト作家側に転身。第一歩を踏み出しました。
時代はめぐり…

「大人の感覚と子どもの感覚は違うように感じます。大人は洗練された色味で落ち着いた表情の動物たちを好む人が多いとしたら、子どもはその逆。はっきりした色味のほうが興味をひくし、わかりやすい表情の方が親しみを感じるようです。また、子どもは身近な生活用品や廃材などでも十分に楽しく遊びます。完成された既製品のおもちゃでなくても、自分で遊び方を見つけます。子どもって好奇心の塊。遊びの天才なんです」と話すいちこさん。プロになってからも学びは止まりません。
クラフト作家としてのキャリアを積むなかで、いちこさん自身も出産し、母となりました。
保育園に通っていましたが、子どもが小さいうちは体調をくずしてお休みすることも多く、締め切り前は寝かしつけた後、夜中の作業となります。しかも、小さな頃は、夜中に何度も起きて泣きます。そのたびに作業を中断して寝かしつけ、あっという間に1時間…。常に寝不足と疲れとの戦いだったといいます。
そんなお子さんたち(姉弟)も、今では少し大きくなり、いちこさんといっしょに作業することも。まるで、お母さんの読み聞かせ会を手伝っていた、かつてのいちこさんのようですね。
撮影で出会う子どもモデルの楽しそうな表情がうれしくて
実は、「ほほえみ7月号・おうち縁日」の案・製作を担当してくださったのもいちこさんです。撮影当日は早くからスタジオ入りして、作品をセッティングし、子どもモデルの登場を待ちます。子どもモデルがスタジオ入りした瞬間のうれしそうな表情と、興味深々の様子を見るのは、クラフト作家としての醍醐味だそう! 子どもは正直なので、遊びがおもしろいと撮影が終わってもそのまま遊んで楽しみます。
赤ちゃん向けのおもちゃを製作することもあります。壊れないように、安全であるようにを基本に、興味をもって何度も遊びたくなるものを考えます。そうして出来上がった作品が、撮影で赤ちゃんモデルと出会ったときは、「作ってよかった」と思う瞬間だそう。ときには、撮影が終わっても赤ちゃんがおもちゃで遊び続けたくてぐずったり泣いたりしてしまうこともあるそうです。
これからもクラフト作家として

いちこさんの上のお子さんは、現在小学生です。先日、ふと上の子の音楽の教科書を見たら、なんと、いちこさんがイラストを担当したものだったそう。自分が手がけたものを、わが子が使うという喜びを実感。うれしくて、思わず家族や親戚に報告したいちこさん。でもお子さん自身は、誰にも言わず、「友達は知らない」のだそうです。きっと照れくさいのかな。
いちこさんの今後の目標は「わが子も楽しめる作品を作ること」だそうです。今までは乳幼児向けのクラフトが多かったのですが、子どもの成長に合わせて、もう少し上の年齢の子が楽しめる製作を考えてみたいのだとか。そのうち、いちこさんの考える小学生向けのクラフト製作本が本屋さんに並ぶかもしれませんね。
おおしださんの個人インスタグラムでは、簡単手作りおもちゃや簡単なおりがみのアイデアを紹介しています。

@ichiko_oshida

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育