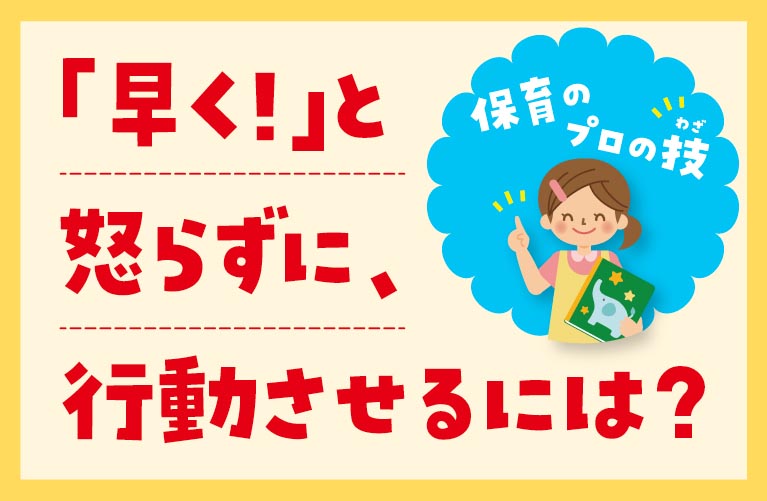
保育のプロに聞く! 行動が遅い子を「早く!」と怒らずに済むコツ
保育のプロの技
毎日の子育てをスムーズにするヒントをNPO法人家庭的保育支援協会代表理事の須貝美香先生に教えていただきました。
目次
子どもが言うことを聞いてくれないと、つい「早くしなさい」と叱ってしまい、気づいたらいつもガミガミ怒っている、と悩まれるかたも少なくないようです。お子さんもおうちのかたもストレスを感じずに行動を上手に促すヒントについて、保育現場を熟知する須貝美香先生にお話をうかがいました。

須貝 美香(すがい みか)先生
保育士として保育園勤務を経て、1997年に在宅保育を開業。現在は、認可園3園を運営し、台湾と上海で活動しながら、子育てアドバイザーとして企業や自治体などで家庭的保育に関する研修講師、保育士や保育施設経営者研修、民間保育園の園内研修などを多数行う。保育者に寄り添い、子ども・子育て家庭に温かい支援に貢献している。著書に『漂流する待機児童たち』(幻冬舎)『保育士が教える「子育て」の正解』(幻冬舎)がある。
プロの技1:「早く〇〇して」を理由や想いに気付かせる言い方に変える

“どうして早くしなければいけないのか”を子ども自身が理解することが大切
お子さんの行動を促すためには、「なぜ早くしなければいけないのか」を本人が理解できるようにしっかりと説明してあげることが大切です。たとえば保育園に遅刻しないためならば、「保育園に遅刻するから早く着替えなさい」だけでは不十分。「先生もお友だちも保育園で待ってるよ、早く着替えるとお友だちとたくさん遊べるよ」と、急ぐことでどんないいことがあるのか、どうして急いだ方がいいのかを伝えてあげるようにしましょう。そうすることで、「お友だちに会いたいから早く着替えよう」とお子さん自身が自主的に判断して行動できる習慣がついてきます。
共感的・肯定的な言葉がけや会話を
本人が「行動したい」と思えるようにもっていくためには、ご家庭での日頃の会話がとても大切です。みなさんは、毎日の生活でお子さんとどのような会話を交わしていますか?
「○○しなさい」「どうしていつも言うことをきかないの?」などの声かけばかりだと、お互いに嫌な気持ちになってしまいます。普段の会話を振り返ってみて、 「…しなさい!」「…しちゃダメ!」といった命令的・指示的な言葉や、「うるさい!」「なんでできないの!」といった感情的・威圧的な言葉が多くなっている場合は、「…したいけど、どうかな?」「今のあそびも楽しいね!こんどは…しようよ」など、共感的・肯定的な言葉を使うように心がけてみてください。食べるのが好きなお子さんなら、「今日の給食○○だよ、楽しみだね」といって保育園に行く楽しみを一緒に見つけてあげるのもいいですね。そうすることで、お子さんの行動はみるみる変わっていきます。
プロの技2:毎日の生活リズムをスムーズにする

明日の服は、天気予報を活用して、前日の夜に用意
朝の忙しいときにその日着る服を選ぶのは大変。前日の夜にできることは済ませておきたいですね。そこで、テレビの天気予報を活用するのがおすすめです。天気予報は毎日決まった時間に放送されるうえ、数分で終わるので、習慣作りにとても役立ちます。夜なら時間的にも余裕を持って服を選ぶことができますし、ゆっくり会話もしやすいもの。「明日は雨だから、ママは傘を用意しようかな。○○ちゃんはどんなお洋服を着ようか?」とお話しながら一緒に明日の準備を進めてあげてください。
健康を保つ大切さを伝えながら、歯磨きや早寝・早起きの習慣を
毎日の生活リズムを整えることはお子さんの健康を維持するためには欠かせません。それをきちんと本人にも伝えてあげると、自分で理解してひとつひとつの行動ができるようになっていきます。「歯磨きしなさい!」とか「早く寝ないと明日起きられないでしょ」という言葉だけでは、なぜその行動をしなければいけないのかが十分に伝わりません。
たとえば、「歯磨きをしないで虫歯になっちゃうととっても痛くなるの。だけど、ママは代わってあげられないから○○ちゃんのことが心配だな」とか、「たくさん寝ないで病気になったり、お熱が出たりしちゃうと、○○ちゃんがかわいそうだとママは思うのよ」など、ママやパパがお子さんを大切に思っている気持ちを伝えながら、体調管理の大切さを教えてあげましょう。
五感を刺激して、目覚めやすい環境づくりを
朝の目覚めをよくするためには、五感をうまく活用することがポイントです。お子さんが起きる30分くらい前にはカーテンをあけて太陽光を入れ、視覚を刺激しましょう。お味噌汁やお野菜のいい匂いは嗅覚にはたらきかけます。冷暖房や太陽の光により外気温が変わると、触覚を刺激することにもつながります。起きる時間になったら、ここで聴覚の刺激です。「朝だよ、ご飯ができたよ」と声をかけてあげましょう。このように五感を刺激していくことによって、徐々に目覚める準備が整っていき、気持ちよく起きられるようになっていきますよ。そして、朝食を食べることで味覚が刺激されて脳がしっかり覚醒します。
プロの技3:時間の感覚を楽しく身につける

楽しく時間をまなべる「砂時計」を活用
特に幼児期のお子さんは、時計が読めていても時間の感覚はまだ身についていません。着替えや食事、お風呂などの日常生活を題材にして「○○ちゃんは何分かかると思う?」とクイズ形式にして、楽しく時間の感覚を育ててあげましょう。
そのためにぜひ活用していただきたいのが砂時計です。砂時計はおもちゃのような感覚でお子さんも手に取りやすいもの。サラサラと砂が流れ落ちていく動きが楽しいので、楽しみながら時間の感覚を身につけるのに最適の道具です。3分、5分、10分、15分など、カラフルな砂時計を使い分けるのがおすすめです。
時間の感覚は一定ではないことも伝えよう
たとえば「15分間」というテーマを決めて、砂時計やスマホのストップウォッチアプリなどを使って、「さまざまな出来事の15分間」を体験させてあげましょう。同じ15分間でも、ニュース番組とアニメ番組とでは“感じ方が違う”という具合で、「楽しい時間って、すぐに過ぎちゃうんだね」ということを普段から話題にしておくのです。あそぶことに夢中でなかなか帰ろうとしないときでも、体感時間にはズレがあることをお子さんが理解していれば、「もう十分遊んだから帰ろうね」とおうちのかたが声かけをしたときに受け入れてくれやすくなります。いろいろなリズムの時間感覚を育てるためには、お風呂で「100数えたら上がろうね」とお子さんと一緒に数を数える練習をするのもおすすめです。2才なら1~30まで、3才なら1~60まで、4才なら1~100まで、5才以降1~120までが目安となります。1分が60秒、1分の半分が30秒、120は2分と教え込まなくても、ちょっとした時間の感覚を身につけるだけで、小学生になったときに勉強を楽しく感じて理解が深まります。
まとめ:小さいお子さんにこそ、ていねいに言葉を尽くして説明しよう
小さなお子さんはまだまだ他人の気持ちをおもんばかって行動することができません。お子さんが自ら気持ちよく行動できるよう、できるだけていねいに説明してあげることが大切です。“何のためにその行動が必要なのか”、“おうちのかたはなぜその行動をしてほしいと思っているのか”。こういったことを言葉を省略せずに順序立てて伝えてあげることでお子さんの理解力が育まれ、状況を読んで自分で行動することができるようになっていきます。
約束ごとを完璧に守れる人はいません。それは私たち大人も同じこと。おうちのかたが作ったルールを「こうしてね」と押し付けても、ルールが自分にとって必要で大切であるとお子さんが理解していなければ、逆効果になってしまいやすいものです。
急いでいたり焦っていたりすると、目の前の行動をすぐに変えてほしくてつい「早く」という言葉をお子さんに使ってしまいやすいものです。しかし長い目でみると、お子さん自身が行動の理由やおうちのかたの考えなどを理解できるように言葉を尽くして導いていくことが、結局は近道となります。ぜひ日頃からお子さんとコミュニケーションを取りながら、すすめてみてくださいね。
取材/遠藤祥子 文/金子千鶴代 編集協力・イラスト/東京通信社
この記事が含まれる連載はこちら

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育