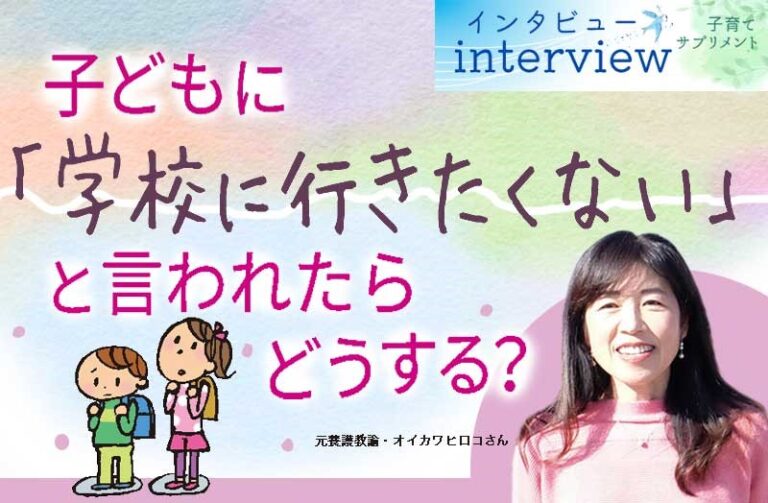
【行き渋り】子どもに「学校に行きたくない」と言われたらどうする? 専門家が事例や対処法を紹介
インタビュー 子育てサプリメント
子育てに関する心配や困りごとは尽きません。肩の力がふっと抜けるような、子育ての処方箋をインタビューでお届けします。
子どもが「学校に行きたくない」と言ったら、親としてどうしたらいい? どんな言葉をかけるべき? 40年にわたり小学校の養護教諭を務め、保健室で子どもとの関わりはもちろん、保護者や先生たちなど大人の悩みや不安にも寄り添った、オイカワヒロコさんに対処法を伺いました。

オイカワヒロコ さん
神奈川県三浦市の小学校で、40年にわたり、養護教諭として勤務。(2021年3月退職)。現役時代、子どもを触発する楽しい教材を駆使した保健教育に定評があり、それらの実践は新聞や雑誌で度々紹介・発表される。研修会や講演などを通して、後進の育成などに当たっている。
「気持ちが悪い」は心がザワザワしているサイン
――学校の保健室というと、体調の悪い子が休んだり、病気やけがの手当てをしたりする場所というイメージがあります。
「保健室には、心が疲れていたり、不安や悩みを抱えていたりする子どもも来ます。行き渋りの子や、学校に来ても教室に入れない子も…。
私の経験では、明らかな体調不良ではなく、心の不調が芯にある子が多かった印象です。具合が悪くないときでも、居場所としてふら~っと来て休み時間を過ごしていい場所、と保健室を位置づけていたせいもあると思います。」

――心の不調が増える時期はありますか?
「環境が変わる新年度は、注意が必要です。また、GW明けも、心のエネルギーがたくさん必要になる時期です。」
――心が不調になる原因は?
「原因はさまざまで、本人にもよく分からないことの方が多いのでは。それに、近年、『ハイリー・センシティブ・チャイルド(ひといちばい敏感な子ども)』が増えている気がします。
たとえば、友だち同士がケンカしている雰囲気に耐えられず、いたたまれない思いで教室にいるのがしんどくなる、などです。」
――悩みや不安を抱えている子のサインは?
「子どもは『気持ちが悪い』と訴えることが多いです。」
――吐き気がしたり、胃がムカムカしていたりするのですか?
「それは大人の思い込みです。実は『よくわからないけど、気持ちが落ち着かない、しっくりこない』と訴えているケースが多いです。
試しに『気持ちが悪いところを触ってごらん』と言うと、『え~!?』と考え、場所や部位を限定できないのです。その後、膝を触った子もいました。」
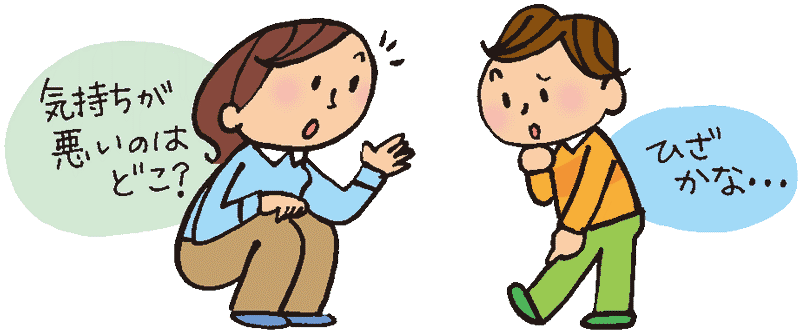
――膝?
「他に訴える場所が思い当たらず、たまたま目にはいったのが膝だったのかもしれません。
腹部を手で押さえる場合も、吐き気があるというより、五臓六腑がゾワゾワして、それを『気持ちが悪い』と表現しているのです。気持ち・心持ちの座りが悪い、って感じでしょうか。」
――どう対処すべきでしょうか?
「その子の訴える『気持ちが悪い』の原因は何なのか。大人が勝手に理由を決めつけず、話を聞きながら一緒に探していくことが大切です。」

行き渋りの事例と対処法
――子どもが「学校に行きたくない」と言ってきたら?
「ひとくくりに行き渋りと言っても、いろいろなケースがあります。
たとえば、明らかな原因がわかって、その原因が取り除けるケースですが、思い出すのは、Aさん(小学2年生の男子)のこと。
Aさんは、公共施設の武道場で剣道を習っていたのですが、ある日、いつもより早く練習が終わる日がありました。お母さんはうっかりそのことを忘れていて、いつもの時間にお迎えに行きました。
すると、Aさんは、武道場の外で、ひとりぼっちでお迎えを待っていたそうです。それ以来、不登校になりました。」
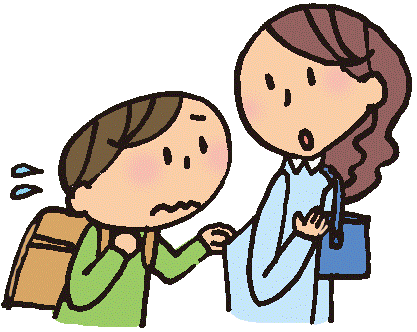
――真っ暗な中、不安だったのでしょうね。
「とっても不安だったのでしょうね。それからは、登校してしまうと、もうお母さんに会えないんじゃないかと心配で、学校に来られなくなったのです。いわゆる『母子分離不安』です。」
――どう対処したのでしょうか?

「まず、『休み時間、いつでも別室にいるお母さんに会える』という環境を整えました。その後、『いつでも電話して声が聞ける』など、ゆっくり段階を踏んで、不安をやわらげていきました。その結果、『お母さんはいなくならない』と感じられ、元気に登校できるようになりました。」
――他のケースは?
「小学6年生のBさんは、体育館や視聴覚室は大丈夫だけど、教室という空間が辛いと感じるようになり、教室に入れなくなりました。
思春期への過渡期で、自分でも説明がつかない心の変化があったのかもしれません。」
――子どもによって、原因はさまざまですね。
「大人の思い込みで原因を決めつけず、いろいろな方向にアンテナを張り、原因や解決のチャンスを見逃さないようにしたいですね。」
――ズバリ、学校に行かせる/休ませるの基準は?
「本当に学校に行きたくないのか、本当は行きたいけれど特定の理由があって、それを取り除いて欲しいという訴えなのか、そこは見極めてあげてほしいと思います。
親の知らない子ども世界の中での出来事が原因の場合は、いくら頑張っても知るよしがない。
子どもが語ってくれるのを気長に待つか、情報を持っていそうな学校の先生や養護教諭に尋ねてみるのもいいです。」
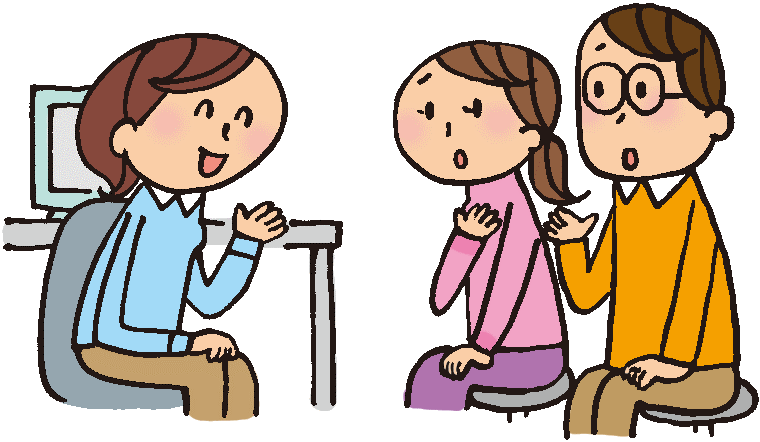
周りの力を借りて子育てを
――親御さんが子育てに悩んだときは?
「おじいちゃんおばあちゃん、ママ友など、SOSを出せる人に力を借りてみてはどうでしょう。泣き言や話を聞いてもらったり、ガス抜きできたり、実は同じ悩みを共有・経験していたり、自分には相談できる相手がいると思えるだけで、気持ちが楽になります。もちろん、養護教諭も利用してください! 遠慮しないでね!」
――子どもが元気で過ごすために、家庭で気をつけたいことは?
「子どもにとって、おうちが安心安全でホッとできる場所であれば、それでいいんです。
たとえば、共働きのおうちなら、バナナやメロンパンなど好きなおやつを用意しておく、「おかえり」のメッセージを置いておくだけでもOK。
空腹ってとってもさみしいし、悲しいから。逆にみかん1個でもプリン1個でも胃袋が満たされると、それを用意してくれた愛情も素直に感じられると思うんです。胃袋で感じた親の愛情は、体に沁みます。子どもは将来、その愛情を次の世代に伝えてくれるでしょう。」

ライター:ひだいますみ(スタジオ・ペンネ)
イラスト:きつまき

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育



