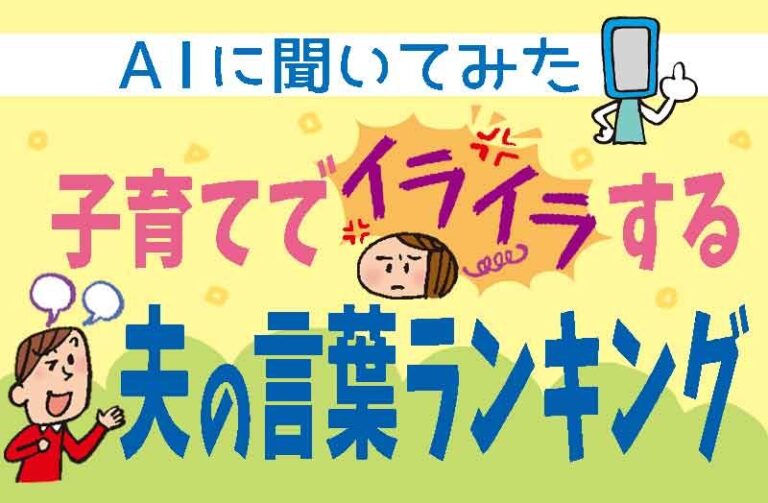笑い飯・哲夫さんが語る「学び」と「子育て」 〜哲夫流・教育観(後編)
インタビュー 子育てサプリメント
今、子どもに必要な力とは。子どもの教育に良くないものとは。お笑い芸人・哲夫さんが教育や子育てについて熱く語ります。
お笑い芸人・「笑い飯」の哲夫さんが語る教育観、後編です。

哲夫(てつお)さん
1974年奈良県出身。関西学院大学文学部哲学科卒業。2000年に西田幸治と漫才コンビ・笑い飯を結成。2010年、Mー1グランプリで優勝。賞レースで結果を残す一方、相愛大学人文学部客員教授を務めるなど教育活動にも注力。著書に『えてこでもわかる 笑い飯哲夫訳 般若心経』(ワニブックス)『がんばらない教育』(扶桑社)など。
地元の暮らしと子育て
今、僕は奈良の地元で暮らしてます。上の子は小学校2年生になりました。学年に1クラスしかないような田舎の学校です。子どもたちに学校がある環境を残したいので、廃校にならないよう、企業を誘致したり、新しく住んでくれる人を増やすような工夫も必要やなと思ってます。
奈良の生活で実感するのは、「ここで暮らすメリット」がちゃんとあると、人は集まってくるということ。僕自身、都会の便利さとはまた違う「地域ならではの良さ」を、子育ての中で感じてます。子どもにとっては、大人が思ってる以上に「地域」が教育の舞台なんやと思います。
大人が子どもたちにするべきこと
一番の問題意識は、やっぱり地球環境です。25年前の最高気温は32度くらいだったのに、今は37度、体温以上になることも珍しくない。これはもう異常やと思います。僕が小中高と育った時代は、教室にクーラーなんてなかった。夏も汗だくで運動してました。でも今はクーラーがなかったら活動できない。完全に環境が変わってしまっています。
でも、みんな「大変やなぁ」とは言いつつ、本気で対策しようとしてる人は少ないんちゃうかなと思うんです。僕らが受け継いだ「平和で過ごしやすい日本」を、次の世代にもちゃんと渡せるか。これは大人としての責任だと思います。僕が農業をやっていても自然の変化は肌で感じます。子どもたちに残すべきは「便利な商品」じゃなく「健康な地球」そのものだと強く思います。
子どもはスマホに頼ったらあかん
「子どもの教育に良くないものは何ですか?」と聞かれたら、僕ははっきり「スマホや」と答えます。もちろん便利な道具ですが、使い方次第で子どもの想像力をそいでしまう。すぐ答えが出てしまう環境は、成長にとって危険だと思うんです。

うちの子どもにはスマホを持たせてません。16歳か18歳ぐらいになってからで十分と考えてます。小さい頃からネットで検索して何でも簡単に答えが手に入ると、自分でイメージを膨らませる力が育たんのですよね。
僕が子どもの頃に与えられたのは自然だけ。欲しいものは自分で考えて作り出すしかなかった。だからこそ、想像力が鍛えられたと思うんです。
昔はファミコンでも、2人用で友達と遊ぶならまだ人間関係を育てられたけど、ひとりでこもってやるロールプレイングゲーム、これは危ない。道具や遊び方ひとつで、人とのつながりや想像力が左右される。スマホはその極端な例やと思います。
自然や遊びから得た「学び」
僕の子ども時代は、遊び道具なんてほとんどお下がりやったんです。ばあちゃんが親戚からもらってきたブロックが唯一の遊び道具。それで自分のイメージを形にしようと工夫して遊んでました。あれが僕の「物をつくる楽しみ」の原点です。
「遊ぶものがなかったら退屈ちゃうん?」って言われるかもしれんけど、全然そんなことなかった。河原に、種がはじけるときに「ポン」って音がする植物があって、ひたすらそれを触って遊んだり、毎日が発見の連続。自然は飽きさせへんのです。
自然の中で育ち、農業をやっている僕は、新幹線から景色を見てるだけでも楽しい。「この田んぼ、早めに田植えしたんやな」とか「この作物は元気やな」とか、景色の中にいろんな情報が詰まってることがわかるからです。タモリさんは石が好きなことで有名ですが、石を見ればどこにいても楽しめるのと同じで、自然を知っていると世界が広がる。子どもたちにも、そういう「自然や遊びから学ぶ力」を身につけてほしいです。

(写真はイメージです)
近所の人に叱られた経験は必要だった
僕の家は両親も祖父母もみんな働いていて、子どもの頃はけっこう放っておかれることも多かったんです。でも不思議と道を踏み外すことはなかった。振り返ると、それは親以外の「大人」と出会う機会が多かったからやと思います。
近所のおっちゃんやおばちゃん、じいちゃんの知り合いの農家さん、ばあちゃんの友達。そういう人たちに可愛がってもらい、時には本気で叱られたことが、自分の社会性を育ててくれた。例えば、料理を作ってくれたばあちゃんの前で「おかんの作った方がおいしい」と言ったら「作った人の前でそんなこと言うたらあかん!」とめちゃめちゃ怒られたり(笑)。ロケ先でラーメンにいきなり胡椒をかけるスタッフを見て、「あれは作った人に失礼や」と思えたのも、昔怒られて学んだからだと思います。
親に叱られると甘えや言い訳も出るけど、他人の大人に叱られるとそれは通用しない。だからこそ、心に残るんです。高校時代も、電車の中で騒いでいたら「うるさいぞ」と知らんおっちゃんに怒られたことがありました。あのときはムッとしたけど、大人になってみれば「ほんまに正しかったな」と感謝できます。
教育って、そういう「時間差で届く贈り物」みたいなものだと思うんです。叱られた意味はすぐにはわからんけど、10年後、20年後に「ああ、そういうことやったんか」と気づく。その「気づき」が自分を形づくっていく。
先生も親も地域の大人も、子どもに布石を置いていく役割があると思います。
地域の人とつながること、環境の変化に向き合うこと、スマホに頼らず想像力を育てること。
哲夫さんが大切にしているのは「子どもに何を残せるか」という視点です。
そして親や先生だけでなく、地域のいろんな大人が子どもに関わり、時には叱ってくれる。その積み重ねが、子どもを社会へ送り出す力になるのですね。
哲夫さん、どうもありがとうございました。
取材・構成/甲斐ゆかり(サード・アイ)

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育