
気持ちを切り替えられる子になるには? レジリエンス教育のすすめ
インタビュー 子育てサプリメント
「失敗やうまくいかない出来事を乗り越える心の力」をのばす教育について、専門家にうかがいます。
目次
「うちの子、すぐにあきらめちゃう」「いやなことがあると、ふさぎ込んでしまって…」。
いやなことがあったとき、気持ちを切り替えて、あきらめずに乗り越えられる子になるには、どうしたらいいのでしょうか。
そんな力を伸ばすのが、レジリエンス教育です。年間100校もの学校で講演会を行っている足立啓美さん(日本ポジティブ教育協会代表理事)に、家庭でもできるレジリエンス教育のポイントについて伺いました。

足立啓美(あだち・ひろみ)さん
一般社団法人日本ポジティブ教育協会代表理事、公認心理士、レジリエンスジャパン推進協議会WG委員、認定ポジティブ心理学コーチ。小学校~高校、適応指導教室などさまざまな教育現場でレジリエンス講座の講師として活躍中。共著書に『子どもの心を強くするすごい声かけ』(主婦の友社)、『きものこころをつよくするえほん』(主婦の友社)、『見つけてのばそう! 自分の「強み」』(小学館)など多数。
自分の心を立て直す力・レジリエンス
――そもそも、レジリエンス教育とは、どういうものでしょうか?
足立啓美(以下、足立) レジリエンスとは、失敗やうまくいかない出来事を乗り越える心の力です。
辛い出来事に直面しても、心を立て直し、立ち直る力は、筋トレのように、トレーニングによって育つことがわかっています。
自分なりに困難や逆境を乗り越えていく力(=レジリエンス)を育てるトレーニングをレジリエンス教育と言います。自分の気持ちとの向き合い方を知るための教育とも言えます。
――昨今、レジリエンス教育に注目が高まっているようですね?
足立 私が行っている全国の小・中・高校での講演会では、校長先生や養護教諭など、子どもたちの心に携わる先生や、子どもの悩みを聞く機会の多い先生からの関心が高いようです。
特に、苦手なことや新しいことには「無理」と言って挑戦しようとしなかったり、あと一歩頑張ってほしいところで諦めてしまったりする姿も見られるようです。
友達同士のいざこざでふさぎ込んでしまったり、逆に感情のままに相手に伝えることでケンカになってしまったり…。友達とのトラブルを上手に乗り越えられない光景もよく見られるようです。
しかし、自分の思い通りにいかないこと、人間関係のぶつかり合いは、生きていれば当然あることです。そこから気持ちを切り替えて、良い行動を選んでいくためにはどうしたらいいのだろうと、レジリエンスに興味を持たれる方が多いです。

まずは子どもの気持ちを受け止め、気持ちの言語化をサポートする
――レジリエンス教育では、まず、こどもたちは自分の中の「嫌だな」とか負の感情と向き合わなきゃいけないということですね。
足立 そうなんです。レジリエンスをお伝えする際には、必ず、自分の気持ちとの向き合い方をお伝えしています。不安、イライラ、悲しみといった、いわゆるネガティブな気持ちをいかに上手に乗り越えていけるかが、非常に大きなカギになります。
――ネガティブな気持ちを乗り超えるときのポイントは?
足立 発達段階に応じたアプローチが大切です。たとえば、幼児期なら、かんしゃくを起して泣いている子に「もう泣きやんで!」と言ったところで、パッと気持ちを切り替えられないですよね。
幼児期のお子さんは、大人が一緒にその気持ちの立て直し方を教えていってあげる必要があると思います。
その段階で一番大切なことは、やはりまず子どもの気持ちに寄り添っていくことです。「嫌な気持ちだったんだね」「悔しかったんだね」という受容的な声かけをして、気持ちを受けとめることです。

――親としては、「もう泣かないで」「そんなの気にしないの」と、つい言っちゃいそうです…。
足立 子どもに前向きな気持ちになってほしいからこそですよね。子どもがつらい気持ちでいるのを見るのは、親にとってもつらいことです。だから、親御さんはそう言うのだと思います。
一方、子どもの立場に立ってみたら、気持ちはそんな簡単には気持ちは切り替えられません。気持ちを切り替えられる力を育てるためにはステップがあります。
まず「ネガティブな気持ちがあってもいいんだよ」「そうなる気持ちって、当然だよね」「そっか、今、そういう気持ちなんだね」と周りの大人がしっかり受け止めてあげる段階が、とても大事な最初のステップになります。
――まず、ネガティブな気持ちを受けとめることが大切なのですね。
足立 自分のどんな気持ちも大事で、受け止めてもらえると感じられた子どもたちは、実は、立ち直りが早いのです。逆に、「早く立ち直りなさい」「早く気持ちを切り替えなさい」と言われてしまうと、気持ちを隠してしまい、うまく気持ちが消化できないのです。
――小学生の場合はどうでしょうか?
足立 幼児期は、大人の働きかけによって気持ちを調整していくことが多いかと思いますが、学童期に入ったら、自分で気持ちを調整できる力を育てることを意識してあげたいですね。
そんなときにおすすめなのが、子どもの気持ちを言葉にしてあげることです。「なんだかモヤモヤする」という気持ちを、具体的な感情名(悲しい、イライラ、不安になった)などに変換する過程を手伝うのです。
言語化できると、自分の気持ちを整理しやすくなり、気持ちが落ち着きやすくなります。自分の感情を言葉にすることが、嫌な出来事に対するネガティブな感情やストレスを和らげるのに効果的であるという研究もあります。

――大人にとっても、気持ちを整理することは大切ですね。
足立 その通りです。子どもが気持ちを調整するために、落ち着いた気持ちで関わってくれる大人を助けにしていますからね。
また、成長に伴い、複雑な気持ちを感じ取っていくようになりますから、大人もその気持ちを理解できるといいですよね。
――たとえば?
足立 「弟のことは好きだけど、なんかお母さんを独占されたようで嫌な気持ちになった」など、大人と同じですが、葛藤が生まれてきます。そして「弟が好きなのに、嫌な気持ちを持つ自分はダメなんじゃないか」と思ってしまうこともあります。
ここで大人が「人は誰もが相反する気持ちを抱くことがある」と伝えてあげると、「自分はダメじゃない」と思えて安心できます。
子どもの気持ちをうまく切り替えるおすすめの方法
――思った通りに出来ないと「できない」「やりたくない」と、そこで心が折れて取り組んでいたことをやめてしまうお子さんがいると思いますが、そういうお子さんには、気持ちを受け止めた後、どうサポートしたらよいのでしょうか?
足立 お子さんはきっと「やりたいけど、できない!」「うまく出来なくて悔しい」、そんな気持ちを抱えていますよね。ですから、気持ちを受け止めながら、どうしたら本当にその子がやりたいことを出来るのか考えるといいと思います。
――具体的には、どうしたらよいのでしょうか。
足立 「これとこれのどちらのやり方なら出来そう?」と選択肢を与えてあげるとか、「お母さんがここを一緒に手伝ったら、出来そう?」と協力を申し出るとか。
もしくは「出来ないときは、『助けて』って言っていいんだよ」と助けてほしいときの言葉を教えてあげましょう。
――子どもが興奮しすぎて、話もできなくなってしまった場合は?
足立 そんなときは、お子さんが「気持ちが切り替わる行動」をするといいですよね。たとえば、小さなお子さんには殴り書きがおすすめです。
クレヨンなどで紙に「わ~!」と気持ちのままに殴り書きする方法です。表現することで気持ちが落ち着き、少しだけ前向きになると、行動が大きく変わることがあります。
そのほか、ゆっくりと深呼吸したり、 好きな音楽を聴いたりして、気持ちを落ち着かせるという方法もおすすめです。
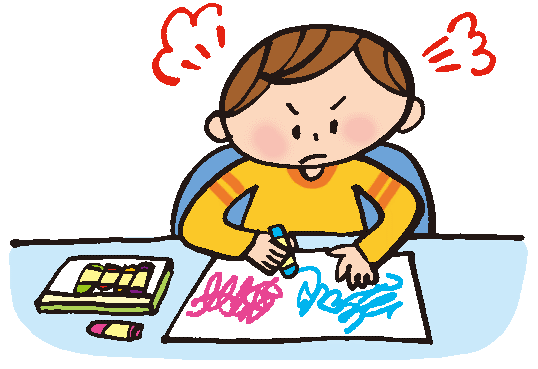
――どれもすぐに取り込むことが出来そうですね。
足立 イライラしているときに殴り書きや音楽を聴くことを提案されても、すぐには出来ないと思うので、ふだんから「今度イライラしたとき、どうする? 殴り書きしたら気持ちが落ち着きそう?」「深呼吸なら、いつでもどこでもできるね」など、親子で気持ちを切り替える方法について話し合っておくことをおすすめします。
――親自身にも役立ちそうですね。
足立 ぜひご自身の気持ちが切り替わる方法を見つけてほしいです。というのも、親御さんは、子どもにとってロールモデルですから、親御さん自身が気持ちを切り替えていく姿を子どもに見せることが大事です。
「お母さん、今イライラしているから、ちょっと深呼吸するね」といった声かけをしながら、健全な形で感情を吐き出す様子を見せてあげたいですね。
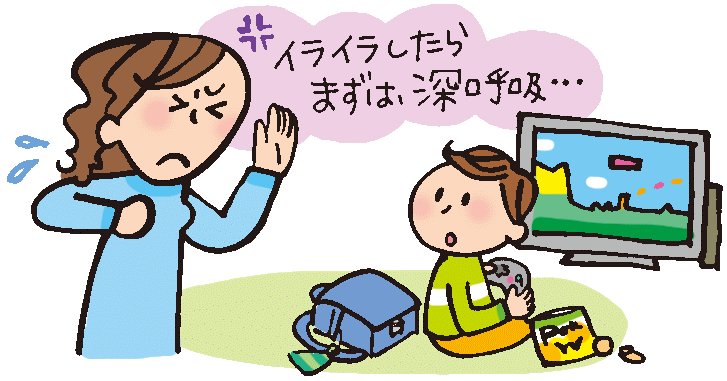
失敗していい、ネガティブな気持ちになってもいい安心感の土台が大切
――気持ちが立ち直ったときに、気をつけるべきことは?
足立 実は、気持ちが立ち直ったときが大事なのです。
たとえば、イヤイヤながらも宿題を終わらせたとしましょう。そういうとき「あのとき、やりたくなくてイライラしてたでしょ。やればできるじゃない!」と言ってしまうことってありませんか?
――あります、あります!
足立 親御さんとしては、褒めているつもりかもしれませんが、子どもの側からすると、宿題が嫌でなかなか取りかかれなかったときの気持ちを思い出してしまいます。困難な状況を何とか乗り切ったのですから、過去のネガティブな状態を蒸し返すことは、やめたほうがいいですね。
――では、どんな対応がよいのでしょうか?
足立 立ち直れたことや気持ちを切り替えたことに注目して、「自分で気持ちを切り替えられたね」と、出来たことに注目してほめてあげましょう。
子どもにとって大切なのは、自分なりにうまく気持ちを切り替えたことを、ちゃんと親御さんが見ていて、わかっていてくれる、ネガティブな気持ちになってもいいという安心感です。

――なぜ、安心感はそれほど重要なのでしょうか。
足立 たとえネガティブな気持ちになったとしても、見守ってもらえているという安心感があれば、「もうちょっと頑張ってみよう」「やってみよう」と思えます。また、失敗や×がつくことを恐れずに挑戦する姿勢にもつながっているからです。
――失敗を恐れずに挑戦する姿勢は、ぜひ子どもに身につけさせたいものです。
足立 最初は、子どもがもつ、イライラやものごとを投げ出したくなったりする気持ちを調整する手助けをしてあげましょう。
成長に伴い、自分で調整できるようにそのスキルを授けていきます。「自分で自分の嫌な気持ちを調整できた!」という経験を積み重ねていくことは、「やればできる」と思える力を育てます。
この経験が自信につながり、レジリエンス力を高めることになります。

親も子も自分の強みを大切にしよう
――子育てを頑張っている親御さんに応援メッセージをお願いします。
足立 子どもたちに「レジリエンスが高い人は誰?」と聞くと、「お母さん」と答えてくれる子どもが多数います。怒っても次の日にはニコニコしている、大変なことがあっても頑張っている…、そんなふうに教えてくれます。
子どもたちは、本当に親の姿をよく見ています。親御さんが自分の気持ちを立て直して元気になっていく様子を見ているうちに、子どものレジリエンス力も自然に育っていくでしょう。
ですから、ぜひ自分自身を大切になさってください。
――親が元気であることは、子どもの幸せにつながっていますね。
足立 その通りです。大人になると、誰かに褒められる機会は少なくなりますが、自分のいいところ、頑張っているところに目を向け、ぜひ自分で自分を褒めてあげてください。
――自分のいいところは、どうやって見つければいいのでしょうか。
足立 自分が困難や逆境をどうやって乗り越えてきたか振り返ってみると、自分のいいところ、ポジティブ心理学でいうところの「強み」が見つけやすいと思います。
たとえば、「忍耐力」という強みがある人は、最後まで頑張り続けて乗り越えます。
「人と関わる力」という強みをもっている人は、周囲の人に「助けて!」とSOSを出し、協力してもらって困難を乗り越えているのです。
――誰でも「強み」をもっているのでしょうか。
足立 アメリカの心理学者が提唱した「ポジティブ心理学」では、「好奇心」「学ぶ意欲」「誠実さ」「美しさを感じる力」…など、人間には24の性格的な強みがあるとされています。
人によってどの「強み」が大きいのかは違いますが、誰もがもっており、周りの人の言葉がけで伸ばすこともできます。

『見つけてのばそう!自分の「強み」』監/日本ポジティブ教育協会、著/足立啓美 ・吾郷智子、小学館
――24の「強み」は、レジリエンス力を高めることにも役立ちそうですね。
足立 レジリエンス力の底力を高めてくれる強みを意識することは、とても有効だと思います。
子どもがもつ強みを知っておけば、「優しさが発揮できたね」「勇気が出せたね」と子どものいいところに注目した声かけもできます。
学校や社会では、できる/できないで評価されることが多いのですが、子どもの内面的な良さを認めてあげるためにも、強みを活用されることをおすすめします。
――ありがとうございました。

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育



