
親野智可等先生 子育て講演会2部 令和7年3月~動画&レポート
目次
全家研ポピー×ママノユメ教育部共催 子育て講演会
全家研ポピーと全国各地のママコミュニティをつなぐ「ママノユメ」がコラボしての「親野智可等先生講演会」、
令和7年3月28日(金)、大阪駅前第一ビルにて開催された第2回の2部「子育て相談おはなし会」の模様をお届けします。
第1部の「親野智可等先生講演」の模様はこちらでお伝えしています。
●第2部 子育て相談おはなし会
第2部の子育てお悩みおはなし会では、親野智可等先生と、
ポピー教育対話主事の太田由枝先生、村田稔子先生が、
参加者から寄せられた様々なお悩みにお答えしました。

親野智可等先生のプロフィールやホームページ、SNSご紹介と、ポピフル連載・記事一覧がプロフィールページからご覧いただけます。


太田由枝先生(写真左)、村田稔子先生(右)
共に京都市内の小学校校長をつとめられた経験豊富な先生です。
現在は全家研ポピーの教育対話主事として、ポピー会員への教育相談や情報サイトポピフルでの教育情報記事発信に携われております。
【お悩み1】負けず嫌いで結果にこだわり、ずるをします
運動をみんなでする時、自分が負けたくないのか、ルールを守らず、早くスタートしたり少しズルいことをして、一番になることに執着します。
一番になりたい!負けたくない!気持ちは、男の子にとって良いことでもありますが、できていないことを「できた」と言ったりするので、結果ばかりにこだわって嘘をつくのも治して欲しいところです。
二人だけの時に、子供の気持ちを聞いてから、言い聞かせをするのが良いでしょうか?
~さおりさんより
子育て相談おはなし会 お悩み1への回答 再生時間:約6分16秒
≪村田稔子先生お答えの要約・ポイント≫
★がんばった部分をほめましょう
負けてくやしかったら、「くやしかったね」と共感してあげればいいんです。
ルール違反は困りますが、負けたくないという気持ちは大切ではないですか。
最近ポピーの教育相談で小1のお父さんから受けた相談に、こんな内容がありました。
子どもが100点を取ってきた。とてもうれしかったので花丸をつけていっぱいほめました。
そうしたら、次の時から「今日も100点だったよ!」と100点のテストばかり持ち帰ってくるように。
でもあるとき、お母さんがランドセルの底から100点でないテストを見つけたんです。そして、
「100点を見せてくれなかった。100点以外のテストを見せられない状況をつくっていたのではないか」
とショックを受けられた。
確かに100点をほめられたので、100点以外はほめてもらえないと思ってしまったのかもしれません。
ほめ方が大切なんです。
100点取れたことは確かにすごいんだけれど、100点を取るためにがんばった部分をほめてあげる。
100点は結果、結果にいたるまでの経過を見つけてほめてあげる。
「先生の話をよく聞いていたから、お勉強わかるようになってきたんだね」
「おうちで国語の文をお母さんに聞かせてくれてるもんね」
そういうがんばりを認めてほめて、100点もほめてあげるんです。
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
★共感と助けで、嘘をつく必要がないように
「嘘をつく」ことを気にされているようですが、あまり嘘を追求しない方が良いです。
子どもは大昔から嘘つきで、嘘をつきます。
大人のようにうまくごまかせないのと、問題解決力がないので、自分を守るために嘘をつきます。
私の知っている親御さんはちょっとの嘘も許さず、厳しかった。
そうしたら子どもは嘘をたくさんつく、嘘のうまい子になってしまいました。
子どもの嘘はスルーする。
共感をたくさんしてあげて、困ったときは助けてあげて、
「嘘をつく必要がない」ようにしてあげたほうが良いと思います。
★ゲームで順番、ルールを覚える
順番やルールを守るようにするためには、トランプやボードゲームのような、
ルールがあって順番を待つようなゲームの中で、守れたら、待てたらほめるということで、できるようになっていくと思います。
★子どもの好きなことをやらせてあげる
また、子どもが好きなことをやらせてあげること。
『博士ちゃん』という番組に出てくる子はすきな事に熱中していて、親はそれを応援している。
どの子にもすきな事はあるので、それを応援してやらせてあげる。
子どもは毎日ハッピーで、自信もついてきます。そうすると勝ちにこだわらなくなります。
もちろん、好きなことに飽きて次のことをやりだすこともありますが、
深追いせず、また新しいことを応援してあげましょう。
子どもの応援に徹して、その時々の好きなことをたくさんやらせてあげると良いと思います。
【お悩み2】 保育園で友だちができず、1人で遊んでいます
保育園に生後4ヶ月から通っていて、現在年少です。
「保育園でいつもひとりぼっちやねん。誰も友達おらんねん。1人で遊んでんねん」
と最近、寝る前などに話してくることが増えました。
決して保育園が嫌という訳ではないようですが、先生に聞くと確かに1人でいる事が多いので1人が好きなんだと思っていたとの返事でした。
性格もあると思うので無理をしてみんなの輪に入るように言うつもりはありませんが、寂しい思いをしているのなら何か手助けしてあげたいなとも思ってしまいます。どのような声かけや関わりをしてあげたらいいのでしょうか。
~れんこんさんより
子育て相談おはなし会 お悩み2への回答 再生時間:約5分45秒
≪太田由枝先生お答えの要約・ポイント≫
★先生に気をつけてもらえるよう話しておく
確かに低学年、もう少し上でも、一人遊びのほうが落ちついて好きという子もいたので、
保育園の先生が「1人が好きなんだと思っていた」と言うことも少しわかります。
「心地よい状態ではなかった。おうちでは寂しいようなことを言っていた」
と先生が気づいてくれたことで、今後もっと気にかけてくれたらと思っています。
お母さんが子どもと話されて、それを先生に伝えられたのは良かったですね。
ここは親は介入して良いところです。
「どうなってるんですか!」という方向ではなく、
「本人こういうことを言っていたので、気をつけてみてくださいね」
「何かきっかけがあれば、お友だちとつないでくださいね」
という話を先生にしておくのが良いと思います。
★「一緒に遊ぼう」や「入れて」…、魔法の言葉を教えましょう
子どもには「一緒に遊びたいんだよね」と言葉をかけた後、魔法の言葉を教えてあげましょう。
「一緒に遊ぼう」、もっと簡単な言葉なら「入れて」…
子どもにあったピッタリの言葉を一緒に考えて、
「魔法の言葉だよ」と渡してあげたら良いと思います。
気をつけなければいけないのは、子どもが帰ってきたとき
「今日はどうだった? 誰と遊んだ?」
と根掘り葉掘り聞かないこと。
子どもにとっての負担になります。
話をしてきたときに聞いてあげて、こちらからは「どうだった?」というのは控えましょう。
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
★実際に口に出しやすすくするためのロールプレイを!
魔法の言葉を教えるときは、「ロールプレイ」がおすすめです。
役割演技というのですが、
パパがお友だちの〇〇くん、ママが△△ちゃん、お兄ちゃんが□□くん
というように役割を作って、3人が友だちごっこをして遊ぶ。
そこに子ども本人が来て「ぼくも入れて」というように実際に言葉にして言ってみる。
場合によってはパパの〇〇くんが「今始まっちゃたからダメだよ」と返して、
その時「じゃあ、見ていていい?」という練習をすると、本番でも言えるんです。
入れてもらうのではなく、「〇〇くん、ぼくと一緒に遊ぼう」と
自分から誘う練習もしておくと、実際に口に出しやすくなると思います。
【お悩み3】 YouTube、子どもに見せた方がいい?
「○○作りたい」「サッカーの△△みたい」の時くらいしか、YouTubeを利用しません。
その為か、YouTubeからの悪い影響は軽く済んでいると思います。
ゲームは、1日1時間。休日の日、午前中にゲームをしたいなら、1時間外で体を動かしたらしてよいルールです。時間より⾧く外で遊んで、いい顔をして、家に帰ってきます。
でも「YouTubeの冷めた情報を知らないより、知って成⾧して行く方が、よいのか?」と悩むことがあります。
以前、「今の子は、みんなYouTubeを見るので、口がたって、ひどいことを平気で言うし、教師の言う
ことを聞かない」と担任から言われたことがありました。
陰で文句を言う、人をばかにして、笑いをとることに、嫌悪感を抱いてしまうので、やはり、子どもたちには、あまりYouTubeを見せたくないです。
~まさんより
子育て相談おはなし会 お悩み3への回答 再生時間:約10分14秒
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
★YouTubeで対立するのではなく、仲良く
教師の言うことを聞かないのは、YouTubeのせいではなく、先生の子どもたちとの人間関係の作り方に問題がるのではと思います。
YouTubeと言っても、内容は様々。
子どもや大人のためになるいいものもありますし、ひどい内容のものもあります。
やはり「選んで見る」ということが大切なのではないでしょうか。
そのためには子どもが見たいのを一緒に見てみる。「これ面白かったよ」と推薦してあげる。
YouTubeで対立するのではなく、YouTubeを媒介にして親子仲良くなるようなことが大事だと思います。
★理解を示して! 否定的な叱りは依存症につながるリスクも
ゲームについてもまったく同じことが言えます。
1日1時間というルールがあるようですが、ルールの作り方が非常に重要です。
「ゲームばっかりやっていてはダメ」
と、親が叱ってしまうことが多いですが、子どもにとってゲームはやっていて楽しい幸せな時間です。
また子どもはゲームで目標を設定したり、工夫をしたり、努力をしています。
目標を達成したときは、達成感を得て、自己肯定感があがるわけです。
そのゲームに対して親が何の理解も示さず、一方的に、否定的に叱ってくると、子どもは悲しみ、孤独感を感じます。
この孤独な状態は良くなくて、依存症のリスクが高まります。ゲーム依存症になるリスクも高まるんです。
子どもが一所懸命ゲームをした後や、休憩しているときに、
「楽しそうだったね」「集中してたね」とほめてあげたり、「今、どんなゲームしてるの」と聞いてみたりしましょう。
また、「私にもやらせてよ」と一緒にやってみると、ゲームが難しいことがわかるので、ほめることもできます。
★良い雰囲気を作って、言いたいことを伝えましょう
ゲームで対立するのでなく、ゲームで仲良くなる。良い雰囲気を作っていく。
そんな中で、親の心配事も少しずつ伝えていくことです。
「面白いね。1時間もやったよ。でもやりすぎると心配だな」
「課金トラブルでこういうがあったよ」
YouTubeも同じ。一緒に楽しみながら、「YouTubeでこういうトラブルがあったみたいだよ」と情報提供しましょう。
上から目線で「気をつけなさきゃダメ」と言うのではなく、
一緒に楽しみ、人間同士として付き合う中で、上下関係ではなく横から目線で伝えていく。そのほうが子どもは聞いてくれます。
「ゲームやYouTubeをわかってくれている」と子どもが感じている良い雰囲気の中で、
「ルール作ろう」と持ち掛けると、子どもも「やりすぎ、見すぎかな」と思ってはいるので、のってくる可能性は高まります。
★共感的で民主的な対話でのルール作りを
ルールを作るとき大事なのが、共感的で民主的な対話をすることです。
「1日1時間だよ、わかった」と押しつけてしまうのは、民主的ではなく独裁的です。
子どもの話を聞く。「1日4時間やりたい」と言うかもしれない。
門前払いするのではなく、
「わかるよ、面白いもんね。でも4時間は長すぎない? 2時間にしない」
「2時間は短いよ。△△くんのうちは3時間だよ」
「じゃあ、2時間半にしよう。その代わり、勉強してからにしようね」
歩み寄れるところは歩み寄って、ある程度妥協しないと民主的対話はできません。
妥協しつつも言うべきことは言って、お互いの着地点をみつける。外交交渉のようなものです。
そうやって作ったルールはホワイトボードに書く。
運用し始めてうまく行かないときは、また対話をして書き換える。
守ってくれる確率が高まります。「自分が作ったルール」だという意識が大事です。
★民主的な対話でのこれからの課題、問題を解決しやすく!
民主的対話を行うと、
「お父さん、お母さんはぼくの話を聞いてくれる。わかってくれる。一緒に考えて問題解決してくれる」
と、子どもの親への信頼感が上がります。これが子どもにとっても、親にとっても大事。
なぜなら、これから親子の前にはいろいろな課題、問題が、時には突然やってきます。
「学校行きたくない」「いじめられてる」「部活辞めたい」「この人と結婚したい」「仕事辞めたい」…、
民主的対話で信頼感ができていれば、子どもは早い段階で親に言うことができ、早く一緒に解決に乗り
出すことができます。
これは良くあるのですが、LINEのような閉じられた空間でいじめがあった場合、
子どもだけでは解決は難しく、大人が積極的に介入しなければ解決できない。
早めに子どもから話をしてもらったほうが良いのですが、
「親だけには言いたくない」という関係だと問題が大きくなってから発覚し、苦しいことになります。
ゲームやYouTubeの問題は現代的で難しいテーマです。
時間はかかりますが丁寧に民主的対話をすることが、後々も含めてとても大事です。
【お悩み4】 家族平等に愛情を注ぎたい。ハッピーに過ごすには?
「子ども3人に、平等に愛情を注ぎたい!」んですけど、
旦那さまに注いでいたら我が家の平穏保たれ、安泰。私の平穏も保たれていると思ってます。
でもそれは、私がやりたい放題できているからと、思うのですが。
夫とこども、家庭を楽しく感じてハッピーに過ごせるには、どんな心意気でいればいいですか。
~やすまりさんより
子育て相談おはなし会 お悩み4への回答 再生時間:約3分59秒
≪太田由枝先生お答えの要約・ポイント≫
★親が仲良いことは、子どもにとって何より幸せなこと
「ハッピーじゃん! 旦那さんを大事にして、自分も好きにやれているんだ」
「ただ、3人のお子さんをもっとしっかり見てあげたいと願っておられるんだ」ということがわかりました。
子どもより旦那さんに手をかけて、うまく家庭がまわるなら、それで良いのではないでしょうか。
放課後教室に残った子どもから、家のことを聞くことがありましたが、
子どもがしんどいとか、嫌だなと思うのは両親のいさかいです。
パパとママが仲良くするのは、自分のことを大事にしてくれること以上に、子どもにとって幸せなこ
とです。
★子どもによって「いつ、何を求めているか」は違う。求められたときに
3人の子を平等にしたいということですが、お金と時間を均等に与えることが平等ではないと思います。
その子が欲しがっているときに、早く集中すればよいのです。
昔、植物が好きな教頭先生からこんことを言われました。
「植物は子どもと同じ。水をどんどん吸うものもあれば、やりすぎると根腐れしてしまうものもある。
ひとつずつ違う。子どももそう」
きょうだい3人いても「いつ、何を求めているか」は違うと思います。
求められたときには、パパを放っておいたり、パパとタッグを組んだりして応えてあげる、
そんな気持ちでいましょう。
「5人そろってハッピーに過ごすことがママの願い!」と宣言して、そうした心持ちで過ごしてほしいと思います。
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
パパとママが仲良くしていれば、それを見て子どもがハッピーになって幸福度合があがります。
とても良いと思います。
【お悩み5】 もっと自立した親子関係に。無気力な子にどう関わる?
小学校の教師であり、3児の母です。
最近、子どもの機嫌に振り回されている親御さんが多くなったように感じます。
子どもの機嫌を損なわないように関わり関係を保っているような保護者さんを見ると、もっと向き合って欲しいと思います。集団に入りづらいお子さんなら、多様性を学びながら少しずつ成⾧して欲しいのですが、子どもが嫌がるから、と学校を休ませます。低学年の不登校が増えています。
また、学校のことやお子さんのことを全て把握したい保護者さんが増えていて、もっと自立した親子関係で小学校に入学してきてほしいと思います。
無気力無関心、ゲームとYouTubeの話しかできない子どもに出会うと悲しくなります。
そんな児童にはどう関わればいいのでしょうか。
~かずちゃんさんより
子育て相談おはなし会 お悩み5への回答 再生時間:約4分28秒
≪村田稔子先生お答えの要約・ポイント≫
★子どもが安全、安心に生きていくための関わりを
確かに最近は友だち関係のような親子関係を求める親御さんもいらっしゃると思います。
ただ、伝えなければならないことは、伝えていかなければならない。
与えっぱなしではいけない。
例えば、「スマホを持ちたい」と言い出したとき、スマホを与えてあげるのが親の仕事ではないでしょう。
自転車の場合、自転車を用意して「はい、乗りなさい」とは言いません。
なぜなら、危険がいっぱいですから。
後ろをもって乗れるようになるまで様子を見る。交通ルールを教える。
一人で乗れるようになるまでたくさん親が関わっていますが、これが大切です。
スマホやYouTubeだけではなく、子どもが新しいことをするとき、
「はい、どうぞ」と与えてしまうのではなく、
「子どもが安全に安心して生きていくために、どう関わっていけばいけないか」を考えて、
声がけを工夫していただきたいと考えます。
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
★子どもの好きなことを、いろいろお試しして見つける
子どもの頭を占めているのがゲームとYouTubeという現実はあり、
他に楽しみがないと子どもたちがこうなってしまうと思います。
やはり「ゲームとYouTubeしかやらない」と悩んでいた親御さんが、
私の講演を聞いて「いろいろお試しでやってみよう」と決意。
あやとりの本を買ってきて一緒にやったり、実験キットを一緒にやったり、
化石発掘体験やメダカの飼育など、いろいろ試してやってみた結果、
プラモデルとプラレールだったと思いますが、趣味が2つ見つかりました。
そして、その2つをする時間が増えたことで、ゲームとYouTubeをする時間が減った。
共感的、民主的ルールを作るのと同時に、子どもが興味を持ちそうなことをする。
いろいろと子どもが興味を持ちそうなことをお試しすることをおススメします。
●講演会、おはなし会を終えて 先生からのメッセージ

太田由枝先生
会場からの生のご質問に答えるという時間がもっとあったらよかったのですが、
事前にいただいた相談への回答だけになり申しわけございません。
私たちは、いつも(ポピー会員さまの)教育相談にお答えしております。
親野先生ともども、お見知りおきください。
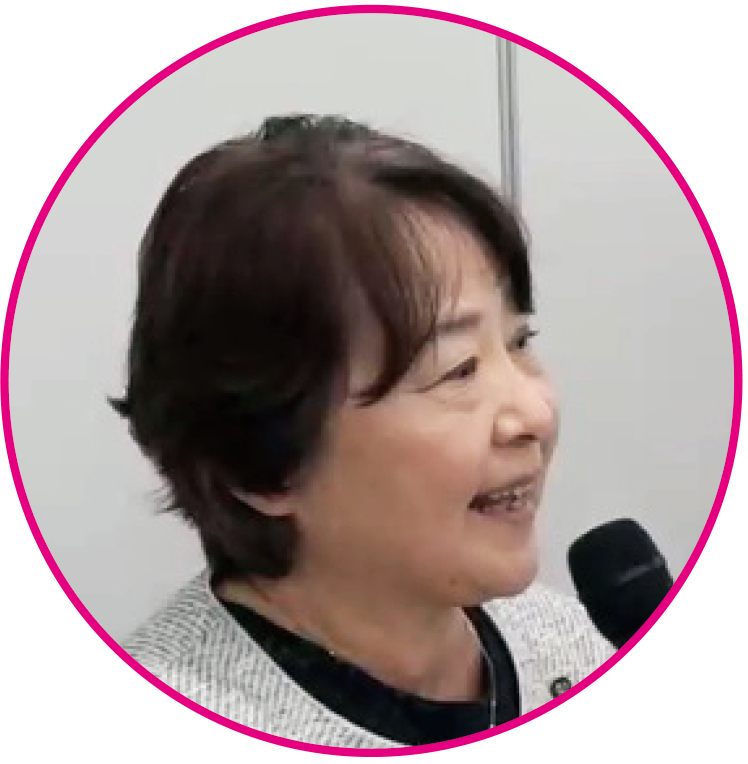
村田稔子先生
親野先生の講演のときから、熱心にメモを取っておられるみなさんの姿を見て、「すごいなぁ」と思っていました。
今日はこの後きっと、お子さんと一緒に1日笑顔で過ごされると思います。
明日はどうでしょう? この先どうなるかはわからないかもしれませんが、
今日の話を頭の隅においておけば、思い出してできることがあるわけです。
「ふっと思い出して、やってみてください」とお願いしたいと思います。

親野智可等先生
しつけや勉強を最優先しないで、とにかく親子関係を大事にする。
親子関係を良くすれば、自己肯定感が上がって、他者信頼感も育つ。
この2つさえあれば、人生全部大丈夫です。
親子で明るく楽しく生きてください。
立派な親にならないで良いので、幸せな親として、子どもと人間同士お付き合いする。「今日もこの子と1日楽しく、幸せに過ごそう」、その延長線上に「幸せな将来」があります。
とにかく子育てを楽しんでください。
▼関連ページ、サイトのご案内
第1部「親野智可等先生講演会」の模様はこちらでお伝えしています。
令和6年6月に開催された、第1回講演会「子どもの学力と人間力を高める「親の5つの習慣」」の模様をこちらでご紹介しています!
令和7年7月に開催された、第3回講演会「一生役立つ力を〝気楽〟に〝楽しく〟育てる方法」の模様をこちらでご紹介しています!
親野智可等先生のプロフィールやホームページ、SNSご紹介と、ポピフル連載・記事一覧がプロフィールページからご覧いただけます。
ポピー教育対話主事の先生が、様々な子育てのお悩みにお答えしている「子育てナビ「あるある」相談室」は、こちらからご覧いただけます。
この講演会は、全国のママをつなぐネットワーク、ママノユメと共同開催いたしました。
ママノユメホームページ、Instagramでも、講演会の模様をレポートしています!

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育


