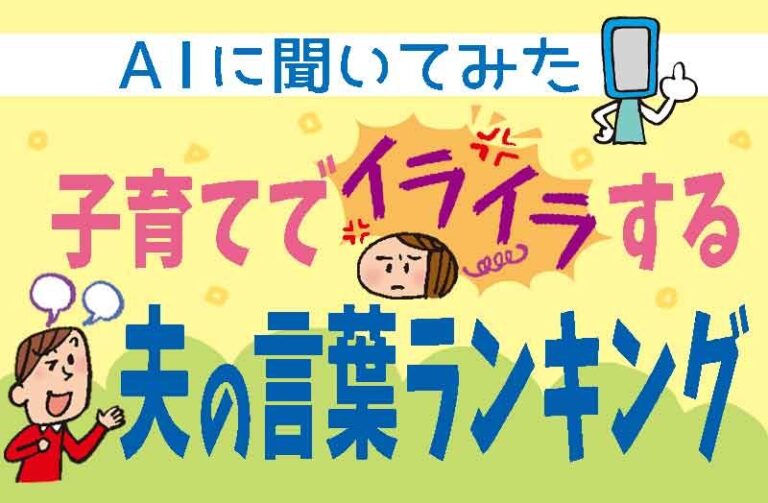親野智可等先生 子育て講演会2部 令和7年7月15日~動画&レポート
目次
全家研ポピー×ママノユメ福岡、ママノユメ九州女子部×特定非営利活動法人Wing-Wing共催 子育て講演会
全家研ポピーと全国各地のママコミュニティをつなぐ「ママノユメ」がコラボしての「親野智可等先生講演会」、
令和7年7月15日(火)、福岡クローバープラザにて開催された第3回の2部「子育て相談おはなし会」の模様をお届けします。
第1部の「親野智可等先生講演」の模様はこちらでお伝えしています。
●第2部 子育て相談おはなし会
第2部の子育てお悩みおはなし会では、親野智可等先生と、
特定非営利活動法人Wing-Wing理事の中山淳子さん、ポピー教育対話主事の村田稔子先生が、
参加者から寄せられた様々なお悩みにお答えしました。

親野智可等先生のプロフィールやホームページ、SNSご紹介と、ポピフル連載・記事一覧がプロフィールページからご覧いただけます。


中山淳子さん(写真左)
種教育機関、幼稚園、保育園などのコンサルティングや、ママ向け商品、施設のアドバイザーとして活動中。子育てにまつわる情報をメールマガジンやフリーペーパー、講演活動を通して発信、テレビ西日本「ももち浜ストア」に水曜日コメンテーターとして出演しています。
著書に『超ママ力 女性が輝く子育ての魔法』(発行:リボンシップ 発売:星雲社)があります。
村田稔子先生(右)
京都市内の小学校校長をつとめられた経験豊富な先生です。
現在は全家研ポピーの教育対話主事として、ポピー会員への教育相談や情報サイトポピフルでの教育情報記事発信に携われております。
【お悩み1】思春期真っ只中の息子、姉が話しかけても返事をしません。
高3の娘と、高1の息子がいます。
息子は、思春期真っ只中と言うこともあるのでしょうが、ここ2年くらい、姉が話しかけてもろくに返事をしません。
娘は来春には東京の学校に通うため、家族一緒に暮らせるのもあと少し、たくさん話して欲しいのにと思います。
もともと口数の少ない息子ですが、姉の事をどう思っているのか、聞きづらいです。
子育て相談おはなし会 お悩み1への回答 再生時間:5分57秒
≪中山淳子さんお答えの要約・ポイント≫
★今はこんな時期だと見守ってあげましょう
幼稚園、保育園、小学校のときも、理解不能と思われることがあるかもしれませんが、高校生になっても同じようなことが起こります。
いわゆるツンデレで、外では無視して、家に帰るとお母さんに甘えたりします。
男子は性、異性を意識し、興味があっても親の前ではかっこつけたり、好きな子の前では意地悪をしたりする時期です。
きょうだい、身近だからこそ恥ずかしい、照れくさいという気持も出てくる時で、子ども扱いされるのもプライド的に嫌だと感じているのではないでしょうか。
息子さんの様子をただ受け止め、今はこんな時期だと見守ってあげるだけでいいと思います。
お姉さんに対しての気持ちは持っているけれど、それを表すのが照れくさいだけで、きっと後になって笑い話になる時がきます。
この男の子の様子は、はしかのようなものであり、一人前の人間になる過程です。
家庭が安心安全な場だからこそ、甘えて感情を出さなかったり、言葉をかけなかったりしているのだと思います。
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
★写真を利用しましょう
家族写真やきょうだいの写真など、スマホの中にある写真をプリントアウトして、玄関やリビングなど目につく場所に飾ることをお勧めします。
こうした写真を見ることで、家族との楽しい思い出が蘇り、自分が愛されているという実感が得られます。また、自分も家族を大切に思う気持ちが芽生えます。
これを「ほめ写」と呼んでいて、脳科学や発達心理学のエビデンスもあります。
【お悩み2】 小学3年生、未だに学校に行く時途中まで送っています。
小学3年生ですが、未だに学校に行く時、途中まで送っています。
トイレも「ついてきて」と言うので、ついて行っています。
夫は、「他の子は一人で学校に行っているのに行けないのは、甘やかしている証拠。他の子と同じくらいに早くならないと!自立させなきゃ!母親依存!」と言います。
子どもは、行き渋り(今学期は2回ありました)があったりするので、ついて行くことで、安心して学校に行けるのなら、と思い送っていますが、これは甘やかしなのでしょうか。
子育て相談おはなし会 お悩み2への回答 再生時間:3分00秒
≪村田稔子先生お答えの要約・ポイント≫
★迷わずついていきましょう
甘やかしであるとは思いません。子どもが一緒に行ってほしいという願いは明らかにSOSです。それを受け止めず、周りの子と比べられるのは子どもにとってつらいことです。
子どもが「自分で行く、今日は大丈夫」と言えるようになるまで、お母さんが迷わずついていってあげればよいでしょう。
迷うと、その迷いで子どもは余計に不安になってしまいます。「もう一緒に行けなくなるかもしれない。僕はどうしてみんなのように一人で行けないだろう?」と自己肯定感は低くなってしまいます。
「どこまででも一緒に行くよ」という安心感を持たせてあげることが、一番大切ではないでしょうか。
早く自立してほしいという願いも理解できます。そのためには、「今日はどこまで行けるかな」「どこまで一緒がいいかな」というように、少しずつ距離を縮めていく具体的な方法が大切です。
「どうして一人で行けないの!」ではなく、「どうしていけないのだろう?」と子どもの気持ちに寄り添い、理解しようとする姿勢が重要です。
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
★自立のペースも子どもにより様々
一緒に行ってあげてOKです。その時、楽しく、不安を感じさせないことは、本当に大事です。
自立のペースも子どもにより様々です。
「When a fruit is ripe, it falls.(熟した果実は自然に落ちる)」ということわざがあります。十分甘えてOKになれば、脱却します。
【お悩み3】 多い宿題に頑張って取り組んでいますが、毎日機嫌が悪くなり暴れ出します。
小学3年生の母です。学校から出される宿題の量が多く、帰ってきてすぐ頑張って取り組んでいますが、毎日寝るまでかかってしまいます。
本人も最初はやる気いっぱい頑張っていますが、毎日機嫌が悪くなり暴れ出す次第です。
頑張っているのは認めて声かけていますが、さすがに毎日暴れられるとめいってしまいます。どんな声かけがいいでしょうか。
子育て相談おはなし会 お悩み3への回答 再生時間:5分16秒
我が家(中山家)の話
私の子どもにも「宿題をしたくない」という時がありました。眠いから、疲れているから、見たいテレビがあるからなど、したくないには理由があります。
それでも宿題をしないと先生に叱られてしまうということを考えてしまい、どうしようとパニックになって、私に当たってきたという経験もあります。
私に当たってこられたのは、私を許しているから、私にだったら甘えられるからだったと思います。
子どもは学校では優等生だったので、「宿題はちゃんと持っていかないと」となって、私に当たってきたのだろう感じていました。なので「いいよ、もうできなかったらできなくて、お母さんが先生に言ってあげるから」といった声かけをしていました。
すると子どもは「お母さんは僕の味方なんだ。自分でできる範囲のことをやろう」と思ったようです。
また学校の個人面談では、先生に「家の中ではこうした状況です」ということをそのまま伝えました。
その時の先生は若い先生で、「たくさん宿題出して勉強を遅れさせないようにしなければ」とがんばっていたようですが、家での状況を感情的にならずそのまま伝えたことで、宿題の出る量も少し落ち着いたという経験があります。
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
★「宿題が多すぎる」の状況を変えるには、大人の交渉を!
この場合、子どもや親が悪いわけではなく、宿題の量が多すぎることが問題です。子どもの自己管理力や集中力、学力には個人差が大きいのに、宿題は一律に出されます。
学力が高い子は短時間で終わる宿題でも、そうでない子は何時間もかかり、親子で苦しい時間を過ごすことになります。これでは子どものためになりません。
先生は学力を上げたい、学習習慣をつけたいという意図で宿題を出しますが、状況を正確に把握していないため、どれくらい子どもたちが苦しんでいるかが分かりません。その結果、子どもたちは勉強嫌いになり、自己肯定感が下がることになります。
状況を変えるには大人の交渉が重要で、まずは良い雰囲気を作ることが大切です。例えば、いきなり問題を持ち出すのではなく、アイスブレイクとして先生を褒めることから始めます。
「先生のことがうちの子大好きです」とか、「いつも先生のものまねをしています」といった具体的な例を挙げると良いでしょう。
先生に感謝の意を伝えた後で、悩み相談という形で問題を持ち出すと、先生も配慮してくれるようになります。
【お悩み4】 丸暗記するのが苦手で、特に漢字が苦手
9歳の子ども(男の子)は、丸暗記するのが苦手のようで、特に漢字が苦手です。
スクールカウンセラーの先生に相談したところ、おそらく子どもにとって漢字を覚えるのは、私達がアラビア語を覚えるようなもの。と言われました。
漢字は毎日1個覚えをしたり、九九も毎日2つだけ言ったりしていますが、何か良い方法はないでしょうか。
子育て相談おはなし会 お悩み4への回答 再生時間:3分32秒
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
★アウトプットをしたり、いろいろな覚え方を試してみたりしましょう
暗記が苦手な子は一定数います。学習障害の一種かもしれません。知能に問題はないものの、暗記が苦手な子どもです。国立大学理系を卒業し、数学が得意ですが、九九の暗記が苦手な知り合いがいます。
専門の医師に診てもらうことが子どものためにも、親のためにも役立つと思います。暗記が苦手な子は、知的能力が低いわけではなく、むしろクリエイティブな能力や論理的思考力が高いこともあります。専門家に見てもらい、長所を伸ばすようするのが良いと思います。
声に出したり、書いたり、五感を使ってアウトプットをしながら覚えると良いでしょう。また、見て覚えるのが得意な視覚優位な子と、聞いて覚えるのが得意な聴覚優位の子がいるため、いろいろな方法を試してみるとよいでしょう。
学校の先生に対しても、こうした情報を提供し、大人の交渉を行うことが大切です。先生は忙しく、最新の知見を学ぶ機会が少ないため、発達障害や学習障害についての情報提供が必要です。授業研究に特化しているため、最新の知見を学ぶ機会が少ないのです。ですから、情報提供を兼ねて大人の交渉を行うことが大切です。
【お悩み5】したい事には集中して取り組みますが、したくないことは絶対にしません。
6歳年長の男の子です。
「皆で家族の絵を描こう!」というテーマでお絵描きをするところで、
息子は、カブトムシを何匹も上手に描いて帰ってきました。
したい事には集中して取り組むことはできますが、
したくないことは、絶対にしない!と意思が強くさせるまでに時間がかかります。
小学校入学目前で、したくない事もしなければならなくなる状況に、小学校生活が楽しめるのか心配しています。
子育て相談おはなし会 お悩み5への回答 再生時間:約2分38秒
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
★これが普通、後伸びを期待しましょう
程度の差はあっても、だいたいこれが普通だと思います。
脳には2種類、晩熟型と早熟型があります。男子の8割は晩熟型で、女子の8割は早熟型です。晩熟型の特徴としては、自己管理の目覚めが遅いことがあります。
また晩熟型は、やりたいことしかやらないし、自分の興味を最優先します。話を全く聞いていないし、理解も遅い。言語表現力、読解能力、時間の観念も低く、だらしない。片付けもできません。
男子にはよくあることですが、能力がないわけではなく、目覚めるのが遅いだけです。だんだん追いついて、後伸びしていきます。
この子も「家族の絵話」という部分を聞いていなかったのではないかと思います。自分が大好きなカブトムシを上手に描いて、「どうだ?」といった感じです。
この場合、それをたくさん褒めてあげてください。ここで叱ってもしょうがないし、叱る必要もありません。
心配なら、大人の交渉術で先生に言っておくといいと思いますが、意外と学校に行ったら困らなかったということもあります。
ITの天才たちや、起業したすごい人たちの子どもの頃はこんなタイプが多いです。自分が好きなことにのめり込んで、他のことには関心がない。こういう子は後伸びするタイプですので、後伸びを期待してください。
【お悩み6】食べるのに時間がかかり、言わないとご飯が進みません
6才の女の子ですが、食べるのに時間がかかり、
毎日「口動かして食べて」と言わないとご飯が進みません。
子育て相談おはなし会 お悩み6への回答 再生時間:約4分28秒
※前半音声が音割れしており、聞きにくい部分があります。
≪村田稔子先生お答えの要約・ポイント≫
★プレッシャーをかけず、食事を楽しいものに!
「食べなさい」と言われたり、親の「食べてほしい」の気持ちを感じたりすることは、子どもにとっての大きなプレッシャーになります。
具体的な対策としては、子どもと一緒に食事の量を決めること。
学校の給食は食べる時間が決められているので、そうしたことへの対策なら、時計を置いて、「ここまでで食べられるといいね」「長い針がここまでにどこまで食べられるかな」と言った声がけをしてみましょう。
食事を楽しいものと感じさせるために、親が一緒に食べて、楽しそうに食べる姿を見せることも大切です。
一緒に料理を作ることも良い方法です。自分で作ったものなら、食べる意欲も高まります。
給食が苦手な子どもの話
小1の担任をしたとき、給食が苦手な子どもがいて、給食を少なめに盛りつけしていたけれど、「もっと減らしてほしい」と言ってきました。
「食べられるくらいに減らしてごらん」と言っても遠慮してあまり減らさないので、こちらで思いきり減らして「これだけ食べられる?」と伝えました。
「これだけでいいの?」と聞いてきたので、「足りなかったらおかわりすればいいよ」と返したら、すごく元気にペロッと食べて「おかわりしてもいい」となりました。
こうした「できる」を経験させてあげるのも大切です。
自分の子どもに離乳食を食べさせるのに困ったとき、松田道雄先生の「育児の百科」という本を読みましたが、そこにこんなことが書かれていました。
「2ヶ月や3ヶ月早く、ジャガイモやほうれん草を食べることは、赤ちゃんの一生にとって何の意味もない。ご心配になっておられることは、長い人生から見るほんの小さなエピソードでいずれ忘れてしまうでしょう」
こうしなければならない、これを食べさせなければならないという親のプレッシャーを取ることで、子どもも楽に食べられるようになります。
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
★無理強いはNG!を先生に伝えておく
生まれつきのペース、食事量があります。
研究によると、同じ年齢で、同じ体重で、同じ運動量でも、食べる量は違ってくると、基礎代謝量が違ってくるので、食べる量も個人差が大きいのです。
無理して急かさなくてもよく、学校に行った時に心配になら、例えば以下のように先生に伝えることが大事です。
「うちの子は食べるのが少なく、食べるのが遅い。園の時に無理に食べさせたり、急かしたりすると吐いてしまった。うちでもいろいろやったが、なかなか治らず、無理すると吐きます」
先ず、無理強いはNGであることを言っておく。
そして「うちでも努力しています、わかっています」と言われると、先生はちょっと安心し、「それではしょうがないな」となります。
【お悩み7】転校して学校に行きしぶりだし、弟たちにあたっています
三兄弟の母です。転校して9ヶ月になります。
小学5年生の長男が新年度から行き渋りはじめ保健室にいる時間が長くなっています。今までは面白い性格で外交的なところがありましたが話を聞いて行くとお年頃なのか教室ではずっと恥ずかしい気持ちでいて学校生活を楽しむことができていないようです。その反動で帰ると弟たちに当たり散らかしてケンカの末壁に穴が空きました(涙)。
自分の殻を破ればこの悩みも解消されるのではと思っているのですが、私ができることはなんなのか悩んでいます。そして、学校側でもできることがあるのかご教示いただけたらと思います。
子育て相談おはなし会 お悩み7への回答 再生時間:4分25秒
※音声が音割れしており、聞きにくい部分があります。
≪親野智可等先生お答えの要約・ポイント≫
★無理して学校に行かせる必要はなく、好きなことをたっぷりやらせて応援を!
親御さんは、どうしても子供に学校に行ってほしいという気持ちが強くなりますが、その気持ちを押し付けるのではなく、まずはお子さんの気持ちを共感的にたっぷり聞くことが大切。
学校に行きたくないという気持ちを理解し、共感することで、お子さんが話しやすい雰囲気が作ってあげることが大事。そうすることで、お子さんの事情などが見えてきます。
不登校は増えており、学校に行くのが当たり前という意識は消した方が良いです。
フリースクールやオンラインスクール、ホームスクーリングなど、学校以外の選択肢も増えており、無理して学校に行かせる必要もありません。
フリースクールやホームスクーリングで充実した生活を送ることで、子供のメンタルも安定し、能力も伸びます。
学校は目的ではなく、子どもを幸せにするための手段の一つ。親は常に子どもの味方であり、子どもが好きなことをたっぷりやらせて応援することが大切です。
ゲームも親子のコミュニケーションの一環として取り入れ、否定せずに楽しむと良い。ゲームを通じて元気が出たり、自信がついたりすることもあります。
ゲームだけでは不安な場合は、プライレールや工作、釣りなど、様々な活動を試すと、子どもの新しい興味を見つけることができます。
。
●講演会、おはなし会を終えて 先生たちからのメッセージ

中山淳子さん
私も今日は一保護者として。 親野先生の話を初めてリアルにお聞きし、非常に学び、たくさんメモもさせてもらいました。私も日常生活を生かして行きたいと思いますし、今日いらっしゃっている方たちの先輩のお母さんとして、皆さんの力になれたらいいなというふうに思っております。

村田稔子先生
私たちもお話させていただいて、嬉しい気持ちでおります。
皆さんにお伝えしたかったのは「ねばならない」と思いすぎないでくださいということなのです。「本当にそれってそうしなければならないですか? 」ということです。
考えてみると、別にいいかと思うこともたくさんあると思います。
「大好きなTシャツを着たままお風呂に入ろうとして、脱がないんですけど、どうしたらいいですか?」という相談を受けた時、「そのままTシャツで入ったら」と答えたら、「えっ」てなりました。
子どもはいろいろな経験を通して、いろんなことを学んでいきます。それを一歩下がって見守っていくっていうことが大切なのかなと思っています。

親野智可等先生
親子関係をひたすら大事にしてください。親子関係を良くすれば、もう全部大丈夫です。本当に親子関係が1から99番目、勉強は百番の後でいいです。よろしくお願いします。
SNSいろいろやっていてに力入れて、スレッズに力を入れていますので、ぜひ
フォローしてください。
▼関連ページ、サイトのご案内
第1部「親野智可等先生講演会」の模様はこちらでお伝えしています。
令和6年6月に開催された、第1回講演会「子どもの学力と人間力を高める「親の5つの習慣」」、
そして令和7年3月の第2回講演会「「自ら動く子ども」に育てる親子関係」」のレポート、アーカイブ動画も公開しています!
親野智可等先生のプロフィールやホームページ、SNSご紹介と、ポピフル連載・記事一覧がプロフィールページからご覧いただけます。
ポピー教育対話主事の先生が、様々な子育てのお悩みにお答えしている「子育てナビ「あるある」相談室」は、こちらからご覧いただけます。
この講演会は、全国のママをつなぐネットワーク、ママノユメ、特定非営利活動法人Wing-Wingと共同開催いたしました。一般社団法人 ガールスカウト福岡県連盟、(株)マザープラス、(株)to planのご協力もいただいております。
ママノユメホームページでも、講演会の模様をレポートしています!

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育