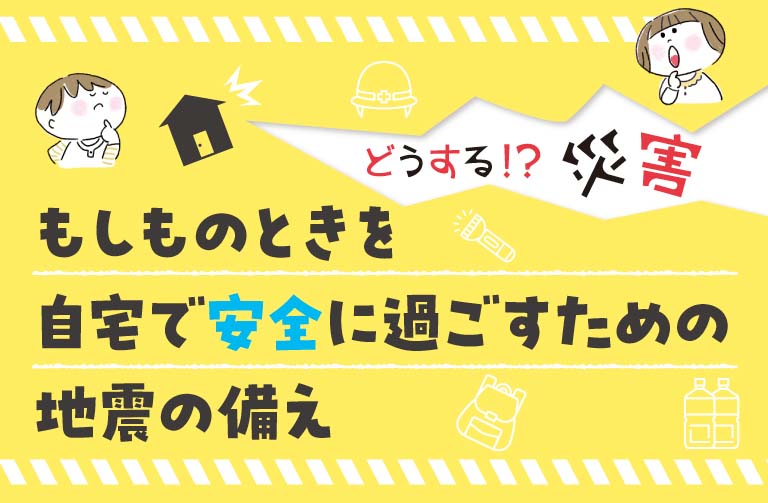
自分でできる地震対策。自宅にセーフティゾーンを作ろう!
どうする!? 災害
小さなお子さんがいるご家庭では、地震のときどうすれば子どもを守れるでしょう。今すぐ始められる対策のヒントをお伝えします。
目次
南海トラフや首都直下型などの大地震が高確率で発生すると言われています。小さなお子さんがいるご家庭では、どのように子どもを守ればいいのでしょうか。阪神大震災での被災経験ののち防災士の資格を取得し、さまざまな震災現場で支援活動を行ってきた乾 栄一郎さんにお話をうかがいました。

乾 栄一郎
NPO東京都防災士会 理事 世田谷区STEAM教育指導員
阪神・淡路大震災での被災経験を、首都直下型地震や南海トラフ地震への備えに
活かしてもらえるようNPO東京都防災士会の広報部長として活動中。
まずはおうちの中に、セーフティゾーンを確保しよう!
地震対策は考えているけれど、子育て中のあわただしい生活の中で何から手をつければいいのか…。そんなお悩みを持つかたも多いのではないでしょうか。そんな場合は、自宅にセーフティゾーンを作ることから始めましょう。
セーフティゾーンとは「何も落ちてこない、何も倒れてこない、安全な空間」のことです。
地震が起きたときにはまず「机の下に隠れること」と習ったかたが多いと思います。ただ、その机に向かって食器棚や冷蔵庫など、いろいろなものが倒れてきたらどうでしょう。机ごとつぶされてしまう可能性もあるのです。
阪神・淡路大震災では、犠牲者の死亡原因の約8割が家具や家屋の倒壊による圧死でした。「何も落ちてこない、何も倒れてこない、安全な空間」であるセーフティゾーンがあれば、震災直後の圧死を免れることができるのです。
♦セーフティゾーンの作り方
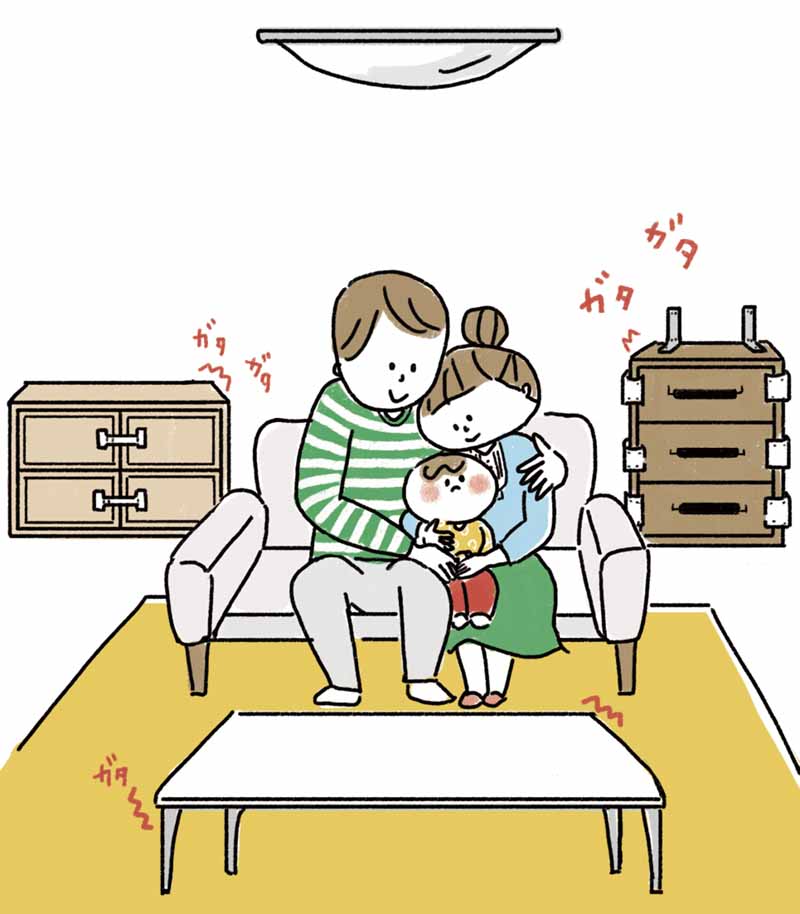
⚫︎セーフティゾーンは、家族4人で1畳程度の広さは確保しましょう。「家族4人が身を丸めた状態で、地震の数分間をやり過ごせる広さ」と考えればいいのです。たとえば食器棚だと高さは200cm程度です。これが倒れてきても安全な場所、つまり、食器棚から2m以上離れた場所は、セーフティゾーンにできるということです。
⚫︎セーフティゾーンを作る際にオススメなのは、比較的荷物が少なく、滞在時間が長いリビングや寝室です。どの部屋にセーフティゾーンを作るか決めたら、その部屋を見渡してみましょう。立ってだけでなく、座ったり、寝転んでみてください。倒れそうなものや落ちてきそうなものはないかなど、地震の際の危険がないか、いろんな目線で探してみるといいでしょう。
災害があっても安全なおうちに! ~地震への備えのチェックポイント~
セーフティゾーンを確保できたら、家の中をより安全にすることを考えましょう。内閣府も提唱していますが、自宅が安全であれば、無理に避難所に行く必要もありません。避難せず、住み慣れた自宅で過ごすことができれば、おうちのかたもお子さんも安心ですね。
上から物が落ちてこないこと、割れたガラスなどでケガをしないこと、夜でも明かりを確保し転倒しないこと、このような観点で、自宅を安全な場所に整えていきましょう。
●家具の固定や配置の工夫を徹底して!
寝室や子ども部屋には、できるだけ家具を置かないようにしましょう。置く場合にはなるべく背の低い家具にして、倒れたときに人が下敷きにならない、また、出入り口をふさがないような場所・向きに設置します。
背の高い家具やタンスや食器棚などは、L字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、転倒防止対策をします。タンスの引き出しや食器棚の扉は、揺れによって簡単に飛び出したり開いたりします。ラッチなどを取り付けて、中身が飛び出さないようにしておきましょう。
●家電製品も固定の対象です!
電子レンジや炊飯器など、家電製品は重量があり、大きな揺れの際に文字通り「飛んでくる」危険があります。専用の固定器具が用意されている場合がありますので、販売店やメーカーに問い合わせてみましょう。設置スペースなどの都合で固定できない場合は、粘着性マットなどで設置台に固定するのも一つの方法です。
●食器棚のガラスには飛散防止フィルムを!
食器棚やサイドボードのガラス面は、家具が倒れなくても中の収納物が飛び出そうとする力で割れる恐れがあります。ガラスや食器の破片が床に飛び散ると、ケガのもとになります。ガラス面は、万が一割れても破片が飛び散らないよう、ガラス飛散防止フィルムを貼りましょう。
窓ガラスも同様ですが、レースのカーテンを常に閉めておくだけでも、ガラスの飛散を抑えることができます。
●食器はプラスチック製など割れにくいものを選ぶ!
食器棚から食器が飛び出したらどうなるかイメージしてみましょう。割れない食器を選ぶ、重量によって収納場所を調整するなど、なるべく危険のない方法を検討しましょう。棚板に滑り止めシートを貼っておくとさらに安心です。
●照明はLEDシーリングライトに変更、停電時でも明かりを確保できる工夫を!
ペンダント式照明は激しく揺れたり落ちたりする危険があるので、シーリングライトに変更しておくと安心です。電球もLEDを選ぶと小さくて軽いためより安全ですし、消費電力が少ないという利点もあります。また、防災対策用に市販されているバッテリー内蔵型の電球やセンサー式足元灯などを備えておけば、就寝中の災害で停電となった場合も安心ですね。
●避難経路を複数確保し、出口が塞がれた時の対応を考える!
寝室や子供部屋からリビングや玄関まで、スムーズに移動できるか確認しましょう。廊下に家具や荷物があると、倒れて逃げられない可能性があります。退避ルートを複数イメージしておくことも大事です。
おうちキャンプであそびの中に防災訓練を取り入れよう

♦非常食を食べる日
定期的に備蓄している非常食を食べる日を作りましょう。カセットコンロとペットボトルの水を持ち、お庭やベランダへ。外で食べると、不便なことや必要なものなどに気づくことができます。またお子さんが食べられるかどうかの確認にもなりますし、賞味期限切れを防ぐこともできますね。
♦電気・ガス・水道を使わない日
半日程度でいいので、できる限り自宅備え付けの電気やガスやインターネットを使わずに生活してみましょう。スマートフォンやゲーム機を手放して、トランプやボードゲームなどの電気を使わないおもちゃで遊ぶのもよい経験になります。携帯トイレの使い方もこのような機会に覚えておくとよいでしょう。
懐中電灯やランタン、ヘッドライトを使ったあそびで暗闇に慣れる
お子さんは特に暗闇に慣れていないため、夜を怖がる可能性が高いです。夜間に停電が起きても慌てたり、怖がったりしないよう、暗がりの中であそんでみましょう。
まずは懐中電灯を用意します。ランタンは転倒等の危険のない電池式や充電式のものを。また、個人用にヘッドライトやネックレス、衣服につけるクリップタイプのLEDライトを用意すると行動範囲が広がります。さまざまな明かりを準備して電気を消せば、おうちが非日常的な空間に早変わり! 暗いお部屋でおもちゃであそんだり、絵本の読み聞かせや影絵あそびなどをして楽しみましょう。おうちの中を探検してみるのもいいですね。夕食を食べたりお風呂に入ったり、普段していることを暗がりの中で行うと、なんでもあそびに変わります。
このようなあそびを通じて「暗くても楽しい!」と感じてもらえたら大成功です。定期的に行えば、懐中電灯などの置き場所をみんなが把握でき、停電時にも慌てず冷静に行動できるようになるでしょう。
まとめ
実際に大きな地震が起きたらどうなるか。被災経験のないかたにとってはイメージすることが難しいかもしれません。防災について学ぶこと、必要なものを揃えることはもちろん重要ですが、普段の生活の中に災害を意識した体験を取り入れていくことで、災害から家族を守れる自信が生まれてくることでしょう。
いざというときの備えとして防災リュックも用意しておくといいですね。
文/那須由枝 イラスト/sayasans 編集協力/東京通信社

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育



