
とけいあそび~時計の読み方「何時かな?」
かんたん べんり 出先でもできる ちょっと知的な親子あそび
幼少期の子どもにとっては「あそびがまなび」です。
楽しく取り組んで好きになることがいちばん!
親子で楽しく、かんたんに取り組めて、まなびが好きになるあそびをご紹介します。
とけいあそび~時計の読み方「何時かな?」
ご家庭にはどんな時計がありますか。時刻を知りたいときには、デジタル時計が便利ですよね。
でもアナログ時計が読めると、便利なことがたくさんあります。針の動きを見て、時間の経過を感じたり、自分の行動に見通しがもてるようになったり。生活リズムを整えることにもつながります。
そんな時計の読み方を、楽しく身につける方法をご紹介します。
1.かんたん時計作り

紙皿を使って、時計作りをしましょう。
おうちの方と一緒に時計作りをすることで、時計に対する興味が膨らみます。
また、お気に入りの色を塗ったり、模様を描いたりすると、より楽しくなりますよ。
時計盤に数字を書き込みながら、時刻の表し方に気づけるといいですね。
準備するもの
- 紙皿
- モール(2色、長針用と短針用)
- ペン
- 紙皿に穴をあける道具(千枚とおし、ハサミなど)
- テープ

作り方
①紙皿の底に中心点を取り、小さな穴をあけます。

② 紙皿を裏返します。
③文字盤となるところに数字を書きます。

④中心にあけた穴に、適当な長さに切ったモールを差し込み、長針と短針を作ります。

⑤モールの端でけがをしないように、裏面をテープでとめておきましょう。

※紙皿の代わりに紙コップの底を使うと、お出かけに持って行きやすい「腕時計」も作れます!

2.手作り時計を使って「何時かな?」あてっこあそび
手作り時計を○時にあわせて「何時かな?」と問題を出しあいっこし、〇時の言い方に慣れましょう。
① 時計の読み方「〇時」
長針がちょうど12を指すとき、短針が指している数字が「何時」を表していることに親しみましょう。



子「これ、何時かな?」
親「短い針が5のところだから、5時でーす」
子「せいかい」

親「おやつの時間、これ何時かな?」
子「3時だよ」
親「すごい!」
② 時計の読み方「〇時半」
長い針が6を指しているとき、時間は「〇時半(30分)」を表すことに親しみます。


でも、短い針は3を超えてるよ?

短い針が次の4に行くまでは、3時というんだよ。

そうか。だから3時半なんだね!
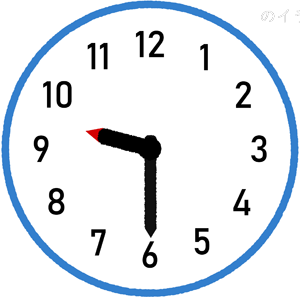
親「じゃあ、これは何時かな?」
子「短い針は10の前だから…9時半だよ」
親「よくわかったね!」
でも、実際はこんなに簡単に理解できるものではありません。
何度も何度も時計を見て、お話ししてくださいね。
③ 時計を合わせよう
実際に、手作り時計の針を「〇時」と「〇時半」に合わせます。

親「この時計を2時に合わせて」
子「簡単だよ。はい、できた」
親「すごいね。じゃあ、2時半はどうなるかな?」
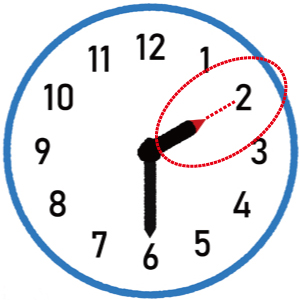
子「半は6のところだから、これでいいのかな」
親「そうだね。長い針は6のところだね。短い針はどうかな」

子「そうか。短い針も動くんだね。どこまで動くのかな」
親「2時半、だから…」
子「そうか。半分だけ動くんだね」
教え込むのではなく、感覚でとらえられるようになるまで、たくさん遊びたいですね。
手作り時計で遊んだ後、針が動く模型の時計を使って遊ぶと、長針や短針の動きをきちんととらえることができますよ。
3.時計を生活に活かそう
例えば…


時計を見ながら、お子さんと約束の時刻を決めましょう。
時計の絵に長針と短針を書き込んで、約束の時刻を家族みんなが見えるところに貼っておきます(見える化)。
守れたらカレンダーに花まるを付けていくなどすると、楽しみながら、生活リズムを整えていく工夫ができますよ。
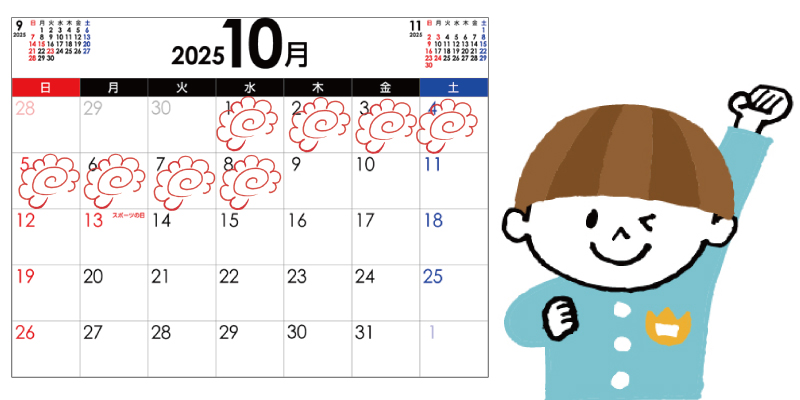
アナログ時計の読み方に慣れるまでは、約束の時刻は、子どもにも読める〇時か〇時半(30分)にしましょう。
子どもにとって時計はわかりづらいもののようです。
「これくらいわかるでしょ」「もう何回も言ってるよ」など、子どもが焦ってしまうような声かけではなく、「一緒にやってみようか」とお子さんと一緒に時計の読み方を楽しんでください。
自分から時計を見たり、針の動きに興味をもったりできるように、時計と楽しく出会わせてあげましょう。
とけいあそびで「時計の読み方」に親しんで…
小学校では1年生の前半に「何時、何時半」の読み方、後半に「何時何分」の読み方を学習します。
焦らず、ゆっくり進めてください。
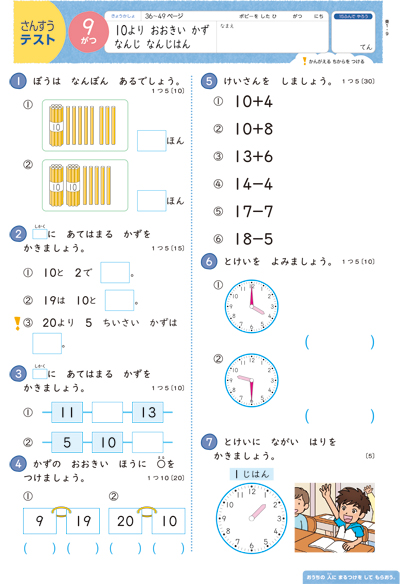
『小学ポピー1年生』算数テストより
時計の学び方のヒントは、こちらでもご紹介しています。

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育



