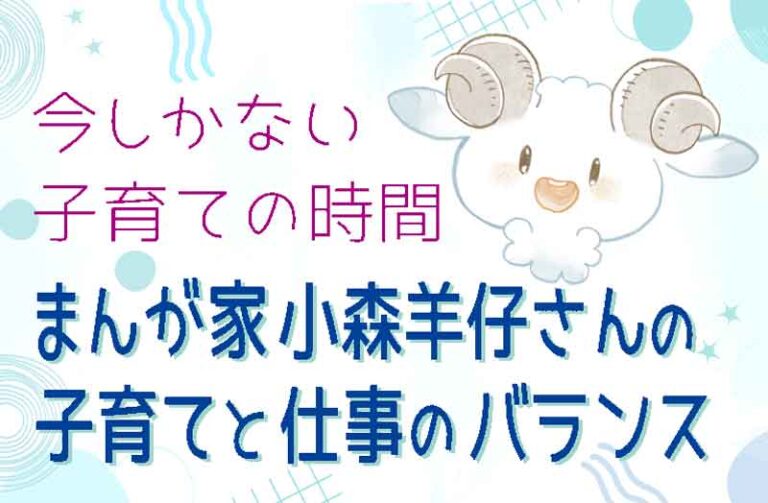ほとんどお手伝いをしない子ども どうする?~お手伝いは子どもになぜ必要? 大切?
先生の子育てインスタライブ
目次
「食事のあと片付けや、掃除、少しは手伝ってほしい…」お手伝いをしない子どもが増えているそうです。
お手伝いはなぜ必要なのか、どう「お手伝い」をする子にするのか、
経験豊富な村田稔子先生とお話し、相談するインスタライブを5月9日(金)に開催しました。
参考になる話がいっぱいのライブアーカイブ動画と、お話のポイントをお届けします!
▶お手伝いは子どもになぜ必要? 大切?
お手伝いはぜ必要? 大切? 再生時間5分18秒
- お手伝いは家事のスキルを覚えるだけではなく、様々なところで子どもの成長に役立っている。
- お手伝いは家族の一員として自覚をしていく大切な経験。
- お手伝いは心と頭を育てるスーパー教材!
- 「お手伝い」という言葉は、主となって家事をやる人がいて、それを補佐する、手伝うということ。
家族全体で分担して家事を行うというイメージにはならない。 - 小学校高学年の家庭科授業でも、「家族の一員として自分でできることをする」「家事を分担する」等ことばがよく使われている。
- 最初は「お手伝い」というところから始まるかもしれないが、将来的には「家事を分担する」「自分ができることをする」という意識を持つことが大切。
- 家事を分担し、いろいろと経験していくことで得る力が自立につながっていく。
▶ 子どもにどのようにお手伝いを経験させる?
どのようにお手伝いを経験させる? 再生時間:5分52秒
- 「行動と快感が結びつけば、やる気は自然と起こる」と、脳科学者・篠原菊紀先生は言っています。
- お手伝いをしてその後快感があれば、お手伝いと快感が結びつけば、自分からやる気になっていく。
- 快感になるものがお菓子のようなご褒美だとしたら、お菓子のためにお手伝いをして、お菓子がないとしないとなってしまう。物ではなく、心に残る快感が大切。
- うんとほめられ、いい気持ちになった。そういった心に残る快感が「またやろう」の気持ちにつながる。
- お菓子をあげるのではなく、「これが終わったら一緒におやつにしようね」でも良いのではないか。
- 「おうちの方が喜んでくれるからする」という子どもは多いので、その快感をどのように与えるかが、大人の工夫のしどころ。ただ「やりなさい」だけではなかなかやる気にはならない。
- 「できそうなこと」を子どもに「やってみる!」とさせていくことが大事。
- 子どもは背伸びをして、難しいことをしたがる。でも、難しいことをして、うまくいかなくて、叱られたり、おうちの方にやり直しをされたりすると、子どもはがっかりしてしまう。
▶子どもが何の家事をするか、どう決める?
子どもが何の家事をするか、どう決める? 再生時間:5分27秒
- 忙しくて「自分がやったほうが早い。やってしまおう」となるのは仕方がない。でも…
- 子どもが将来、「これをしておこう」「これは自分のやること」と思えるようになるためには、小さいころから「これ頼んだよ」と任せるようにしたい。
- 子どもにしてもらうことをどう決めたらよいか?
- その時々で「これ手伝って」としていると、言われなければやらない受け身になってしまう。
- 「毎日の家事の中で、どんな仕事ならできるかな。これをがんばってみる?」と子どもと一緒に相談して決める。
- 子どもはどんな家事があるか、知らないことが多い。
- 園ではお昼ご飯の片付けなどを、子どもがやっていることが多い。
- 園に通っているようなら、「園ではどういったことをしているのか」「園でやっていることならできるのではないか」というように、子どもに任せる家事を考えても良い。
- 子どもに任せる家事を決めて、それを子どもがしなかったとき、「なんでしないの、約束したでしょ」と叱るのはNG。
- 「叱られた」では子どものやる気は育たない。
- 「今日はまだできてないのね。一緒にやろうか」「今からでもやってくれるかな」といった声がけで、子どもによりそうように。
- 頼むと嫌がる。嫌がらずに手伝ってもらうには?
→最初は「一緒にやろうか」の声かけをし、少しずつ自分でできるように。
▶お手伝いでできる心の成長
お手伝いでできる心の成長 再生時間:5分53秒
- 子どもが「お手伝いする」と言ってきたが、忙してやらせられないときどうすればよいか?
→やらせなければならないということがストレスになってしまうと、かえってうまくいかない。 - 親が子どもに感情をぶつけてしまうことがあっても仕方がない。
- 余裕があるときにはできるので無理しないで。
- 段取りがわかってきて、「ここはこれくらいでいいかな」とできるのは力の一つ。
- きちっとしてほしい場合は、毎日やっていることをまずほめて、「もうちょっとこうなったらうれしいな」と伝える。
- お手伝いはいろいろな力を育てる。特に心の成長に大きく影響する。
- ほめてもらう、喜んでもらう良好な親子関係、信頼関係が生まれる。
- 家族としての自覚や、「自分はやったらできるんだ」という自己有用感、自己効力感が育つ。
▶ 家族の一員としての気づきや経験を
家族の一員としての気づきや経験を 再生時間1分50秒
- 小6の家庭科の授業で、「家の仕事にはどんなことがあるか」を子どもに書き出させたところ「洗濯、食事の用意、掃除」くらいしか上げられない子がいれば、たくさん書き出せて、「洗濯、干して、たたんで、片づけて」と仕事が見えている子もいた。
- いろいろな家事を担当しているのは誰かをあげていったところ、母親がやはり多かったが、「当たり前でしょ、お母さんだもの」と反応する子と、「わぁ、お母さんたいへんだ」と反応する子がいた。
- 家族の一員として子どもにできることを伝え、気づかせていかなければいけない。
- 家でも子どもに「こんな仕事がある」ということを発信していくことが大切。
▶ お手伝いで育つ様々な能力
お手伝いで育つ様々な能力 再生時間4分25秒
- お手伝いで育つ能力。お手伝いは心だけでなく、様々な力を育てる。
- お手伝いは、「第2の脳」と呼ばれる指先をたくさん使う。脳に刺激を与え、活性化させる。
- 「手順」を考えていくことができ、「段取り力」が身につく。
- 「洗濯ものの取りこみ」と「お風呂掃除」など、仕事をいくつか担当する場合がある。
天気の様子など状況に応じて行動をとらなければいけない。
どうすればスムーズにできるかも考えなければいけない。 - 子どもの段取りが悪いと、つい「なんでこれを先にやらないの!」という言い方をしてしまうが、どういった言い方が子どもに伝わるか。
- 「どういう考えでそういう順番にしたのか」子どもに聞いてみる。
- その考えを受け止めたうえで、順番を考えるとスムーズに進むということや、「段取りをつけていく方法」を少しずつ伝えていく。
- 「これを先にした方がいいでしょ!」というように言うのではなく、子どもが自分で考えさせることが大切。教えても忘れしまう。自分で気づいたことは行動に移せるので、気づくような声がけを。
▶ まとめ~我が家の話
まとめ~我が家の話 再生時間6分52秒
- 年齢とともに自然とできるようにはならない。
- できそうなことから、少しずつ経験させていくことが大切。
- 一人でできそうでないことは、一緒にやるなど段取りを踏むことを考える。
- 「できたね」「うれしいな」「ありがとう」という気持ちを伝えること。
- それが、何よりも心に残る快感になり、「またやろう」の行動につながる。
我が家の話
学級懇談会で帰りがとても遅くなった日がありました。
家に帰り、食事の準備をしようとすると、当時年中だった娘が「わたし、お手伝いする!」と言ってきたのです。
少しでも早く食事の準備をしたい。普段だったら「今日はいいよ、待っていて」と言っているところですが、その日は懇談会で、保護者の方たちに「お手伝いの大切さ」を話してきたばかりです。
私は手伝ってもらうことにしました。すると娘はよりによって「きゅうりを切りたい」と言ってきたのです。
私は包丁を持つ娘のそばで、はらはら、どきどき、そしてイライラ。ほんの2、3分が、とても長い時間のように思えました。やっと切り終えた時、私は一言「ありがとう」と言って、次の作業を始めようとしました。その時です。娘が私の服の裾をもって、私を見上げ
「お母さん、わたしお母さんの役に立った?」と聞いてきたんです。
私はハッとしました。そして、娘の横でイライラしていた自分がたまらなく情けなくなり、「助かったよ。ありがとう」と抱きしめました。
このことは、大人になった娘も覚えていて、
「お母さん、あの時、本当は困ったんでしょう」と言いました。
私の心にも、娘の心にも残った出来事だったんです。
あの時のことが、理由のすべてではないのでしょうが、娘は、高校生になると兄と自分のお弁当を作ったり、私が宿泊研修に行くときは晩ご飯を作ったりするようになりました。
子どもが「やりたい」と言ったときは寄りそえる限り寄り添ってあげることが大事だと思います。
お手伝いって良いものです。
最新開催情報&ポピー教育相談について
先生の子育てインスタライブを、毎月上旬に開催しております!
最新の開催情報をご確認の上、ぜひ事前アンケートにご協力ください。
インスタライブへのご意見・ご感想
毎月開催している「先生のインスタライブ」へのご意見・ご感想はコチラから!
子育てインスタライブは教職経験豊富なポピー教育対話主事の先生がお届けしています。
ポピーでは、教職経験豊富な対話主事先生が会員からのさまざまな子育て、
家庭学習に関するお悩みにおこたえしています。
ポピー会員のおうちの方へ、お悩みの際はポピー教育相談(無料)をご利用ください。
ポピーが運営する教育情報サイト「ポピフル」では、他にも子どもとの関わり方に関するお悩みへのアドバイスをご紹介しています。合わせてご覧ください。



 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育