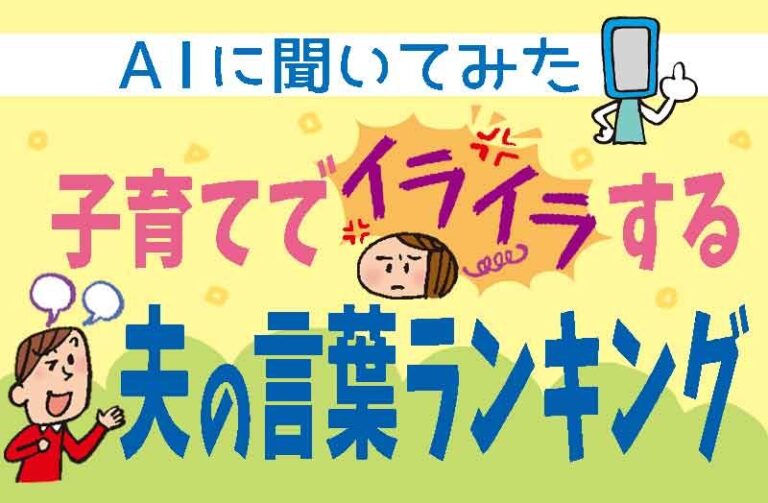親野智可等先生 子育て講演会 令和7年7月15日~動画&レポート
目次
全家研ポピー×ママノユメ福岡、ママノユメ九州女子部×特定非営利活動法人Wing-Wing共催 子育て講演会
全家研ポピーと全国各地のママコミュニティをつなぐ「ママノユメ」がコラボしての「親野智可等先生講演会」、
第3回を令和7年7月15日(火)、福岡クローバープラザにて開催しました!
配信視聴も含め、多くの方にご参加いただきました。
「親野先生のお話はとても面白く、すっと話が入ってきやすかったです!ためになる話が盛りだくさんで、ペンを持つ手が止まらなかったです!」
「やってみよう!と思える実践可能な話がたくさんあったところが参考になりました!」…
2部の「子育て相談おはなし会」も含めた講演会、
一生役立つ力を〝気楽〟に〝楽しく〟育てる方法
「学力」も自然とついてくる「生きる力」をはぐくむには
の全内容をお届けします!
第2部の「子育て相談おはなし会」の模様はこちらでお伝えしています。

親野智可等先生のプロフィールやホームページ、SNSご紹介と、ポピフル連載・記事一覧がプロフィールページからご覧いただけます。
●第1部 一生役立つ力を〝気楽〟に〝楽しく〟育てる方法
「学力」も自然とついてくる「生きる力」をはぐくむには
現在、社会で重視されている「非認知能力」。
意欲や自立心、コミュニケーション力などの、数値で測れない力が人生を豊かにし、
また、学力を伸ばす下地になるとも言われています。
親野智可等先生が育てるコツをアドバイスいたします!
【1】 子どもの長所も短所も「生まれつき」が大きい
親野智可等先生 子どもの長所も短所も「生まれつき」が大きい 再生時間:約8分06秒
≪子どもの長所も短所も「生まれつき」が大きい の要約・ポイント≫
「人生万事塞翁が馬」です。子育て中の皆さんも、困難なことが実は良いことにつながることを覚えておきましょう。
逆に、良いことが悪いことの引き金になることもあります。一喜一憂しすぎないことが大切です。
せっかちな人か、のんびりマイペースな人か、朝型か夜型か、仕事を前倒しで計画的にやる方か、土壇場力に頼る方か、プラス思考かマイナス思考か、片付けが得意か苦手か、これらはすべて「生まれつき」です。
ダニエルディック博士の『「遺伝が9割」そして、親にできること』という本をお勧めします。1章だけでも読むと、人生観や子育て観ががらりと変わります。
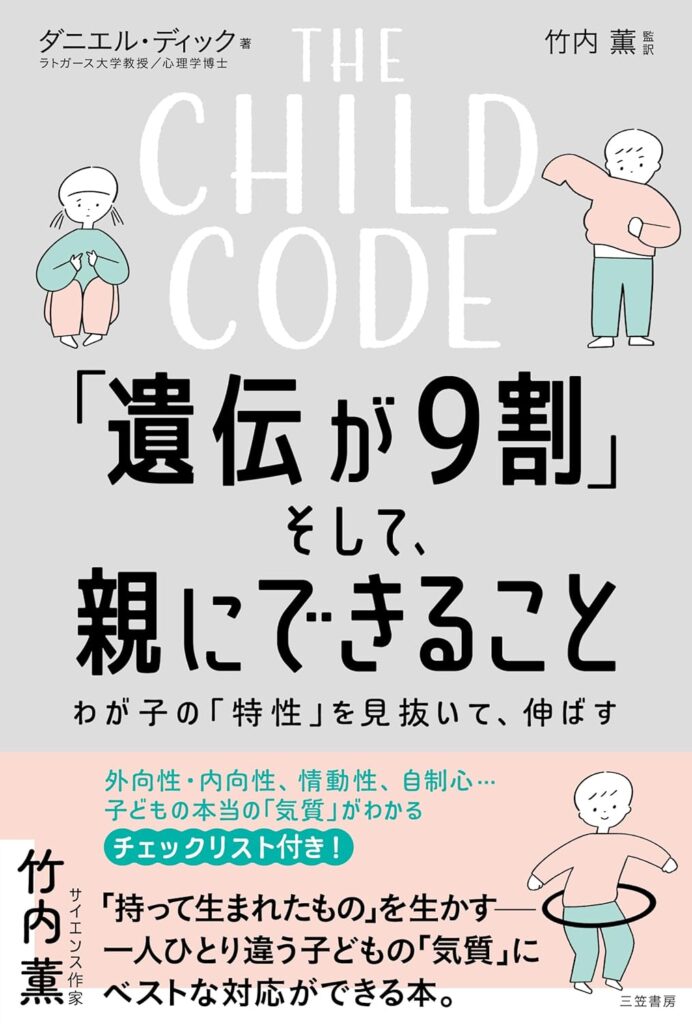
ダニエル・ディック (著)/ 竹内 薫 (監修, 翻訳)/ 三笠書房
【2】 子どものうちには直らない
親野智可等先生 子どものうちには直らない 再生時間:約6分44秒
≪子どものうちには直らない の要約・ポイント≫
きょうだいの一人は片づけが得意で、もう一人は全くできないことがあります。
これは生まれつきの資質が大きいと感じます。
しつけや育て方で変わるなら、どちらも片づけが得意になるか、どちらもできないかになるはずです。
生まれつきの資質が大きいのです。親の育て方のせいではありません。
朝型か夜型かも遺伝子レベルできまっていることがイギリスの大学の研究でわかっています。
遺伝子も発見されている。こうしたことをしっかり認識してください。
でないと、いたずらに叱ることが増えてしまいます。
「片づけなきゃダメ」「だらしないね」…
「子どものうち、小さいうちの方が直る」は全部嘘です。
逆に、大人になってからの方が直すことができます。
大人になれば必要に迫られます。そして、その気になれば、意思や問題解決力を持っているので直すことができます。
私自身も大人になってから、忘れ物や時間にルーズな性格を改善しました。
人間の人生は、生まれつきのもの、環境、そして本人の自由意志の3つで決まります。
遺伝子や環境の奴隷ではなく、強い意志を持って行動すれば、性格を改善することができます。
しかし、子どもには強い意志、モチベーションがないため、性格を直すのは難しいです。
子どもは将来・人生・仕事…何も考えていない。だからかわいいのです。だから直らない。
【3】 叱らないで合理的工夫を!
親野智可等先生 叱らないで合理的工夫を! 再生時間:約3分05秒
≪叱らないで合理的工夫を! の要約・ポイント≫
子どもをいたずらに叱ることは弊害しかありません。
「どうせ私なんかダメだ」「ぼくはママに大切にされていないかもしれない」…
自己否定感が強まり、親子関係が悪くなります。子どもは余計に反発します。
親子関係は最初の人間関係です。親子関係が悪くなると、子どもは人を信じられなくなります。他者不信感を持ってしまう。そうすると被害妄想的な言動が多くなり、友だちなどと良好な人間関係が築けなくなります。
生まれつきのものが大きいから、親のせいではないから、気持を楽にしてください。
これが非常に重要です。
うまく行かないことには合理的な工夫が必要です。
・毎朝朝顔に水をやる約束をした子どもができない場合、ペットボトルに水を入れて枕元に置くことで、朝起きたときに水をやることができるようにする
・歯磨きが始められない子供には、歯ブラシセットをお茶碗の横に置いておく。
・時間にルーズな子供には模擬時計やおうち時間割を使う。
できるようにしてあげることです。
【4】 手伝ってあげる、やってあげると親子関係は良くなる
親野智可等先生 手伝ってあげる、やってあげると親子関係は良くなる 再生時間:約5分52秒
≪手伝ってあげる、やってあげる と親子関係は良くなるの要約・ポイント≫
★親子関係が良くなり、自己肯定感が高まると、大人になってから直せるようになる!
それでも子どもができないときには、親が手伝ってあげる、やってあげる。
「やってあげると自立ができない」は迷信です。
発達心理学の最先端の研究では、親が手伝ってあげる、やってあげることで子どもの自立が促進されることがわかっています 。
親が手伝ってあげる、やってあげることで、子どもの自己肯定感が高まり、親子関係が良くなります。
親にやってもらった子、手伝ってもらった子は、そのありがたみを知っているので、友だちが困っているときに、手助けしたり、やってあげたりができるようになります 。
やってあげるときはいちいち叱らない。余計なことを言っては、子どもは感謝せず、親子関係も悪くなる。自己肯定感も上がらない。
明るく楽しい気持ちでやってあげる。
自己肯定感が保たれている子どもは、大人になってからも困難に立ち向かう力を持つことができます。
「このままじゃダメだな。直そう。私なら直せる」と思えるのです。
とにかく子どもの自己肯定感、他者信頼感を大事にしてください。
この2つは基本的信頼感と言って人間土台ですので、一番大事にしてください。
それには親子関係が大切です。
この講演会のテーマの「学力」も自然とついてくる「生きる力」、「非認知能力」もここからスタートします。
【5】 「非認知能力」は親子関係で育つ
親野智可等先生 一番大切な「非認知能力」は親子関係が育てます 再生時間:3分23秒
≪「非認知能力」は親子関係で育つ の要約・ポイント≫
★「非認知能力」の中で一番大事なのが自己肯定感、他者信頼感。それは良い親子関係で育つ!
今、「非認知能力」というものが非常に注目されています。
「非認知能力」の対となるのが「認知能力」です。「認知能力」とは、偏差値や学力テストの点、IQなどの数字ではっきりわかる能力です。
一方、「非認知能力」は数字化して判断できない、ばくぜんとした能力です。
今言った自己肯定感や他者信頼感、自己管理力、それに自己実現力、ストレス耐性、メンタルの安定性、目標に向かって試行錯誤してやり切る力・グリット、回復力、自己決定力、メタ認知力、思いやり、コミュニケーション力、協力する力、リーダーシップなどの能力です。
いろいろ研究され、この「非認知能力」を育てることが非常に重要だとわかっています。
・学力も非認知能力によって決まってくる。
・生涯年収レベルにも圧倒的な影響力を与える。
では、この「非認知能力」を育てるにはどうしたら良いか?
親子関係を良くして、自己肯定感、他者信頼感を育てることです。
「非認知能力」の中で一番大事なのが自己肯定感、他者信頼感だと、私は思います。
【6】「やりたい!」遊びが大事
親野智可等先生 「やりたい!」遊びが大事 再生時間:4分38秒
≪「やりたい!」遊びが大事 の要約・ポイント≫
★スポーツでも、勉強でも、好きな遊び、「やりたい!」遊びを通していろいろな非認知能力が身につく。
2つ目に強調したいのが遊びの大事さです。
日本の発達心理学の大家、お茶の水女子大学名誉教授・内田伸子先生の研究で、いわゆる難関大学に合格した学生さんの親子さんにアンケート調査し、幼稚園、保育園の時に何を大事にしたかを調べたところ、一番多かったのが「本人が好きなやりたい遊びをたっぷりやらせた」という回答が多かった。
本人がやりたい好きな遊びをやっているときに非認知能力が育つとわかったのです。
「大きい砂の山を作って長いトンネル掘りたい」という子どもの場合
自分がやりたいことを自分で見つけている。主体的な自己実現に向かっているのですね。
そして自分がやりたいことだから頑張る。
「崩れちゃった。どうしたら大きい山作れるかな。やっぱ手じゃダメだな、スコップにしよう。大きいスコップは〇〇ちゃんが使っているな。〇〇ちゃん、ちょっと僕にも貸して」
〇〇ちゃんから「だめだよ。僕使っているもん」と言われたら、
「そんなこと言わないでね。貸してじゃじゃんけんしよう」と交渉、コミュニケーションする。
または「じゃあ何々ちゃん一緒に砂の山を作らない」と誘う。
「ああ、でもうまくいかないな。じゃあ水をかけよう。じょうろが必要だ」
試行錯誤してやり遂げる。そして、諦めずにやり取る。
「うまくいかないなあ。もっと下を掘ればいいんじゃないか」
なんでできるかというとこれね、自分がやりたいことだからです。
自分がやりたいことを主体的に。 喜びにあふれて。 楽しみながらやっている。
いろいろな非認知能力が身につくわけです。
やらされること、受け身的、受動的だと、意欲がないのでこのようにはならない。
本人がやりたがる好きな遊びをやらせるって事が大事です。
こういう話を聞いたあるママは子どもに「遊びなさい」と言う。頭がよくなるみたいな遊びを一生懸命紹介する。
これ、全くわかっていません。大事なのは本人が好きなやりたい遊びなのです。
本人が「勉強やりたい!」、だったら勉強をやらせればいい。
子どもは遊びが大事だから勉強しちゃダメという人がいますがそうではない。
本人のやる気のベクトルの向かっている先を一番大事にする。
スポーツだったらスポーツで良いし、勉強だったら勉強で良い。小さい子にとってはほとんどが遊びです。
【7】早期教育にはほとんど意味がない
親野智可等先生 早期教育にはほとんど意味がない 再生時間:4分28秒
≪早期教育にはほとんど意味がない の要約・ポイント≫
★ひらがな、漢字、計算の勉強…、早い段階で勉強させても、効果は3年以内になくなる。
幼稚園、保育園でも、自由遊び、自由保育の園の方がいい。
遊びたいことをたっぷりやれるそういう園の方が後伸びするってことが、研究で分かっています。
地域の事情もあるので、なかなかそう簡単にはかない。そういう場合はせめて、うちにいるときは本人の主体性、好きな遊びを応援してあげましょう。
早期教育と幼児教育を混同している人が非常に多いですが、全く別も別のものです。
幼児教育においては遊びが大事です。早期教育というのはそうではなくて、小学校へ入る前のひらがな、漢字、計算の勉強。
いわゆる勉強を早い段階でやることを早期教育と言っていますが、これにはほとんど意味がないことがわかっています。
有名なのはアメリカのボストンカレッジのピーターグレイ教授の研究です。
幼稚園、保育園段階で早期教育をやっても、その効果は3年以内に消え去ってしまうということが明らかになっている。
私も実際経験しています。小学1年を何回か担任しましたが、早期教育を受けてきた子どもたちは、スタートダッシュはすごい。読める、書ける、計算できる。一方自由保育で遊びまくってきた子どもたちはそういうのは苦手です。
でも、同じ子供たちを4年生あたりで受け持つと、「あれ、この子1年生の時にあんなにできたのに…」という子が何人もいるのです。逆に1年生の苦手だった子が伸びてきている。
幼児期の早期教育の効果は三年以内になくなり、その後は自由な遊びをしていた子どもたちに学力は逆転される。
内田伸子先生も同じ研究しており、自由遊びをしてきた子どもの方がコミュニケーション力、語彙力も伸びるので、国語の力が高いという結果が出ています。
でも、こうしたことは、なかなか世の中に浸透していません。アップデートしてください。
【8】情緒安定には腸が大事
親野智可等先生 情緒安定には腸が大事 再生時間:5分30秒
≪情緒安定には腸が大事 の要約・ポイント≫
★食べ物と運動を大事にし、腸内環境を浴すれば、メンタルが安定し、記憶力も良くなる!
今日のテーマ、非認知能力を高める、この中でも大事なことがメンタルの安定です。
ストレスに耐える、情緒が安定している、安らかで穏やかな気持ちでいる、こうしたことも非認知能力として非常に重要です。
そこで大事なのが腸内環境です。
自己肯定感を高める。安らぎを感じる。幸せを感じる。ストレスに耐える。イライラしない。
これにはセロトニンが非常に重要な働きをしている。
このセロトニンっていうのは、以前は脳で作られると考えられていました。
実際、脳でも作られるのですけれど、腸で作られることがわかっています。
腸内環境が悪いとセロトニンはあんまり作られない。
作られたとしても、腸内環境をよくするために使われてしまい、脳で活用することができない。
皆さんのメンタルの安定にも、子どものメンタル安定、そして非認知能力を高める上で腸はすごく大事です。
腸は第二の脳と言われています。
腸内環境をよくするにはどうするか。
一つは食べ物です。学力を高める上でも、食べ物大事なことが研究でわかってきています。
特に大事なのは野菜、果物、ナッツ類などの食物繊維を増やすことです。あとは発酵食品が大事。
水分もちゃんと十分に摂取する。白砂糖系統のものはできるだけ控える。
もう一つは、やはり運動です。
NHKで「人体」というスペシャル番組でやっていたのですが、これが大変勉強になりました。
定期的な運動、ジョギング、ウォーキングのような有酸素運動で腸内環境は良くなり、便秘も解消する。
さらに運動すると記憶力がよくなるってことが明らかになっているそうです。
運動すると筋肉からメッセージ物質というが出る。そして「記憶力を高めなさい」というメッセージが筋肉から脳に届く。
それを受けた脳の中の海馬が、記憶を司る神経細胞を新しく作るそうです。
ですから皆さん自身にとっても、子どもにとっても運動は大事です。
もちろん本人が嫌いな運動じゃ続かないので、楽しくできる運動を定期的にやるというのがベストだと思います。
記憶力が増し、腸内環境も良くなってセロトニンが出て、自己肯定感が高まりメンタルも安定するということです。
あとは、トイレに必ず行く排便習慣、十分な睡眠が大事です。睡眠不足も便秘を引き起こします。
【9】スキンシップ、じゃれつき遊びをしましょう
親野智可等先生 スキンシップ、じゃれつき遊びをしましょう 再生時間:5分18秒
≪スキンシップ、じゃれつき遊びをしましょう の選択肢の要約・ポイント≫
★スキンシップで幸せ感、自己肯定感が高まり、じゃれつき遊びでキレない子になります
毎日ハグをしましょう。
「大好きだよ」「ママとパパの宝物だよ」「このうちに生まれてくれてありがとう」…
できれば、その子の存在そのものを丸ごと肯定する言葉を送りながらハグをする。
一番いいのは、夜寝る前のハグです。
脳科学の研究で、寝る直前の精神状態は寝ている間続くことがわかっています。
寝る前にハグすると幸せいっぱいが寝ている間中続き、寝起きも良くなり、自己肯定感も上がります。
逆に寝る前に叱るのは最悪です。寝ている間中の嫌な感じはよくないですね。
タッチケアもしましょう。
子どもの背中とか頭、腕、お腹や足でもいい。本人が嫌がらないところをゆっくりしたスピードで軽くソフトにタッチする。
マッサージだとちょっと強いです。触るか触らないくらいのタッチケア。
NHKの実験結果では、1秒間に5cm進むくらいの速さ、強さがいいそうです。
そこまで意識できないでしょうが、ゆっくりと愛情を込めてしましょう。
このハグやタッチケアのスキンシップで、子どもにも親にもオキシトシンという幸せホルモンが出て、ストレスを和らげ、イライラを沈め、安らかで幸せな感じを整えてくれます。
ハグやタッチケア、ぜひ増やしてください。
オキシトシンをたくさん出す経験を子どもの頃にしておくと、大人になってから出やすい幸せ体質になります。
親子じゃれつき遊びも大事です。 手押し相撲、指相撲、おしくらまんじゅう、お馬さんごっこ…こうした遊びを親子で楽しみましょう。親子で組んずほぐれつ、大騒ぎ、ストレス解消。
こうした時、脳科学的には扁桃体というところが活性化しているのです。
当然そういう状態はずっと続かない。静かになる。静かになって絵本を読む、ご飯食べる、昼寝する、こうして静かになる時、活性化している偏桃体に前頭前野がブレーキかけるそうで、これがとても大事。
毎日親子でじゃれつき遊び、大笑い、大ふざけしていると、ブレーキかける力が強くなるのです。ブレーキかける練習をしている。
イラッとし偏桃体が活性化したとき、ブレーキがかかる子になるのです。
いつも大はしゃぎをせず、「静かにお行儀よく」と言われていると、ブレーキをかける練習がされてないので、いざという時にキレやすい子になってしまいます。
いざという時にキレないアンガーマネジメント。皆さんにとっても非常に重要ですが、これも非認知能力の非常に重要な部分です。
【10】 メタ認知能力を鍛える読書
親野智可等先生 メタ認知能力を鍛える読書 再生時間:5分11秒
≪メタ認知能力を鍛える読書 の要約・ポイント≫
★読書で人の心の動き方がわかるように。読み聞かせや家族の読書タイムを!
メタ認知能力も重要です。
「メタ」というのは一つ上っていう意味です。「自分は今ストレスいっぱいだ」「もうすぐイラっとしそうだ」というように、もう一つ上の自分が自分をちゃんと認知するのがメタ認知力です。これを鍛えるためには読書が非常に効果的です。
絵本や物語には、主人公や脇役、いろんな登場人物の心の中が描写されていますが、そうしたものをたくさん、間接的にでも経験しておくと人間の心の動き方がわかるのです。
『キャンディ キャンディ』の思い出
私は子どものころ『キャンディ キャンディ』という漫画が大好きでした。
お話の中でキャンディがイライザって子にいじめられるのです。
『キャンディ キャンディ』を読むと、
「ああ、いじめられるとこういう気持ちになるんだ」
「こういうことを言われると、人間ってね、こういうふうに感じるんだ」
「自分は絶対こういうこと言わないようにしよう」
と思えるようになりました。
漫画も含めて、アニメ含めて物語、絵本、小説。 こういうものに触れる事は、非認知能力である思いやりや、メタ認知力をつける上で効果的です。
どうしたら読書が好きになるか。
一つは、やはり読み聞かせです。
あまり絵本好きではないという子もいる。 そういう子は、図鑑などが好きな本を読んであげればよいのです。
物語にこだわりすぎると本が嫌になってしまいます。本人が好きな本を読んであげることが大事。
その時は絶対叱らないことです。「パパ、ママに愛されているな」を実感しながらの至福の時間の中に本がある。
ママパパに愛されているという実感が一番幸せなのですが、その時に本があると「本って幸せなんだ」と脳が勘違いするのです。
それによって本が好きになる。
読み聞かせの次におすすめなのが一家の読書タイム。5分でいいから時間を決めて、その時間は家族みんなが読書する。
みんな読書をするから、子どもも読書をするわけですが、時間が終わっても続き読みたくなるのです。あとは親子で図書館や本屋にしょっちゅう行く。こうした時間をたくさん取ることが、読書好きになるためには大事です。
【11】自然体験、リアルな感動を!
親野智可等先生 自然体験、リアルな感動を! 再生時間:2分6秒
≪自然体験、リアルな感動を! の要約・ポイント≫
★絵本や動画とは違うリアルな感動が探求心や芸術的創造にむずびつきます。
自然体験も大事。自然の中にいるだけでセオトニンが出ます。
自然の中で蝶々を見て「綺麗だな。なんでこんなに綺麗なんだろう」と感動する。こうしたリアルな感動が大事です。
絵本や動画と本物とは、インパクトが違うのです。子どもも、親も知っているつもりになっている。でも、本物は全く違う。
自然の中で得た感動が、「なんでこういうふうに光るんだろう」といった学問的探求に結びついたり、これを表現したいという芸術的創造に結びついたりします。
筑波大学の落合陽一さんは子どもの頃は昆虫少年で、蝶を見て「なんでこんなに綺麗になるんだろう」びっくりしたことが今の研究の土台になっているそうです。
そういう人は一流の科学者でたくさんいます。茂木健一郎さん、養老孟司さん、福岡伸一さん、ノーベル賞受賞者の大隅良典さん…。みんな子供の頃、自然の中で遊びまくった昆虫大好き少年、あるいは少女です。
自然体験をする、自然の中で遊ぶことが大事。もちろん森に行くのがベストですけが、近くの公園でもかなりのことができます。
▼関連ページ、サイトのご案内
第2部の「子育て相談おはなし会」の模様はこちらでお伝えしています。
令和6年6月に開催された、第1回講演会「子どもの学力と人間力を高める「親の5つの習慣」」、そして令和7年3月の第2回講演会「「自ら動く子ども」に育てる親子関係」」のレポート、アーカイブ動画も公開しています!
親野智可等先生のプロフィールやホームページ、SNSご紹介と、ポピフル連載・記事一覧がプロフィールページからご覧いただけます。
この講演会は、全国のママをつなぐネットワーク、ママノユメ、特定非営利活動法人Wing-Wingと共同開催いたしました。一般社団法人 ガールスカウト福岡県連盟、(株)マザープラス、(株)to planのご協力もいただいております。
ママノユメホームページでも、講演会の模様をレポートしています!

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育