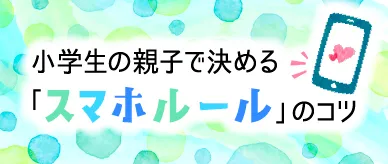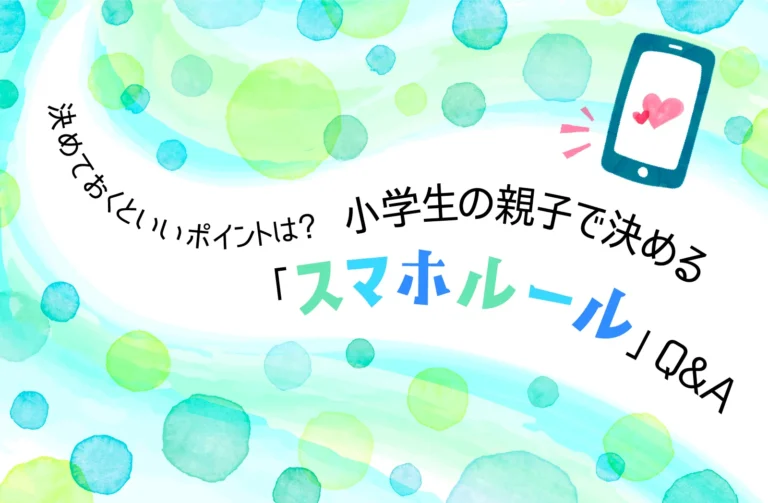
決めておくといいポイントは? 小学生の親子で決める「スマホルール」Q&A
小学生の親子で決める「スマホルール」のコツ
どうすれば親子でスマホと賢く付き合っていけるか、親子でスマホのルールをつくるときのコツを一緒に考えてみましょう!
ここ数年、小学生のスマホ所有率が急速に上がりつつあります。もはや、子どもとスマホの問題は保護者にとって避けられない課題といえるでしょう。そこで、20年間、公立中学校で生徒指導主事などを担当され、文部科学省や総務省などでも子どもとネット問題の委員を歴任されてきた竹内和雄先生に、親子でスマホのルールをつくるときのコツについてお聞きしました。
1回目は、スマホを持たせる年齢や思春期の子どもとのルールづくりのポイントを伺いました。引き続き第2回もQ&A形式でルールづくりの際の具体的なポイントについて、竹内先生に教えていただきます。
加工-1-300x300.webp)
竹内 和雄(たけうち・かずお)さん:兵庫県立大学教授(教育学博士)
公立中学校で20年生徒指導主事等を担当(途中小学校兼務)。寝屋川市教委指導主事を経て2012年より現職。生徒指導を専門とし、いじめ、不登校、ネット問題、生徒会活動等を研究している。文部科学省有識者会議座長など、子どもとネット問題についての委員を歴任。生徒指導提要(改訂版)執筆協力者。2014年ウィーン大学客員研究員。
竹内先生に聞く!スマホルールQ&A
ルール作りのポイントは?

Q. 子どもとスマホのルールを決める際に、おさえておくべきポイントを教えてください。

A. 「時間」「場所」「マナー」「危険」「お金」の5つが、スマホのルールづくりのポイントです。
時間のルール
まず「時間」は、スマホを使っても良い時間のことです。「夜◯時まで」と終了時間を決める場合と、「1日□時間以内」と合計使用時間を決める場合が考えられます。「終了」とは、充電場所に置いたときなのか、見るのをやめたときなのか、言葉の定義も決めておいたほうがケンカが起きにくくなります。
場所のルール
次に「場所」では、「自分の部屋には持って行かない」「居間だけで使用する」など、使用可能なエリアを決めます。風呂・トイレ禁止も重要です。
マナーのルール
そして「マナー」では、「人が嫌がることは書き込まない」「食事中は使用しない」といった、人として守ってほしい点を決めておきます。
危険のルール
「危険」では、「ネットで知り合った人と直接、会わない」「個人情報を書き込まない」など、いわゆるネット犯罪につながりかねない行為を防止します。
お金のルール
最後に「お金」は、課金やネットショッピングなどについてのルールです。最近は、コンビニで買えるプリペイドカードで課金できたり、「投げ銭」という送金システムも出てきたりしました。個人間で簡単に商品を出品・売買できるサイトも多数あります。そうした新しいシステムの仕組み・危険を知っておくことも必要でしょう。
これらのルールは、できるだけ対等に意見を出し合って決めてほしいのですが、話の主導権は親が握ってください。子どもの言い分を丁寧に聞くことと、子どもの言いなりになることは別です。親としてゆずれない一線は決めておき、理由とともに伝えましょう。
また、一度決めたルールを頑なに守ろうとはせず、子どもの成長や状況の変化に応じて、少しずつ修正していきましょう。きちんと話し合った上での変更なら、変えることを恐れる必要はありません。

スマホの時間管理は?

Q.子どもは習い事や塾などで、毎日忙しく過ごしています。こういった子のスマホの時間管理のポイントを教えてください。

A. スマホの時間管理において最も重要なことは「子どもの健康と成長のための睡眠時間の確保」です。
例えば、購入前に「1日□時間以内」と決めたものの、習い事や塾に通うようになると、帰宅が遅くなります。そこから夕食、入浴をすませ、その時点で22時だったとしても、当然子どもは「1日□時間以内」なんだからと言ってスマホをさわり始め、深夜まで起きていることが日常化してしまいます。こうなると、時間制限のルールは子どもにとって都合の良いバリアになってしまいます。
こうした場合は、先述したように状況に合わせてルールを変えていきましょう。「1日□時間以内」というルールが不都合になったなら、塾のある曜日だけは「夜◯時まで」にするなど、臨機応変に対応してください。当然、子どもは嫌がるでしょう。しかし、スマホの時間管理において最も重要なことは「子どもの健康と成長のための睡眠時間の確保」です。親として「成長期のあなたの体が心配である」ことを丁寧に伝え、ルール変更を納得してもらってください。
そういう意味では、「自室にスマホを持ち込まない」というルールも大切です。大抵の子どもは「スマホが目覚まし時計だから」と言い訳して持ち込もうとします。でも、「夜間は居間で充電しておく」などのルールを決め、自室にはできるだけ持ち込ませないほうが良いでしょう。
スマホのルールを守らせるには

Q.購入前に決めたスマホのルールを守らせる、効果的な方法があれば教えてください。

A. 最も良い方法は、決めたルールを誰の目にも留まる場所に貼っておくことです。
私のおすすめは冷蔵庫です。単純な方法ですが、言葉だけで決めておくのと、わかりやすく「可視化」させておくのとでは、ルールが守られる確率に大きな差が出るはずです。
そして、もうひとつの方法は「親も一緒に守る」ことです。親も同じように守っている中、子どもが自分だけルールを破ることは簡単ではありません。さらに「一緒に頑張っている」という一体感も生まれ、信頼感の醸成にもつながります。
ただこの方法は、特に仕事をしている親御さんにとっては現実的ではないかもしれません。それでも、スマホは子どもが寝た後でさわるようにするなど配慮に努め、実現してもらえたらと思います。
少し長いスパンでとらえると、スマホのルールは、最初はできるだけ厳しめに設定しておき、年齢や判断力に応じて徐々にゆるめていくほうが守られる傾向にあります。つまり、親が子どものことを決める「他律」から、子どもが自分自身で決める「自律」へのゆるやかな移行という意識が、スマホとのルールづくりにおいて重要なのです。最終的には自分でルールを決め、それを守れる人間になることを目指し、親が導いてあげてください。

7月号でも、引き続き竹内先生にスマホとルールに関する質問をお聞きしていきます。
文:シガマサヒコ
イラスト:あんみ
編集協力:どりむ社

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育