
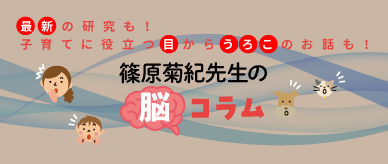
❸ 子どもの頭の中では何が起こってる? <幼児期に効く! 脳コラム5選>
篠原菊紀先生の脳コラム
子どもの脳の発達について年齢別に解説。幼児期は「頭を使うのが好き」「体を動かすのが好き」「人とかかわるのが好き」になるこ
子どもの頭の中では何が起こってる?

子どもが上手にできる/できないで、つい一喜一憂してしまいがちですが、目指すべきは何か。今回は、脳の発達の様子からお伝えします。
1~3歳の脳の発達
大人の脳の重さは体重の約2%。男性では1350~1500g、女性では1200~1250gほどになります。一方、子どもの脳は3歳くらいで約1000g、大人の8割ほどの重さになります。このころの子どもの体重は14㎏くらいですから、脳がずいぶん重いわけです。
実は、大人も子どもも大脳の神経細胞数は約1400億であまり変わりません。しかも、神経細胞同士のつながり(シナプス)は1~3歳くらいで過剰に作られ、その後、必要なつながりだけが残されていくので、1~3歳でシナプスが多いのです。
このため、1~3歳の子どもの脳では、ひとつの情報の入力に対して必要以上の出力を行ってしまいます。
たとえば、人差し指だけ動かすという命令を指に送っても、神経細胞どうしが過密に繋がっているので、他の指も同時に動いてしまうということが多々出てきます。だから1~3歳は細かな動きができず、ジャンケンのチョキができないなどといった大雑把な動きになります。

3~7歳の脳の発達
その後、3~7歳の脳では過剰なシナプスの刈り込みが行われ、効率的な処理が行えるようになっていきます。
また、「髄鞘化(ずいしょうか)」といって、神経細胞が情報を伝える際に用いる軸索(じくさく)が脂肪の鞘(髄鞘)に覆われ、情報の伝達効率をよくしていきます。電線を被膜で覆うと漏れが小さくなるようなものです。髄鞘化は、基本的動作に関する部位では3歳くらいまでで完成します。
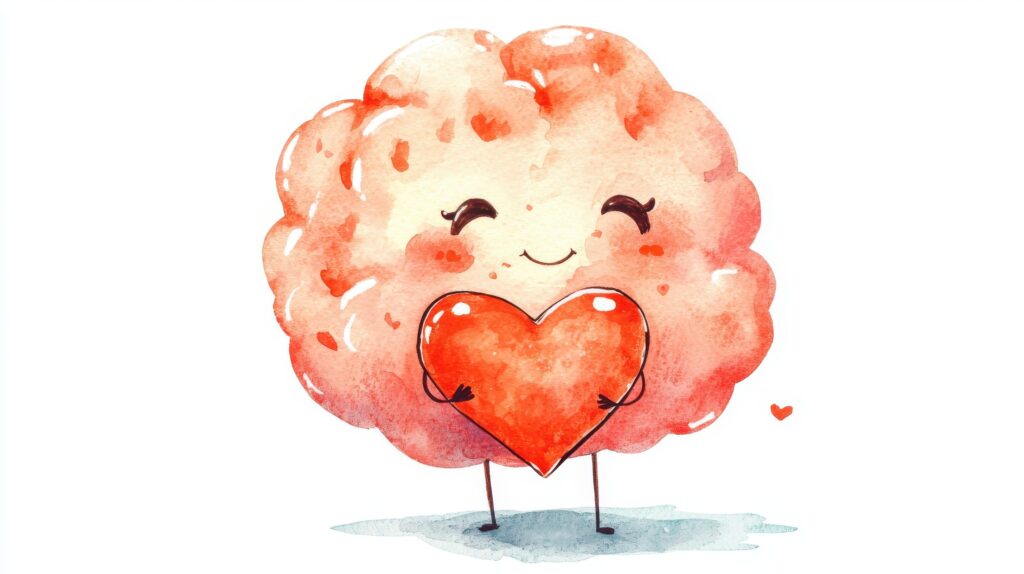
そして3歳以降になると、長期記憶に関連する大脳の前頭連合野(ぜんとうれんごうや)や頭頂連合野(とうちょうれんごうや)、側頭連合野(そくとうれんごうや)などで髄鞘化が進みます。
そしてこの時期に舌状回など単語の認知にかかわる脳部位と、眼窩前頭前皮質(がんかぜんとうぜんひしつ)、内側側頭葉(ないそくそくとうよう)などの記憶と好き嫌いにかかわる脳部位が発達のピークを迎えます。
たっぷりの愛情で包んであげましょう
舌状回の発達は、おうちの方との愛着関係の中で言葉を覚えていくこととかかわると考えられ、虐待を受けた子どもでは、ここの成長が遅れることを指摘した研究もあります。
「頭を使うこと」「体を動かすこと」「周囲とかかわること」の好き嫌いも、この時期、周囲との愛着関係の中で育まれていきます。
信頼できる人とのスキンシップは信頼ホルモン=オキシトシンの分泌を高め、お互いの絆を高めます。信頼できる人の声、笑顔も同様です。
オキシトシンの分泌が増すと、ドーパミンの分泌も増しやすくなり、学習効果も促進されます。また自己肯定感が高まり、チャレンジする力が育まれます。

目標は「嫌いにならないこと」
子どもに賢くなってほしい、スポーツの才を伸ばしてほしい、コミュニケーション力を身につけてほしい。おうちの方がそのように考えるのは当然です。
しかし、3~7歳の時期では、頭の使い方や体の動かし方、人とのかかわり方が上手になることよりも、「頭を使うのが好き」「体を動かすのが好き」「人とかかわるのが好き」という感覚を獲得することのほうが重要です。
もっといえば、そういうことが「嫌いじゃない」、その感覚の獲得こそ大事です。
「できる」を目指して叱られ、トラウマを作り、「嫌い」になっては本末転倒です。「楽しく」が基本中の基本です。楽しんでいるうちにできるようになる、それがまさに『幼児ポピー』の目指すところです。
↓↓↓篠原先生によるその他の 【幼児期に効く!脳コラム】 はこちら!↓↓↓
❶ 脳の根っこを育むとは?
❷ 大切なのは「好きになること」
❹ 何歳でどんな運動が効果的!?
❺ 後伸びにつながる力を育もう

篠原 菊紀(しのはら きくのり)先生
公立諏訪東京理科大学 特任教授(脳科学、健康科学)。人システム研究所所長。東京大学、同大学院教育学研究科修了。『頭がいい子を育てる8つのあそびと5つの習慣』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『子どもが勉強にハマる脳の作り方』(フォレスト出版)など著書多数。NHKこども科学電話相談など、TV、ラジオ、雑誌でもご活躍。
ポピーが運営する教育情報サイト「ポピフル」では、他にも脳科学者の篠原菊紀先生による子育てに役立つお話をご紹介しています。合わせてご覧ください。

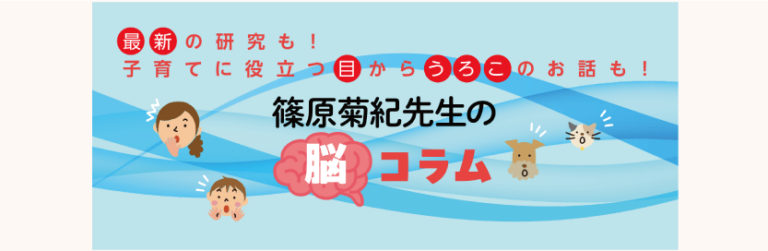
❶ワーキングメモリが知的能力の基礎 <勉強に効く脳コラム10選>
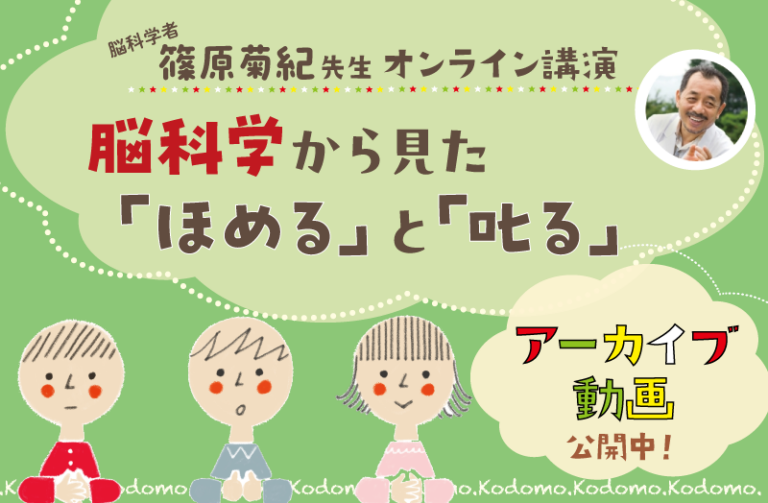
脳科学から見た『ほめる』と『叱る』by篠原菊紀先生 ~子育て講演動画を公開!
「ポピフル」は月刊ポピー、全日本家庭教育研究会がお届けしている教育情報サイトです。

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育



