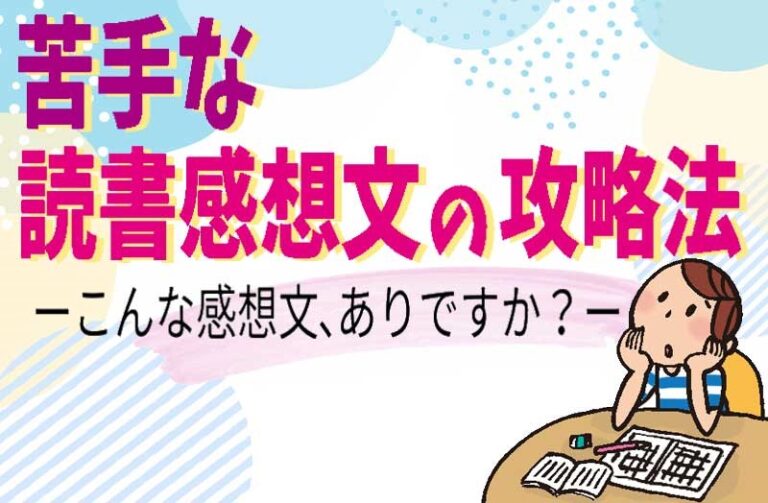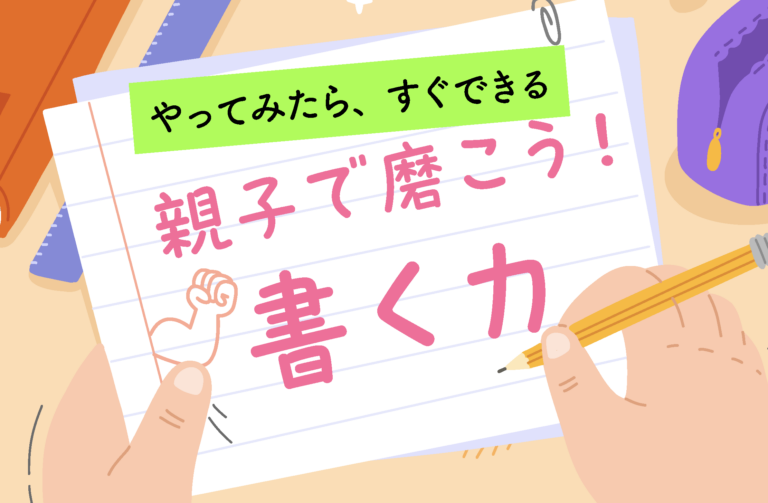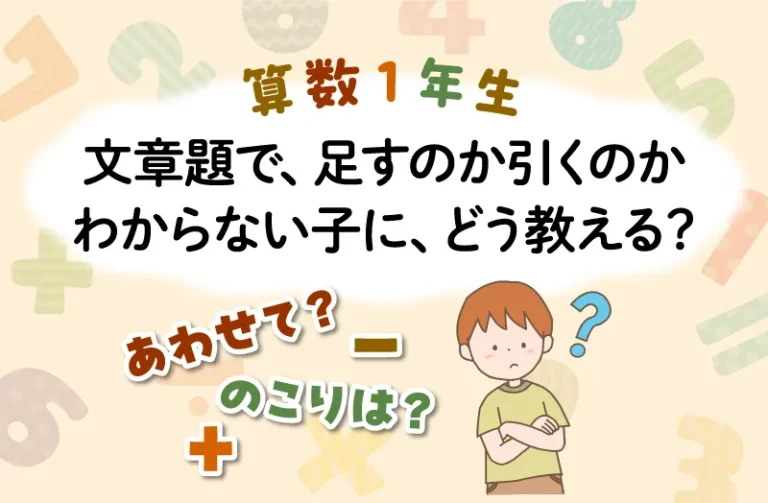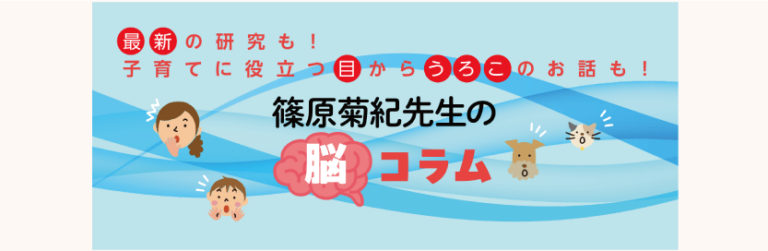
勉強に効く!脳コラム10選 ~ ❻「集中学習」より「分散学習」
篠原菊紀先生の脳コラム
「集中学習」より「分散学習」

今回は、よりよい記憶の仕方や学習法のお話です。
「寝る子は育つ」ということわざがありますが、記憶を根付かせるにも、睡眠は大切なようです。
インターリーブ(同時並行)学習法
最近、「インターリーブ学習法」が話題だそうです。
インターリーブ(interleave)は交互に配置するとか、挟み込むといった意味です。inter(間)に leave(置く)、ひとつのことをひたすらくり返すのではなく、その間に別の訓練や学習を挟むのです。
たとえば、テニスの練習なら、サーブばかりを練習するのではなく、フォアハンド、バックハンド、ロブ、スマッシュなどをとりまぜたメニューで練習する。そのほうが上達しやすいというのです。
カリフォルニア大学ロサンジェルス校のロバート・ビューク博士が提唱しているそうです。
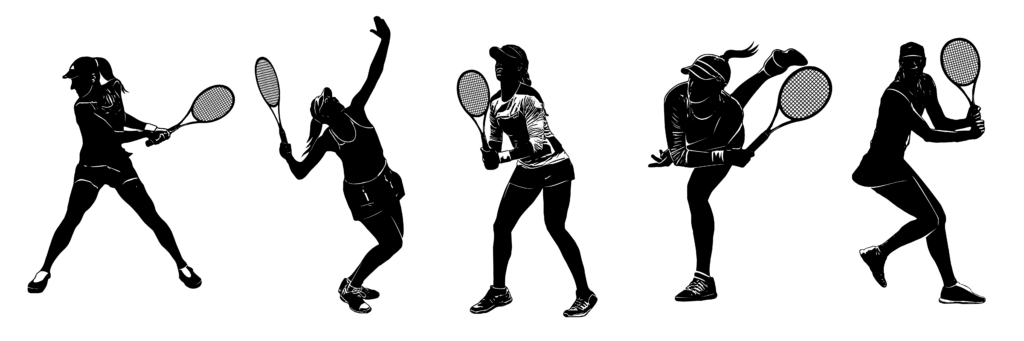
記憶にもインターリーブがいい
スポーツばかりではありません。ビューク博士らは、さまざまな絵画と作者を学生たちに覚えさせ、絵がどの画家のものか当てさせる記憶実験を行っています。このとき、一方のグループは作者ごとに絵をセットにして覚える方法で記憶します。もう一方のグループは、作者ごとではなくランダムに記憶していきます。前者が集中学習、後者はインターリーブ学習ということでしょう。
結果は、インターリーブ学習をしたほうが成績がよかったそうです。
間に睡眠があることも重要?
スポーツや音楽などの「技の記憶」では、学習後に睡眠を挟むと成績が向上しやすいことが知られています。たとえばジャグリングの学習では、学習直後に寝たグループのほうが、起きていたグループより数か月後までうまかったそうです。キーボードたたく不規則な順番を覚える実験でも、間に睡眠をはさむと20%近く成績がよくなったそう。テニスでは1日の練習でサーブ、フォアハンド、バックハンド、ロブ、スマッシュを行えば、10日の練習で10回の睡眠が挟めます。一方、サーブを2日、フォアを2日、バックを2日…では、それぞれの技の学習時間が同じでも、それぞれの技に対して2回の睡眠しか挟めず、技の定着が遅れる可能性があるわけです。
「技の記憶」ばかりではありません。英単語を覚える、年号を覚えるといった言葉にできる記憶(陳述的記憶といいます。逆に、技の記憶は非陳述的な記憶と呼びます)も、睡眠、特に深い眠りのときに定着することが知られていますから、間に何回眠りを挟むのかが学習効率にかかわる可能性があります。

記憶しようとするより、引き出すことが大事
一方、ビューク博士の絵画記憶実験では、睡眠の関与なしで記憶に差が出ています。いろんな解釈があり得ますが、バラバラで覚えるときはそれぞれの絵で作者名を思い出す必要がある一方、ある作者の作品群を覚えるときは作者名を思い出す機会が少なくなります。
一般に、脳は出力依存性も持ち、記憶しようとするより、記憶を引き出そう、使おうとしたときのほうがよりよく記憶します。すると、分散学習のほうが改めて記憶を引き出す機会が多くなり、記憶の定着に役立つのかもしれません。
また、学習の初期はやる気にかかわる脳部位が活性化しても、しばらくすれば低下するのが脳の必然なので、目先を変える分散学習がよく、また、全体のつながりの中で学習が進むので、記憶同士をつなぐメタ認知ができやすいのかもしれません。
↓↓↓篠原先生によるその他の 【勉強に効く!脳コラム】 はこちら!↓↓↓
❶ワーキングメモリが知的能力の基礎
❷「すぐやる脳」をつくるコツ
❸よりよい学習習慣をつけるには
❹運動は苦手科目を底上げする!?
❺へぼを見るとへぼになる!?
❼目標達成には「報酬 ー(ひく) 罰金」がよろしいようです
❽鏡のような脳細胞
❾よい記憶法とは?
❿やる気ニューロンと移り気ニューロン

篠原 菊紀(しのはら きくのり)先生
公立諏訪東京理科大学 情報応用工学科教授(脳科学、健康科学)。東京大学、同大学院教育学研究科修了。『頭がいい子を育てる8つのあそびと5つの習慣』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。『子どもが勉強にハマる脳の作り方』(フォレスト出版)など著書多数。NHK夏休みこども科学電話相談など、TV、ラジオ、雑誌でもご活躍。
「ポピフル」は月刊ポピー、全日本家庭教育研究会がお届けしている教育情報サイトです。

 あそび
あそび 人間関係・接し方
人間関係・接し方 健康・運動
健康・運動 入学準備
入学準備 国語
国語 園生活
園生活 夢 実現
夢 実現 学校生活
学校生活 学習習慣
学習習慣 幼児期のまなび
幼児期のまなび 性格
性格 本・読書
本・読書 生活習慣
生活習慣 算数
算数 食事・食育
食事・食育