フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?
更新日:2025年3月14日

フィンランド教育は、世界中で高く評価される理由がいくつもあります。まず、教育費が無償で提供され、すべての子どもが平等に質の高い教育を受ける権利を持っています。さらに、教師は厳しい選抜を経て養成され、社会的地位も高く、教育の質を支えています。
フィンランドの教育システムは、試験や宿題に依存せず、生徒の自主性を重視した柔軟な学びを促進します。
このような環境が、フィンランドを教育の成功モデルとして位置づけ、世界一の幸福度を実現する要因となっています。
1.フィンランド教育とは?基本的な考え方を解説

フィンランドの教育は、平等性と自主性を重視しています。すべての子どもに均等な教育機会を提供し、教育費はプレスクールから大学院まで無料です。教育は個々の子どもの特性を尊重し、比較されることなく柔軟に行われます。また、教員は高い専門性を持ち、授業の自由度が高く、子どもたちの主体的な学びを促進します。学習時間は短く、ストレスの少ない環境で学ぶことができるため、子どもたちの幸福度も高いとされています。
| 年齢範囲 | 教育内容 | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| 幼児教育 | 0-6歳 | 幼児教育・保育 | 無料、地域に応じたサービス提供 |
| 就学前教育 | 6歳 | プレスクール(1年間) | 無料、基礎教育への準備 |
| 基礎教育 | 7-16歳 | 総合学校(9年間) | 無料、全科目を学び、個性を重視 |
| 高等教育 | 16歳以上 | 普通高校または職業高校(3年間) | 無料、大学進学または職業訓練を選択可能 |
| 大学・応用科学大学 | 19歳以上 | 学士課程(3年)・修士課程(2年) | 無料、研究と実践を重視 |
北欧の教育大国が掲げる「学びの哲学」
フィンランドの教育理念は、社会構成主義に基づいており、学びは他者との相互作用を通じて形成されると考えられています。このアプローチでは、教師は知識を一方的に伝えるのではなく、生徒の学びをサポートする役割を担います。具体的には、協同学習が広く実践されており、生徒は小グループでの活動を通じて問題解決能力を育むことが重視されています。
例えば、フィンランドの学校では「プロジェクト学習」が取り入れられており、生徒が自らの興味に基づいてテーマを選び、調査や発表を行います。この方法により、生徒は主体的に学び、実社会の問題に対する理解を深めることができます。さらに、フィンランドの教育システムでは、学びの過程を重視し、失敗を恐れずに挑戦する姿勢が奨励されています。これにより、生徒は自信を持って学び続けることができる環境が整っています
教師の社会的地位が高い理由とは?
フィンランドの教師になるためには、修士号の取得が必須であり、教育学部での学士課程を経て、さらに2年間の修士課程を修了する必要があります。教師の質を高めるため、教育実習も充実しており、実習期間は合計で6〜7ヶ月に及びます。
待遇面では、フィンランドの教師は高い社会的地位を持ち、給与水準も他の公務員と同等です。教員は授業内容や評価方法に対して大きな裁量を持ち、教育環境の改善に貢献しています。
また、フィンランドでは教員の専門性を維持するために、年間最低3日間の研修が義務付けられており、研修費用は地方教育委員会が負担します。これにより、教員は最新の教育理論や実践を学び続けることができ、質の高い教育を提供することが可能となっています。
学力テスト世界一を支える独自の教育観
フィンランドの教育がPISA調査で高評価を得ている理由は、教育制度の改革と教育理念の明確さにあります。1990年代に行われた大規模な教育改革により、フィンランドは中央集権的な教育システムから地方分権型へと移行しました。この改革では、教員に大きな裁量権が与えられ、教育課程の内容や指導方法が学校や教師の判断に委ねられるようになりました。
具体的には、フィンランドの教育制度では、学力テストや受験勉強が存在せず、子どもたちが主体的に学ぶことが重視されています。授業は少人数制で、教師は生徒一人ひとりに深く関与することができるため、個々の学習ニーズに応じた指導が可能です。PISA調査では、フィンランドの生徒は読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの分野で常に上位に位置しており、特に読解力では高い得点を記録しています。
また、フィンランドでは教育が無償で提供され、給食や教材も無料であるため、すべての子どもが平等に教育を受けることができます。このような環境が、学力の向上に寄与していると考えられています。
-
※引用・参照:
- 「Finnish education system」
- 「教育大国フィンランドに学べ」
- 「フィンランドの教員養成・教員資格について」
- 「フィンランドの教育と教師養成の秘密」
2.フィンランド教育が世界一と評価される理由

個別指導を実現する少人数制クラス
フィンランドの教育システムでは、少人数制クラスが個別指導を実現する重要な要素となっています。一般的に、クラスの人数は約20人程度で、教師は生徒一人ひとりに対してきめ細やかな指導が可能です。これにより、教師は各生徒の学習スタイルや進度に応じた個別のサポートを提供できます。
具体的な実践例として、プロジェクト学習が挙げられます。生徒はグループで特定のテーマに取り組み、調査や制作、プレゼンテーションを通じて学びを深めます。この過程で、教師は各生徒の進捗を観察し、必要に応じて個別のアドバイスや支援を行います。さらに、特別支援が必要な生徒には、個別の学習計画が作成され、少人数での指導が行われることで、学習の理解を深めることができます。
このように、少人数制クラスはフィンランドの教育において、個々の生徒のニーズに応じた柔軟な指導を可能にしています。
効率重視の独自の時間活用法
フィンランドの授業時間は、他国と比較して非常に短いのが特徴です。例えば、小学校の1年生と2年生は、週に約19時間の授業を受ける一方で、授業時間は1回45分程度で、授業と授業の間には15分の休憩が設けられています。これにより、生徒は集中力を保ちながら学ぶことができます。
授業時間の短さは、学習の質を高める効果があります。フィンランドでは、授業の約30%が「自由時間」として設定されており、生徒は自分の興味に基づいて学ぶことができます。このように、短い授業時間でも生徒が主体的に学ぶ環境を整えることで、学習効率が向上し、結果として高い学力を維持しています。実際、フィンランドの生徒は、短い学習時間にもかかわらず、国際的な学力テストで高評価を得ています。このような教育方針は、学びの楽しさを重視し、ストレスを軽減することにも寄与しています。
教師の質を支える厳格な採用制度
フィンランドの教師採用基準は非常に厳格で、教育の質を確保するために高いハードルが設けられています。まず、教師になるためには修士号が必須であり、教育学部への入学試験は倍率が約13倍と競争が激しいです。入学試験では、教育に関する専門知識やテーマに基づくエッセイが求められます。
採用後も、フィンランドでは教員の専門性を維持するために定期的な研修が行われています。例えば、教員は毎週2時間の専門的な発展のための時間が与えられ、最新の教育方法や技術を学ぶ機会が提供されています。さらに、教員は自らの授業を評価し、改善するためのフィードバックを受けることが奨励されており、これにより教育の質が常に向上する仕組みが整っています。このような取り組みが、フィンランドの教育システムの成功に寄与しています。
国による充実した教育支援体制
フィンランドの教育支援体制は、すべての児童生徒が平等に学べる環境を提供するために非常に充実しています。特に、特別支援教育においては、一般的な支援、強化された支援、特別な支援の3段階のサポートが用意されています。これにより、特別なニーズを持つ生徒にも適切な教育が行われます。
具体的には、一般的な支援では、教室内での個別指導や学習環境の調整が行われ、強化された支援では、専門の教育者による追加の指導が提供されます。特別な支援が必要な生徒には、個別の教育計画が策定され、必要に応じて心理的サポートや言語療法なども受けられます。
また、フィンランドでは、教育費が無償で提供されるため、家庭の経済状況に関わらず、すべての子どもが教育を受ける機会を持っています。このような支援体制が、フィンランドの教育の質を高め、国際的にも高く評価される要因となっています。
3.フィンランドと日本の教育制度の違いは?

フィンランドと日本の教育制度には、いくつかの顕著な違いがあります。
・授業時間: フィンランドでは、年間190日の授業が行われ、1時限は45分程度です。生徒は1日5〜7時間の授業を受け、夏休みが長いのが特徴です。
一方、日本は年間約210日の授業があり、1時限は50分から60分で、授業時間が長く、学期中の休暇も短いです。
・評価システム: フィンランドでは、成績評価は教師の裁量に委ねられ、標準化されたテストは少なく、個別の学びを重視します。
日本は定期試験や入試が重視され、成績が競争の基準となるため、学業のプレッシャーが高いです。
・教師の待遇: フィンランドでは、教師は高い社会的地位を持ち、修士号が必須で、教育の質が重視されます。教員の選抜は厳しく、待遇も良好です。対照的に、日本では教員の労働環境が厳しく、長時間労働が常態化しており、教員不足が問題視されています。
このように、両国の教育制度は、授業の進め方や評価、教師の地位において大きな違いがあります。
成績評価から見る教育理念の違い
フィンランドと日本の成績評価システムには、根本的な違いがあります。
・評価方法: フィンランドでは、成績評価は主に自己評価と教師による評価が組み合わさっています。生徒は自分の学習目標を設定し、達成度を自己評価することが多く、教師はその結果を基にフィードバックを行います。例えば、学期末には10段階の成績表が渡されますが、日常的にはテストや偏差値による評価は行われません。
対照的に、日本では5段階評価が一般的で、成績は定期試験や課題の点数に基づいて決定されます。例えば、数学のテストで90点を取った場合、他の生徒との比較により成績が決まります。このため、競争が生じやすく、学習へのプレッシャーが高まる傾向があります。
このように、フィンランドは個々の成長を重視し、日本は相対的な成績を重視するため、評価のアプローチが大きく異なります。
教師の待遇・採用基準の格差
フィンランドと日本の教師の待遇や採用基準には顕著な違いがあります。
・待遇: フィンランドでは、教師の社会的地位が高く、平均年収は約42,426ドル(約550万円)で、労働時間は週32時間程度と短いです。対して、日本の教師は平均年収が約48,919ドル(約650万円)ですが、勤務時間は週56時間に達することもあり、長時間労働が常態化しています。
・採用基準: フィンランドでは、教師になるためには修士号が必要で、教育課程は厳格です。これにより、高い専門性を持つ教師が確保されています。日本では、教員免許を取得するための基準は比較的緩やかで、大学卒業後に教員採用試験を受けることが一般的です。
・影響: フィンランドの教師は、職業に対する満足度が高く、教育の質も向上しています。一方、日本では長時間労働やストレスが教師の離職率を高め、教育の質に影響を及ぼしています。このように、待遇や採用基準の違いは、教育現場の環境や教師の職業満足度に大きな影響を与えています。
4.子どもの能力を伸ばすフィンランド教育のポイント

フィンランド教育は、子どもの能力を最大限に引き出すために、以下のポイントを重視しています。
教育の基本理念
・平等性: すべての子どもが質の高い教育を受ける権利を持ち、経済的な格差にかかわらず同じスタートラインに立つことができるように教育が無償で提供されます。
具体的な教育アプローチ
・少人数制: クラスの人数が少なく、教師一人あたりの生徒数も少ないため、個別指導が可能です。これにより、教師は生徒一人ひとりの進度やニーズに応じた指導ができます。
・自主性の尊重: 生徒が自分で学習計画を立て、自主的に学ぶことが奨励されます。これにより、独創性や問題解決能力が育まれます。
・プロジェクト学習: 生徒が自ら問題を見つけ、解決する力を養うために、プロジェクト学習や協働学習が重視されています。実践的な学びを通じて、社会に出てからも役立つスキルを育成します。
・教師の専門性と自律性: 教師は高い専門性を持ち、教育課程の内容や方法についての自律性が認められています。これにより、教師は自らの専門性を活かして教育を行うことができます。
これらのアプローチにより、フィンランドの教育システムは子どもたちの能力を効果的に伸ばすことを目指しています。
自主性を育てる学習アプローチ
フィンランドの教育システムは、生徒の自主性を育てることを重視しています。このアプローチは、学習者が自らの興味や関心に基づいて学ぶことを促進し、独創性や問題解決能力を育むことを目的としています。
具体的な実践例
・自主学習の時間: フィンランドの小学校では、授業の約30%が「自由時間」として設定されており、生徒は自分の興味に基づいて学ぶことができます。この時間を利用して、好きなテーマについて調査し、レポートを作成することが奨励されています。
・プロジェクトベースの学習: 生徒はチームで協力し、実際の問題を解決するプロジェクトに取り組むことが多いです。例えば、環境問題に関するプロジェクトでは、調査、討論、プレゼンテーションを通じて学びを深めます。
・個別の学習計画: 教師は生徒一人ひとりの学習スタイルや進度に応じた個別の学習計画を作成し、自主的な学びをサポートします。
これらのアプローチにより、フィンランドの教育は生徒の主体性を高め、学習意欲を引き出しています。
自主性を養うためには、家庭学習をとりいれるのも一つの方法です。毎月決まった量を計画的に自ら学ぶことができる家庭用通信教育教材を利用することで、自ら学ぶ習慣づくりができますよ。
読書で培う思考力と創造性
フィンランドの教育システムでは、読書が思考力と創造性を育む重要な要素とされています。読書を通じて、子どもたちは批判的思考や問題解決能力を養い、創造的なアイデアを生み出す力を高めます。
具体的な活動例
・読書時間の確保: フィンランドの学校では、授業の中に読書の時間が設けられており、生徒は自分の興味に合った本を自由に選んで読むことができます。この自主的な読書は、自己表現や感情の理解を深める助けとなります。
・読書感想の共有: 生徒同士で読んだ本について意見を交換する活動が行われます。これにより、他者の視点を理解し、自分の考えを論理的に表現する力が養われます。
・クリエイティブライティング: 読書後に物語を創作する課題が出されることもあります。これにより、想像力を働かせながら、物語の構成やキャラクターの設定を考える力が育まれます。
このように、フィンランドの教育では読書が思考力と創造性を高めるための基盤となっています。
実践的な問題解決力の育成法
フィンランドの教育方法は、実践的な問題解決力を育成することに重点を置いています。このアプローチは、学生が自ら考え、協力しながら課題に取り組むことを促進します。
具体的な手法
・現象ベース学習: 教科の枠を超えた学習方法で、学生は実際の問題やテーマを探求します。例えば、環境問題をテーマにしたプロジェクトでは、科学、社会、アートなどの視点からアプローチし、解決策を考えます。
・グループワーク: 学生同士が協力して問題を解決する活動が多く取り入れられています。例えば、数学の授業では、学生がグループで問題を解き、意見を交換しながら理解を深めます。
・反省的実践: 教師は学生の学びを観察し、フィードバックを行います。これにより、学生は自分の考えを振り返り、次回の課題に活かすことができます。
このように、フィンランドの教育は実践的な問題解決力を育むために、協働的で反省的な学びを重視しています。
5.フィンランド教育の課題と将来展望
フィンランドの教育は、かつての高い学力で知られていましたが、近年はさまざまな課題に直面しています。特に、国際学力調査PISAにおいて、読解力や数学的リテラシーの順位が低下していることが問題視されています。これには、移民の増加による教育の均一性の確保が難しくなっていることや、教師の負担が増加していることが影響しています。
具体的な問題点としては、以下のようなものがあります。
・学力の格差: 移民背景を持つ生徒と非移民生徒の間で学力差が拡大している。
・教師の負担: 教師が多様なニーズに応えるための負担が増加し、教育の質が低下するリスクがある。
これらの課題に対する解決策としては、以下が考えられます。
・特別支援の強化: 学習に困難を抱える生徒に対して、より手厚い支援を提供することで、学力の均一化を図る。
・教師のサポート体制の充実: 教師の負担を軽減するために、教育資源やサポートスタッフを増やし、教育環境を改善することが求められます。
将来的には、これらの対策を通じて、フィンランドの教育システムが再び国際的に評価されることが期待されています。
デジタル化への対応と新たな挑戦
フィンランドの教育は、デジタル化に積極的に対応しており、特にICT(情報通信技術)の導入が進んでいます。教育政策では、デジタルリテラシーが早期からカリキュラムに組み込まれ、学生は小学校からデジタル技術を学び始めます。
具体的な取り組みとしては、以下の点が挙げられます。
・デジタル教材の活用: 学校では、クラウドベースのプラットフォームやデジタル教材を使用し、個別化された学習を促進しています。
・AIの導入: 一部の学校では、AIを活用した学習プラットフォームを導入し、生徒の理解度に応じた個別指導を行っています。
・メディアリテラシー教育: メディアリテラシーが教育の一環として長年にわたり実施されており、学生はさまざまなメディアを分析し、批判的に考える力を養っています。
これらの取り組みを通じて、フィンランドはデジタル社会に適応した教育を実現しようとしています。
教育制度への疑問の声
フィンランドの教育制度は、かつては世界的に高く評価されていましたが、最近ではいくつかの疑問や批判が浮上しています。特に、PISA(国際学力調査)の結果が低下していることが問題視されています。2022年の調査では、数学や読解力、科学の成績が大幅に下がり、フィンランドの教育の質に対する懸念が高まっています。
具体的な批判としては、以下の点が挙げられます。
・教育の平等性の低下: 教育資源の減少や社会経済的格差の拡大が、特に低所得層の生徒に影響を与え、学力差が広がっているとの指摘があります。
・デジタル化の影響: ICT教育の導入が進む一方で、過度なデジタル依存が学力の低下を招いているとの意見もあります。
・教師の負担増: 教員の多忙化が進み、個別指導が難しくなっていることが、全体の学力低下につながっているとされています。
これらの問題は、フィンランドの教育制度が直面している重要な課題です。
6.「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てる

幼児期における「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てることは、子どもの健全な成長にとって非常に重要です。このアプローチは、シュタイナー教育などの教育法でも強調されており、子どもが多面的に成長するための基盤を築くことを目的としています。
日本の教育においても、これらの要素をバランスよく育てることが求められています。特に、幼児教育の現場では、遊びを通じた学びが重視され、子どもたちが自らのペースで成長できる環境を整えることが重要です。これにより、子どもたちは心身ともに健康で、社会に適応できる力を身につけることができます。
幼児ポピーの学習教材「幼児ポピー」は、毎月届く紙を中心とした教材で、親子のふれあいを楽しみながら、いきいきとした脳を育み、人間力の基盤となる力を培います。

通信教材「幼児ポピー」は、全国の小・中学生を対象にワークブックやドリル、問題集などの学習教材を発行している「新学社」が制作している家庭学習教材です。学校教材作りのノウハウも活かされた「幼児ポピー」は、創刊以来50年以上にわたり多くのご家庭で愛用されています。
「続けられるか不安」「子どもが興味をもつかわからない」という場合は、無料おためし見本から始めてみるのがおすすめです。
「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。
同カテゴリの人気記事
 お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介
お子さまのタイプ別「幼児ポピー」教材紹介
 「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!
「うちの子にぴったりの学習スタイルは?」5つの選択肢を徹底比較!
 幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について
幼児教育とは?親が持つべき心構えと教育の種類について
 絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?
絵本の読み聞かせが子どもに与える効果とは?
 フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?
フィンランド教育の驚くべき秘密!世界一の理由と特徴とは?
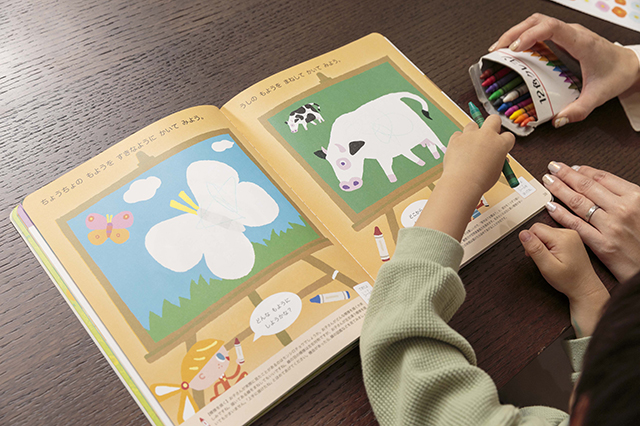 4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説
4歳の教育を最大化!実践的な勉強法や学習サポートについて解説
 空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法
空間把握能力を鍛える!子どもの成長を加速するトレーニング方法
 2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説
2歳児に必要な幼児教育のポイントを発達の特徴を踏まえて解説
 エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!
エリクソンの発達段階って何?年齢別の発達課題を抑えて子育てに活かそう!
 アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?
アドラー心理学を子育てに活かす方法とは?
 知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説
知的好奇心とは?高める方法とメリットを徹底解説
 プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説
プログラミング的思考とは?メリットと鍛え方を徹底解説
 リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!
リトミックとは?年齢別の効果とやり方やメリットを徹底解説!
 英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法
英才教育とは?子供の才能を伸ばす方法
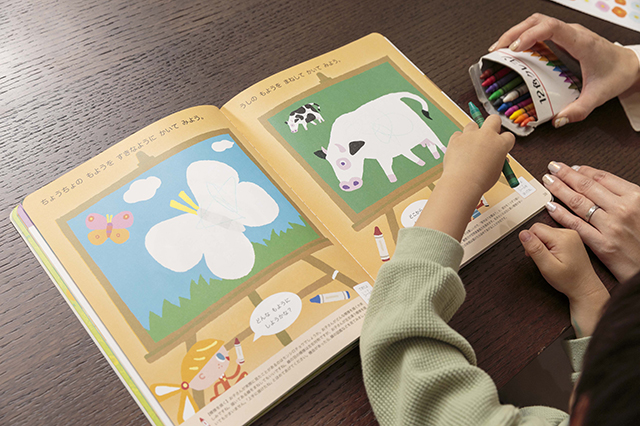 年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?
年少におすすめのワークはこれ!3歳用の市販の100均ドリルとの違いは?
 年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう
年長におすすめのドリル&ワークはこれ!入学前に「学ぶ力」を育てよう
 2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?
2歳におすすめのワーク!100均ドリルとの違い。ドリルはできない?
