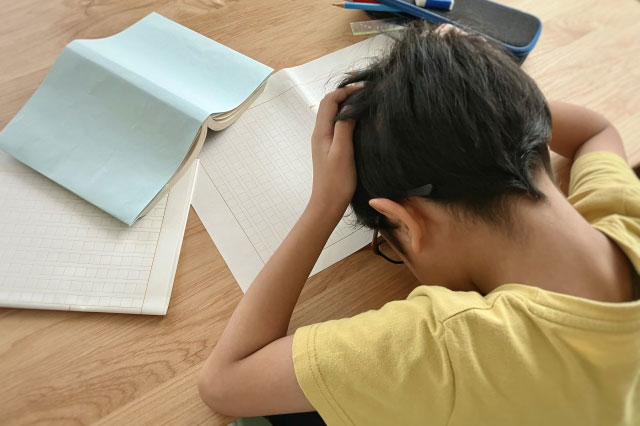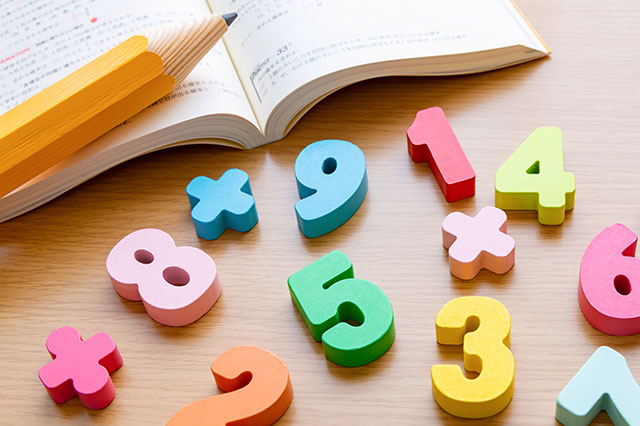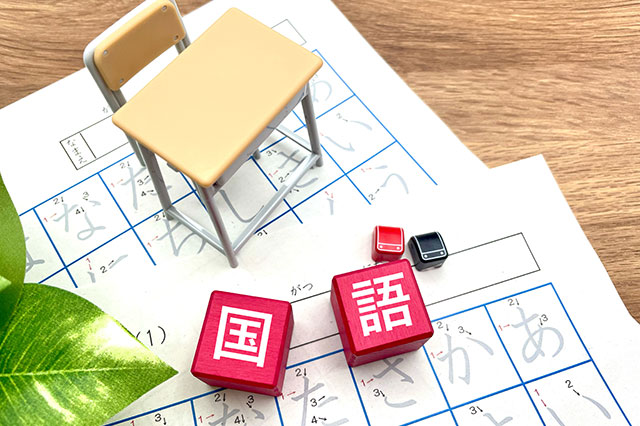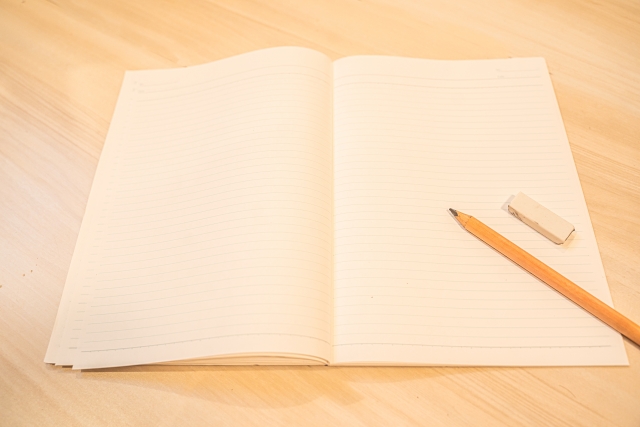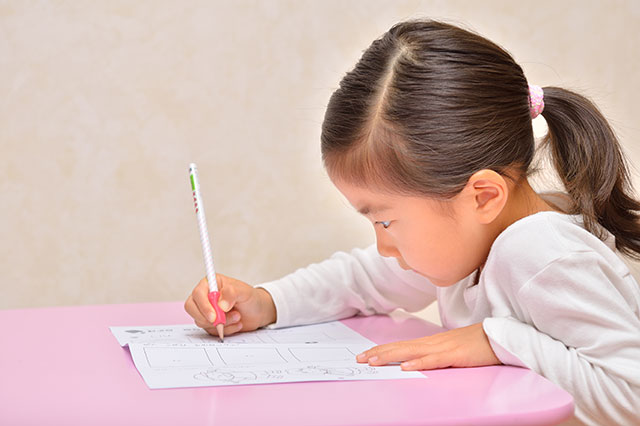小学生の通信教育は紙教材がおすすめ!
比較ポイントと“不要ではない”理由を解説
更新日:2025年10月20日

通信教材、塾、市販のドリルなど、小学生の学習スタイルはさまざまです。どれを選ぶかで、学習方法や効果も変わります。
さらに通信教材でも、「紙教材」か「デジタル教材」か、我が子に一番合う学習スタイルはどれだろう?とお悩みの方は少なくないでしょう。
教育現場でもデジタル教材が主流になる中、紙教材ならではの価値が改めて注目されています。
本記事では、紙教材がおすすめな理由やデジタル教材・市販ドリルとの比較ポイント、さらに「通信教育は不要?」という疑問への答えを解説します。
小学生の学びを最大限に活かす通信教育選びに、ぜひお役立てください。
小学生の通信教育は紙教材をおすすめする3つの理由
小学生の通信教育を選ぶとき、教材の形式は大きなポイントです。 最近はタブレットを使ったデジタル教材も増えていますが、紙教材にはデジタルにはないメリットがあります。 ここでは、小学生の通信教育に紙教材をおすすめする3つの理由をご紹介します。
1.思考力・記述力が身につく
紙教材では、問題を読んで自分の手で書きながら解くため、思考のプロセスを自然と整理する力が育ちます。 タブレットのように選択肢をタップするだけでなく、「どうしてそうなるのか」を自分の言葉で書く経験が、思考力や記述力を養う大きなポイントです。 また、書き直しやメモを取る過程で、自分なりの「考えるクセ」も身につきます。これは高学年になってからの作文や説明問題にも大いに役立ちます。
2.記憶定着が良い
手を動かして「書く」ことで脳が活性化し、学んだことが記憶に残りやすくなります。立命館大学×KOKUYOの共同研究でも、紙教材による学習はタブレット学習に比べて記憶定着率が約20%高いことが実証されています。特に「見返しやすさ」「覚えやすさ」に加え、脈波で測るリラックス度合いやストレス度合いでも、紙の筆記に有意な差が見られています。
3.学校のテストに備えられる
小学校のテストは今も紙で実施されるのが一般的です。 普段から紙教材で学習しておくことで、鉛筆を使って書くスピードやマーク位置の感覚など、実際のテスト形式に慣れることができます。 また、紙に書いて答える練習は、見直しや計算過程の確認など、本番でのケアレスミス防止にもつながります。 「紙で学ぶ→紙でテストする」という一貫した学び方が、安心感と自信を生み出します。
ポピー会員に聞いた!「タブレット教材から紙教材に切り替えた理由」
実際に「タブレット教材」から紙教材の「ポピー」に切り替えられたポピー会員さまからの口コミをご紹介します。
- 「タブレット学習のようにお任せには出来ないけど、子どもがどこが得意でどこが苦手か把握する機会になる。」
- 「タブレット学習だと適当にボタンを押したりしていて、理解しているつもりになっていた。」
- 「紙教材の方が学習内容の定着率が高いと思う。」
- 「タブレットではなく紙の教材なので、頭や目に優しいのがいい。」
- 「我が家はWi-Fiが全部屋に完璧に届くわけではないためタブレット学習は不向き。」
- 「普段デジタル時間が増えているからこそ、ポピーでデジタルから離れる時間を持てるのがいい。」
- 「紙に書いて間違ったら消しゴムで消す!という行動で情報が頭に入りやすいと思う。」
このように「理解度の把握」「学びの定着」「健康面への配慮」「Wi-Fiなどのネット環境」などを重視し、タブレット教材から切り替えられているようです。
紙の小学生向け通信教材と市販のドリルの違いは?
紙の小学生向け通信教材と市販のドリルでは、使い方や学習効果に違いがあります。 通信教材は毎月届く冊子で計画的に学習できるのが特徴で、教科書に沿った内容で学習習慣を身につけやすい点が魅力です。 一方、市販のドリルは自由に選んで取り組める反面、量や内容の調整は家庭に任されることが多く、子どもに合った学習計画を作る工夫が必要です。 ここでは、市販のドリルと比べる視点で、紙の通信教材の特徴について整理します。
特徴①:毎月届く楽しみと継続性
通信教材は毎月新しい教材が届くため、子どものモチベーションを保ちやすく、自然に学習習慣が身につきます。市販のドリルは購入後に取り組むかどうかが子ども次第で、習慣化しづらいことがあります。
特徴②:学習量が適切で負担が少ない
市販のドリルは学習量や内容がさまざまで、自分の子どもに合ったものを見つけるのが難しい場合があります。一方、通信教材は学年に合わせて学習量が調整されているため、習い事や生活リズムに合わせて無理なく学習できます。また、ポピーなら教科書準拠の教材で学校の授業に合わせて学べるため、理解度を高めながら学習を進められます。
「市販の問題集」と比較したポピー会員さまからの口コミをご紹介します。
- 「問題集などはたくさん書店にも並んでるけど、程よいボリュームでなおかつ子どもが集中して取り組める教材で助かってます。」
- 「毎月新しいものが届くという楽しみもあり、1学年分のドリルを本屋さんで買うのをやめました。」
- 「難しい市販の問題集を検討したこともありましたが、レベルに合ったものでないと学習の習慣は身についていなかったと思います。」
プロが教える小学生向け通信教育を選ぶ際のおすすめ比較ポイント!
小学生向けの通信教育は種類も多く、選び方に迷う保護者も多いはずです。 特に紙教材を選ぶ場合は、価格だけでなく「内容」「継続性」「安心感」など複数の視点から比較することが大切です。 ここでは、教材選びの際に注目したい4つの比較ポイントをご紹介します。
費用
通信教育は継続して取り組むことが重要なので、月額費用や年間トータルのコストは大きな比較ポイントです。 紙教材はデジタル教材に比べて比較的安価な場合もあり、付録やサポート内容によって差が出ます。 無理なく続けられる費用設定かどうかを確認することが大切です。
教科書準拠の内容
小学生の学習は学校の授業進度に沿って進めることが理解定着の鍵になります。 教科書準拠の教材なら、授業の予習・復習がしやすく、学校のテスト対策にも直結します。 特に紙教材は、ページ構成が見やすく、教科ごとの学びを整理しやすいのが特徴です。
出版元会社の歴史
出版元の歴史や実績は、教材の信頼性に直結します。長年教育に携わってきた会社の教材は、教科書準拠や子どもの学習効果を考えた設計になっていることが多いです。教材選びの際は、出版元の歴史や教育方針をチェックすることも重要です。
付録の有無
付録の有無は教材の魅力に影響します。一方で、付録が多すぎると学習の本質から外れてしまう場合もあります。余分な付録のない通信教育は、シンプルに学びに集中できるメリットがあります。教材選びでは、付録の内容と学習目的のバランスを考えましょう。
小学生向け通信教育の紙教材が不要と言われる理由
近年、『小学生向け通信教育に紙教材は不要』という意見をよく見かけます。特に塾に通っている場合や、タブレット教材が普及していることから、紙教材は必要ないと考える保護者もいるようです。ここでは代表的な不要理由とその理由と考え方のポイントを紹介します。
理由①:塾に通っているから不要
塾で“すべて完結している”お子さんには、通信教材は必ずしも必要ではありません。 しかし、そうでないご家庭――たとえば「塾では理解できたと思ったのに、家で解くとつまずく」場合には、紙の通信教材が力を発揮します。 教科書に沿った紙教材なら、自分のペースで何度も復習でき、塾で学んだ内容を“自分のものにする”手助けになります。
理由②:タブレット教材があるから不要
タブレット教材は手軽で多機能ですが、短時間の利用や選択型の学習になりがちです。 紙教材は自分のペースでじっくり取り組めるため、思考力や記述力を育む点で強みがあります。 特に漢字・計算・文章問題など、繰り返し書いて定着させたい分野では紙教材の価値は大きいです。
小学生向け通信教育の紙教材のデメリット。向いていない人は?
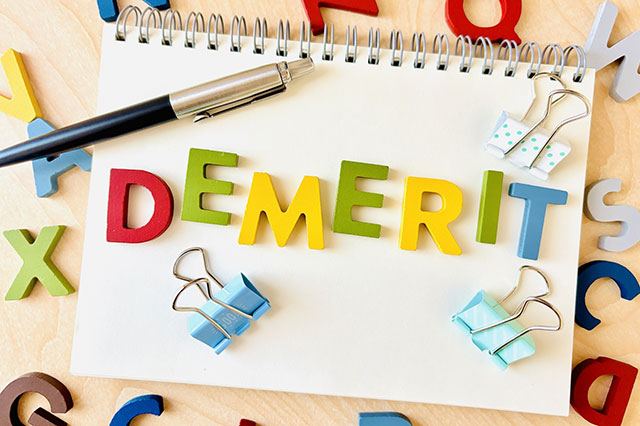
紙教材の通信教育には多くのメリットがありますが、すべてのご家庭にとって最適とは限りません。 ここでは、あえて紙教材のデメリットと、うまく活用するための工夫を紹介します。
デメリット①:親の見守りが必要
紙教材は、子どもが自分から進めるよりも保護者の声かけが必要な場面があります。 ただし、「今日ここまでやってみよう」と軽く習慣づけるだけでも十分。 スケジュール表やシールなどを使って達成感を見える化すると、子どもが自発的に進めやすくなります。
デメリット②:丸つけや採点に手間がかかる
紙教材はタブレットのように自動採点ができないため、丸つけの手間がデメリットに感じられることがあります。 ただ、この時間は「親子で学びを振り返る大切な機会」。 一緒に見直すことで理解が深まり、会話の中で学ぶ姿勢や考え方も育ちます。
デメリット③:教材の保管場所が必要
紙教材は続けると冊子が増え、収納に困ることも。 ただし、月ごとにファイルで整理するなど、家庭学習の記録として残すことで、後からの復習にも役立ちます。 形として残るのは、紙ならではのメリットにもなります。
小学生向け通信教育の費用の相場と比較
小学生向けの通信教育は、教材の内容や形式によって月額費用が大きく異なります。ここでは主要な通信教材の月会費(毎月払い)を比較してみましょう。
| 学年 | ポピー | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|---|
| 小1 | 3,300円 | 4,020円 | 4,730円 | 5,600円 |
| 小2 | 3,600円 | 4,320円 | 5,170円 | 5,880円 |
| 小3 | 4,100円 | 5,320円 | 6,160円 | 9,700円 |
| 小4 | 4,300円 | 5,590円 | 7,040円 | 10,600円 |
| 小5 | 4,700円 | 6,710円 | 8,030円 | 12,200円 |
| 小6 | 5,000円 | 7,150円 | 8,580円 | 12,200円 |
小学生向け通信教育(紙教材)の全学年平均は約7,000円。 ポピーは約4,000円と、月額3,000円以上安いため、長く続けやすい教材です。 学年が上がるほど費用差が広がり、きょうだいがいる家庭にもおすすめです。
紙教材はタブレット教材のように端末費や通信費が不要なため、初期費用を抑えて始められるのも魅力のひとつです。 学習効果をしっかり得ながら、コストを抑えたいご家庭には、紙教材の通信教育がぴったりといえるでしょう。
まとめ
紙の通信教材、デジタルの通信教材、市販の問題集、塾など、学習スタイルはさまざまです。それぞれに良さがあり、費用や学習環境、子どもの性格によって向き不向きがあります。 大切なのは、子どもに合った方法を選び、学びを続けられる環境を整えることです。
「月刊ポピー 教育情報サイト」は、子育て世代や教育に関心のある保護者の皆さまに向けて、信頼性の高い情報を発信する教育情報メディアです。家庭学習教材「月刊ポピー」を提供する新学社のノウハウを活かし、子どもの学力・生活・心の成長に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。